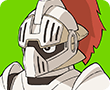![]()
2WEEKS 人形使いのペトルーシュカ
人間的でありすぎることへの不安
レビュアー:横浜県 ![]()
主人公の上代雪介には、死んだ人間を生き返らせる力があった。そんな彼の前に、ホルマリン漬けにされた自分の子供を復活させようと目論む女が現れる。雪介は一度、その要求に従う。しかし彼の能力にも限界はあった。やがてその子供は目を開けなくなってしまう。
女は怒り狂い、再び雪介を呼び出すが、彼は打つ手がないと拒絶する。
そんなとき、妙生が姿を見せる。やつはネクタールという名前の宇宙人だ。そして妙生は、その子どもを燃やしてしまった。これで生き返らせることもできない。子どもは完全に消滅してしまった。
この一節を読んだとき、なんと呆気ないのだろうと思った。ヒロインの黒戸サツキが後に語っているが、「好きな人を生き返らせたいと思うのは、自然なこと」である。それには雪介も同意している。それは至極、人間的な感情だった。
一方で、死者を生き返らせるという能力に対して雪介が見せる拒否反応もまた、きわめて人間的なものであるといえるだろう。彼はその能力を用いて、逆説的な話ではあるが、人を殺す結果にいたってもいる。そのような代物を彼が禁忌として捉えるのも当然だと言える。事実、エピローグの最後で、彼は「僕は、能力で人を殺している。こんな綺麗な涙、ありえない」と自らの能力とそれを用いての行為に対して懺悔するかのような心情を吐露している。
しかしそんな両者による葛藤は、妙生という超越的な存在によって一蹴されてしまった。彼は「どうせもう生き返らないだろ」とあっさり言い捨てる。もう生き返らせたくなかったはずの雪介でさえ「お前なにしてんだよ!」と驚いているにも関わらずだ。ちなみに女は無言のまま佇んでいた。
妙生はその後、「理由なんてないんだ。人間見たく余計なことは考えたくない。人間ってさ、不完全な脳があるから、苦しんだり余計なことをごちゃごちゃ考えるんだよ」と説明する。これはとても皮肉だ。人間は誰しもが、つねに考えている。何かしらのものごとについて、悩み、理由を与え、納得しようとする。あるいは受け入れがたいものに対しては抗おうとする。しかし、妙生のように超越的な存在、あるいは運命と呼ぶのがよいのかもしれないところのものは、決してそのような人間の「考え」には囚われてくれない。それどころか、意に介することもなく、突如として妙生が子どもを燃やしてしまったように、呆気ない結末を提示する。
そして人間は誰しもが、その超越的な力からは逃れられない。黒戸は雪介に対し、女のような子供を生き返らせることに執着して幸せを逃すような、そんな人生にならないようにと誓いを立てさせようとする。雪介はそれを、「あの女の一生に触れて、不安になったのは僕だけじゃなかった」と評する。そして不安になるべきなのは二人だけではない。本作の読者もまた、人間的な感情に引きずられすぎることで、幸せを逃してしまうかもしれない。人生は、そんな感情にかまってくれやしない。
女の不幸は、つねに自分の不幸でもありうる。妙生が子どもを燃やしたとき、そんな不安を感じた。
女は怒り狂い、再び雪介を呼び出すが、彼は打つ手がないと拒絶する。
そんなとき、妙生が姿を見せる。やつはネクタールという名前の宇宙人だ。そして妙生は、その子どもを燃やしてしまった。これで生き返らせることもできない。子どもは完全に消滅してしまった。
この一節を読んだとき、なんと呆気ないのだろうと思った。ヒロインの黒戸サツキが後に語っているが、「好きな人を生き返らせたいと思うのは、自然なこと」である。それには雪介も同意している。それは至極、人間的な感情だった。
一方で、死者を生き返らせるという能力に対して雪介が見せる拒否反応もまた、きわめて人間的なものであるといえるだろう。彼はその能力を用いて、逆説的な話ではあるが、人を殺す結果にいたってもいる。そのような代物を彼が禁忌として捉えるのも当然だと言える。事実、エピローグの最後で、彼は「僕は、能力で人を殺している。こんな綺麗な涙、ありえない」と自らの能力とそれを用いての行為に対して懺悔するかのような心情を吐露している。
しかしそんな両者による葛藤は、妙生という超越的な存在によって一蹴されてしまった。彼は「どうせもう生き返らないだろ」とあっさり言い捨てる。もう生き返らせたくなかったはずの雪介でさえ「お前なにしてんだよ!」と驚いているにも関わらずだ。ちなみに女は無言のまま佇んでいた。
妙生はその後、「理由なんてないんだ。人間見たく余計なことは考えたくない。人間ってさ、不完全な脳があるから、苦しんだり余計なことをごちゃごちゃ考えるんだよ」と説明する。これはとても皮肉だ。人間は誰しもが、つねに考えている。何かしらのものごとについて、悩み、理由を与え、納得しようとする。あるいは受け入れがたいものに対しては抗おうとする。しかし、妙生のように超越的な存在、あるいは運命と呼ぶのがよいのかもしれないところのものは、決してそのような人間の「考え」には囚われてくれない。それどころか、意に介することもなく、突如として妙生が子どもを燃やしてしまったように、呆気ない結末を提示する。
そして人間は誰しもが、その超越的な力からは逃れられない。黒戸は雪介に対し、女のような子供を生き返らせることに執着して幸せを逃すような、そんな人生にならないようにと誓いを立てさせようとする。雪介はそれを、「あの女の一生に触れて、不安になったのは僕だけじゃなかった」と評する。そして不安になるべきなのは二人だけではない。本作の読者もまた、人間的な感情に引きずられすぎることで、幸せを逃してしまうかもしれない。人生は、そんな感情にかまってくれやしない。
女の不幸は、つねに自分の不幸でもありうる。妙生が子どもを燃やしたとき、そんな不安を感じた。