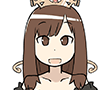![]()
『青春離婚』HERO
上手な息の吸い方。
レビュアー:オペラに吠えろ。 ![]()
僕はこの物語が好きだ。何度も読み返している。けれど、読み始めはいつもそっと本を閉じたくなる。実は、初読のときもそうだった。でも、物語のある時点で、ふっと救われた気がして、それからは物語に夢中になった。
今回は、その瞬間について、語りたいと思う。
佐古野郁美と佐古野灯馬。二人は、親戚関係でもなんでもないけれど、同じ名字だからという理由だけで学校で「夫婦」として扱われている。こういうのは、僕が通っていた学校でもあった。幸いなことに僕はその対象にならなかったけれど、なんて理不尽なんだ、と思っていたのを覚えている。でも、学生生活を卒業した今ならばよくわかるのだけれど、世の中には理不尽なことなんてたくさんあって、特に学校なんて理不尽なことばかりで、だから、子どもたちはそれとなんとか折り合いをつけていく。その手段は人によって違う。馴染んだり、耐えたり、うまくかわしたり。
この作品に登場する「夫婦」は、僕らが普段から経験する「理不尽なもの」の象徴として描かれる。そして、この作品に出てくる「妻」の郁美さんは、それに耐えることしかできない。いや正確には、耐えることすらできていない。「夫婦」と呼ばれるたびに左頬がつりあがってしまう彼女の拒否反応は、その現れだ。彼女はきっと、そういう理不尽なものをどう受け入れたらいいのか、よくわかっていない。まだ、世の中とうまくやっていく術を知らないのだ。だから彼女はもろく、あまりに痛々しく、まるで張り詰めた糸のように耐えて耐えて耐えて、あるとき、あっけなく切れてしまうのではないかと危惧してしまう。彼女が知るべきなのは、限界が来る前に力を緩める、そのやり方。けれども彼女は、そうした手抜きを当たり前のものだと思うには、あまりに不器用だった。
だから、「夫」になった灯馬さんが、そういうことに長けていたのは、郁美さんにとって、本当に幸運だった。灯馬さんは、理不尽なものをうまくかわす術に長けている。僕が本当にこの作品を好きだと確信したのは、第1回のラストだった。そのきっかけとなるのは、「夫婦」と呼ばれることに対しての「下手に抵抗すると逆効果だと思うので」という灯馬さんの言葉で、それに対して、郁美さんはこう思う。
「灯馬さんが 一番はじめにわたしに教えてくれたのは そういう上手い逃げ方であり 教室という狭い水槽の中での 上手な息の仕方だった」
……この上手な息の仕方を、まだ知っていない人は、どこにでもいるだろう。たとえば、僕がそうだった。学校時代の僕は人の顔色をうかがうばかりで疲れ果て、人の反応に一喜一憂し、それなのに、クラスからはホコリのように浮いていた。ひょっとすると、呼吸を楽にすることができる、ということすら知らない人もいるかもしれない。物語のはじめ、郁美さんがそうだったように。
だから僕は、この本が、僕が学生のころにあったらよかったのにな、と思う。「よい物語は人生のどの時期に読んでも面白い」とはいうけれど、きっと、人生の特定の時期に読むことが望ましい物語もあると思うのだ。僕は残念ながら、遅れてやって来てしまったけれど、今、まさに今、学校を息苦しいと思っている人は、ぜひこれを読んでほしい。今ならまだ間に合うはずだ。
上で、僕はこの物語に出てくる「夫婦」は、世の中にあふれる「理不尽なもの」の象徴だと書いた。それに対する郁美さんの答えは、タイトルにもあるとおりの「離婚」。僕は、その決断に至ることができた郁美さんを抱きしめてあげたい。彼女はきっと、もう、耐えることだけが自分の生きる道ではないとわかっただろうから。
今回は、その瞬間について、語りたいと思う。
佐古野郁美と佐古野灯馬。二人は、親戚関係でもなんでもないけれど、同じ名字だからという理由だけで学校で「夫婦」として扱われている。こういうのは、僕が通っていた学校でもあった。幸いなことに僕はその対象にならなかったけれど、なんて理不尽なんだ、と思っていたのを覚えている。でも、学生生活を卒業した今ならばよくわかるのだけれど、世の中には理不尽なことなんてたくさんあって、特に学校なんて理不尽なことばかりで、だから、子どもたちはそれとなんとか折り合いをつけていく。その手段は人によって違う。馴染んだり、耐えたり、うまくかわしたり。
この作品に登場する「夫婦」は、僕らが普段から経験する「理不尽なもの」の象徴として描かれる。そして、この作品に出てくる「妻」の郁美さんは、それに耐えることしかできない。いや正確には、耐えることすらできていない。「夫婦」と呼ばれるたびに左頬がつりあがってしまう彼女の拒否反応は、その現れだ。彼女はきっと、そういう理不尽なものをどう受け入れたらいいのか、よくわかっていない。まだ、世の中とうまくやっていく術を知らないのだ。だから彼女はもろく、あまりに痛々しく、まるで張り詰めた糸のように耐えて耐えて耐えて、あるとき、あっけなく切れてしまうのではないかと危惧してしまう。彼女が知るべきなのは、限界が来る前に力を緩める、そのやり方。けれども彼女は、そうした手抜きを当たり前のものだと思うには、あまりに不器用だった。
だから、「夫」になった灯馬さんが、そういうことに長けていたのは、郁美さんにとって、本当に幸運だった。灯馬さんは、理不尽なものをうまくかわす術に長けている。僕が本当にこの作品を好きだと確信したのは、第1回のラストだった。そのきっかけとなるのは、「夫婦」と呼ばれることに対しての「下手に抵抗すると逆効果だと思うので」という灯馬さんの言葉で、それに対して、郁美さんはこう思う。
「灯馬さんが 一番はじめにわたしに教えてくれたのは そういう上手い逃げ方であり 教室という狭い水槽の中での 上手な息の仕方だった」
……この上手な息の仕方を、まだ知っていない人は、どこにでもいるだろう。たとえば、僕がそうだった。学校時代の僕は人の顔色をうかがうばかりで疲れ果て、人の反応に一喜一憂し、それなのに、クラスからはホコリのように浮いていた。ひょっとすると、呼吸を楽にすることができる、ということすら知らない人もいるかもしれない。物語のはじめ、郁美さんがそうだったように。
だから僕は、この本が、僕が学生のころにあったらよかったのにな、と思う。「よい物語は人生のどの時期に読んでも面白い」とはいうけれど、きっと、人生の特定の時期に読むことが望ましい物語もあると思うのだ。僕は残念ながら、遅れてやって来てしまったけれど、今、まさに今、学校を息苦しいと思っている人は、ぜひこれを読んでほしい。今ならまだ間に合うはずだ。
上で、僕はこの物語に出てくる「夫婦」は、世の中にあふれる「理不尽なもの」の象徴だと書いた。それに対する郁美さんの答えは、タイトルにもあるとおりの「離婚」。僕は、その決断に至ることができた郁美さんを抱きしめてあげたい。彼女はきっと、もう、耐えることだけが自分の生きる道ではないとわかっただろうから。