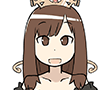![]()
ビアンカ・オーバースタディ 筒井康隆
ラノベ以前
レビュアー:鳩羽 ![]()
女性へのクールビズの提案として、通気性のよい服装の他に、涼しげな髪型やメイクが提案された。本来の目的であるクールビズに今更目新しさがないせいもあるが、「涼しげなメイク」に引っかかりを覚え、失笑してしまった女のひとは多いのではないだろうか。
そこに記述されている「涼しげ」の意味は、メイクをしている女性本人が涼しくなるためのものではなく、見る人が涼を感じるようなメイクという意味だった。「女は見られるもの」なのだから「見る人」のために留意しなさいというメッセージを堂々と送られたなら、まあ、やはりせいぜい苦笑いするしかない。
ほとんどの章が、
「見られている。
でも、気がつかないふりをしていよう。
気がつかないふりをしていると思われてもかまわない。
いつも見られているから平気なんだと思わせておけばいい。」
で始まる『ビアンカ・オーバースタディ』は、学校一の美少女であり生物研究部員であるビアンカが、ウニの繁殖の実験だけでは飽き足らなくなり、己の崇拝者である文芸部員の男の子から精子を抜きとり、その精子が孤独でかわいそうだからと自分の卵子をそばに置いてみたり、カエルとかけ合わそうとしたり、という、むちゃくちゃな実験がくり返される話である。
実は未来人だった生物研究部の先輩ノブや学校一美しいとされる燿子、ビアンカの妹のロッサも加わり、ビアンカたちの思いつきとノリだけでくりひろげられる実験は、肯定的にも否定的にも世界を変えうる爆発的な可能性を持っていることが示唆される。
ビアンカが見られていると感じるのは作中の男の子たちに対してであるが、メタラノベとして読むこともできると作者によるあとがきにもあるので、視点をもう一段上にあげ、ラノベとして読もうとする読者のことも視野に含めてみる。
すると、ビアンカは異性として見られると同時に、キャラとしての萌えどころを読者に探されている、ということができるだろうか。
「見ている」だけの存在でしかないうちは、「見えない」部分は存在していないかのように思いがちである。それがキャラクターならば「見えない」部分は設定されていない、つまり「見えない」イコール「無い」といっていいのかもしれない。現にビアンカが実験室以外の場所ではどう振る舞っているのかまったくうかがい知ることができない。
けれど、ビアンカは「見られている」ことを知っている。一方的に「見ている」はずの存在から、最初から「見られているのは分かっている」というメッセージを受け取るとき。それだけでなく、逆にこちら側を「見られて」いて発言をされるとき。そんなことをキャラクターに想定していなかった読者は驚き、その「見えない」部分があることが不気味に思えてくる。
未来の男たちは生殖能力が弱く、また現実の女は魅力的じゃないからと興味を持たなくなっており、ビアンカたちは漫画やアニメのキャラにしか興味がない男の子って私たちの時代にもいるよねと、ちくり毒を吐く。
これはビアンカにキャラ萌えやシチュエーション的においしい部分を探していた読者には、痛烈な皮肉に感じられるだろう。そもそも鑑賞している側が批評めいた意見を言うのは当然の権利で、「見られる」側は黙ってそれを受け入れるべきという暗黙の上下関係は、作者と読者の関係然り、芸能人と視聴者の関係然り、社会のあちこちで見て取れる。まして人間でないキャラクターなら、遠慮する必要もない。
その関係を、意図的ではないにしても、覆そうとするように見えるとき、ビアンカの例で言うなら、「おまえなんかには全然萌えない」「これはラノベじゃない」と、見えている部分を否定したくなるのだ。
だが、「萌えない」と思われても、「ラノベじゃない」と言われても、ビアンカも作者も気にも留めないだろう。むしろ、細かな心理描写やキャラ設定の説明もなしに、「見えない」部分を勝手に想像し肉づけして、あたかも現実の人間らしい存在感で読んでくれたと喜びすらしそうである。
属性を否定されて傷つくのは、その属性に愛着や誇りを持っている場合だけだろう。「ラノベのキャラらしくない」ことは、おそらくビアンカにとって至極どうでも良いことである。
放課後、という言葉の上にオーバースタディというルビがふってあるが、本来は「勉強のしすぎ」という意味が正しいらしい。
恋愛課程をすっとばして、物理的な受精や繁殖を行うビアンカ。
恋愛に関して、あるいは感動することに関して、フィクションから学びすぎるている、誰かさんたち。
ここで揶揄されているオーバースタディとは、一体どちらのことなのだろう。「見る」と「逢う」が同義だったのは遙か昔のこと、ボーイミーツガールすらままならなかったと言うなら、確かにこの小説はラノベとはいえないのかもしれない。
そこに記述されている「涼しげ」の意味は、メイクをしている女性本人が涼しくなるためのものではなく、見る人が涼を感じるようなメイクという意味だった。「女は見られるもの」なのだから「見る人」のために留意しなさいというメッセージを堂々と送られたなら、まあ、やはりせいぜい苦笑いするしかない。
ほとんどの章が、
「見られている。
でも、気がつかないふりをしていよう。
気がつかないふりをしていると思われてもかまわない。
いつも見られているから平気なんだと思わせておけばいい。」
で始まる『ビアンカ・オーバースタディ』は、学校一の美少女であり生物研究部員であるビアンカが、ウニの繁殖の実験だけでは飽き足らなくなり、己の崇拝者である文芸部員の男の子から精子を抜きとり、その精子が孤独でかわいそうだからと自分の卵子をそばに置いてみたり、カエルとかけ合わそうとしたり、という、むちゃくちゃな実験がくり返される話である。
実は未来人だった生物研究部の先輩ノブや学校一美しいとされる燿子、ビアンカの妹のロッサも加わり、ビアンカたちの思いつきとノリだけでくりひろげられる実験は、肯定的にも否定的にも世界を変えうる爆発的な可能性を持っていることが示唆される。
ビアンカが見られていると感じるのは作中の男の子たちに対してであるが、メタラノベとして読むこともできると作者によるあとがきにもあるので、視点をもう一段上にあげ、ラノベとして読もうとする読者のことも視野に含めてみる。
すると、ビアンカは異性として見られると同時に、キャラとしての萌えどころを読者に探されている、ということができるだろうか。
「見ている」だけの存在でしかないうちは、「見えない」部分は存在していないかのように思いがちである。それがキャラクターならば「見えない」部分は設定されていない、つまり「見えない」イコール「無い」といっていいのかもしれない。現にビアンカが実験室以外の場所ではどう振る舞っているのかまったくうかがい知ることができない。
けれど、ビアンカは「見られている」ことを知っている。一方的に「見ている」はずの存在から、最初から「見られているのは分かっている」というメッセージを受け取るとき。それだけでなく、逆にこちら側を「見られて」いて発言をされるとき。そんなことをキャラクターに想定していなかった読者は驚き、その「見えない」部分があることが不気味に思えてくる。
未来の男たちは生殖能力が弱く、また現実の女は魅力的じゃないからと興味を持たなくなっており、ビアンカたちは漫画やアニメのキャラにしか興味がない男の子って私たちの時代にもいるよねと、ちくり毒を吐く。
これはビアンカにキャラ萌えやシチュエーション的においしい部分を探していた読者には、痛烈な皮肉に感じられるだろう。そもそも鑑賞している側が批評めいた意見を言うのは当然の権利で、「見られる」側は黙ってそれを受け入れるべきという暗黙の上下関係は、作者と読者の関係然り、芸能人と視聴者の関係然り、社会のあちこちで見て取れる。まして人間でないキャラクターなら、遠慮する必要もない。
その関係を、意図的ではないにしても、覆そうとするように見えるとき、ビアンカの例で言うなら、「おまえなんかには全然萌えない」「これはラノベじゃない」と、見えている部分を否定したくなるのだ。
だが、「萌えない」と思われても、「ラノベじゃない」と言われても、ビアンカも作者も気にも留めないだろう。むしろ、細かな心理描写やキャラ設定の説明もなしに、「見えない」部分を勝手に想像し肉づけして、あたかも現実の人間らしい存在感で読んでくれたと喜びすらしそうである。
属性を否定されて傷つくのは、その属性に愛着や誇りを持っている場合だけだろう。「ラノベのキャラらしくない」ことは、おそらくビアンカにとって至極どうでも良いことである。
放課後、という言葉の上にオーバースタディというルビがふってあるが、本来は「勉強のしすぎ」という意味が正しいらしい。
恋愛課程をすっとばして、物理的な受精や繁殖を行うビアンカ。
恋愛に関して、あるいは感動することに関して、フィクションから学びすぎるている、誰かさんたち。
ここで揶揄されているオーバースタディとは、一体どちらのことなのだろう。「見る」と「逢う」が同義だったのは遙か昔のこと、ボーイミーツガールすらままならなかったと言うなら、確かにこの小説はラノベとはいえないのかもしれない。