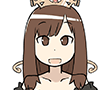![]()
一億総ツッコミ時代 槙田雄司
ツッコミ不可
レビュアー:鳩羽 ![]()
恐ろしい本である。
ツッコミたいところがあっても、ツッコメないという、ある意味レビュアー泣かせの本である。
「一億総ツッコミ時代」は、タイトル通り、誰もがあらゆる事柄に対してまるで平等であるかのように物申す、つまりツッコミを入れることの息苦しさを指摘する本だ。
誰でも簡単に情報を集め、取りまとめて、評価することができるようになった。何も知らない素人でも、マスコミのように上から目線で、あらゆる問題に意見を言えるようになった。お笑い芸人でなくても、ツッコミを入れるのが当たり前の人間関係にもなった。ある問題について知識を持っていなくても、簡単にそれは良い/悪いと判断することに抵抗がなくなったと言うこともできる。
そんなふうにツッコむ側にいるよりも、いつツッコまれるかとびくびくしているよりも、勇気を持ってボケて、ベタベタなことを全力で実行してみる。面白いか面白くないかを判別する側にいるのではなく、面白いことをしてみる。その方が幸せな人生を送れるのでは、という本なのだ。
恐ろしい本である。
これがまた、ツッコミたいところが満載の本なのだ。ツッコミを入れている人達と、ボケている人達はそんなにきっぱりと二分されているものなのだろうか、とか。
もちろん納得できるところもあるのだが、首を傾げるところも結構ある。でもそう言われると、ツッコメないではないか。
山藤章二著「ヘタウマ文化論」(岩波新書、2013年)と、切り口は違えどよく似た本のように思える。
こちらの本は、「ヘタ」から「ウマい」の一直線のルートだけではなく、「面白い」という文化が日本にはあったのではないかという着眼点から思いつくままに書かれた、エッセイである。ヘタウマとは、ウマいひとがわざわざヘタに表現することで、ヘタが一歩一歩芸術の道を歩んでいくのとは異なるルート、正道からちょっと外れた横道を粋であると面白がることである。
その精神的なゆとり、遊びの例として落語があげられているが、これは演じる側も観客の側も、共通の知識や教養が必要となる。何も知らないお客様が黙って座っているだけで楽しませてもらえるようなものではないし、自分を皮肉ること、毒がはけること、それをからりとした笑いに昇華できること、それが芸としてあるわけだ。
この二冊は、どちらも立川談誌の言葉を引いてきたり、タモリを登場させたり、瞬間に笑いが起こるような芸ではなくて、ちょっと知的な溜めがいるような笑いを尊重している点が似ている。
ヘタウマは、素人がただヘタにやってみせることとは違う。同様に、ちょっとアクのある毒舌めいたツッコミは、誰がやっても笑いとなる訳ではないのだ。
何が主流で、何が亜流なのか、判別しがたい時代なのではないかと思う。一般大衆が楽しんできた娯楽が大衆に共有されなくなり、通好みのような変わった嗜好が逆に一般的に広まったりもしている。
なればこそ、この著者が言うように、メタから一回り巡って敢えてベタに徹する。
なるほど、そういう生き方の方が、今度は変わっていて「おもしろい」ことになるのかもしれない。
ツッコミたいところがあっても、ツッコメないという、ある意味レビュアー泣かせの本である。
「一億総ツッコミ時代」は、タイトル通り、誰もがあらゆる事柄に対してまるで平等であるかのように物申す、つまりツッコミを入れることの息苦しさを指摘する本だ。
誰でも簡単に情報を集め、取りまとめて、評価することができるようになった。何も知らない素人でも、マスコミのように上から目線で、あらゆる問題に意見を言えるようになった。お笑い芸人でなくても、ツッコミを入れるのが当たり前の人間関係にもなった。ある問題について知識を持っていなくても、簡単にそれは良い/悪いと判断することに抵抗がなくなったと言うこともできる。
そんなふうにツッコむ側にいるよりも、いつツッコまれるかとびくびくしているよりも、勇気を持ってボケて、ベタベタなことを全力で実行してみる。面白いか面白くないかを判別する側にいるのではなく、面白いことをしてみる。その方が幸せな人生を送れるのでは、という本なのだ。
恐ろしい本である。
これがまた、ツッコミたいところが満載の本なのだ。ツッコミを入れている人達と、ボケている人達はそんなにきっぱりと二分されているものなのだろうか、とか。
もちろん納得できるところもあるのだが、首を傾げるところも結構ある。でもそう言われると、ツッコメないではないか。
山藤章二著「ヘタウマ文化論」(岩波新書、2013年)と、切り口は違えどよく似た本のように思える。
こちらの本は、「ヘタ」から「ウマい」の一直線のルートだけではなく、「面白い」という文化が日本にはあったのではないかという着眼点から思いつくままに書かれた、エッセイである。ヘタウマとは、ウマいひとがわざわざヘタに表現することで、ヘタが一歩一歩芸術の道を歩んでいくのとは異なるルート、正道からちょっと外れた横道を粋であると面白がることである。
その精神的なゆとり、遊びの例として落語があげられているが、これは演じる側も観客の側も、共通の知識や教養が必要となる。何も知らないお客様が黙って座っているだけで楽しませてもらえるようなものではないし、自分を皮肉ること、毒がはけること、それをからりとした笑いに昇華できること、それが芸としてあるわけだ。
この二冊は、どちらも立川談誌の言葉を引いてきたり、タモリを登場させたり、瞬間に笑いが起こるような芸ではなくて、ちょっと知的な溜めがいるような笑いを尊重している点が似ている。
ヘタウマは、素人がただヘタにやってみせることとは違う。同様に、ちょっとアクのある毒舌めいたツッコミは、誰がやっても笑いとなる訳ではないのだ。
何が主流で、何が亜流なのか、判別しがたい時代なのではないかと思う。一般大衆が楽しんできた娯楽が大衆に共有されなくなり、通好みのような変わった嗜好が逆に一般的に広まったりもしている。
なればこそ、この著者が言うように、メタから一回り巡って敢えてベタに徹する。
なるほど、そういう生き方の方が、今度は変わっていて「おもしろい」ことになるのかもしれない。