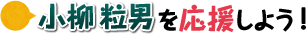若くもないけど真理に到達したな
2012.08.22
上京五日目、去年の12月25日の早朝二時過ぎのことだ。
僕は、真新しい半ヘルメットをかぶり、借り物の手袋をはめ、配達用の前カゴがついたスーパーカブにまたがっていた。
エヴァやガンダムの専属パイロットじゃないんだから、有り得へんぐらいの失敗なんて腐るほどするはずだ、と想い続け、転んでしまったときの言い訳にしようとしていた。
カブ、バイク、原付に乗ることが初めてだった。
例のごとく、バイクの疾走シーンを心象風景とするような漫画やアニメなどはいくらか知っていたので、とにかくそういうシーンを思い浮かべたり、そういうアニメの主題歌などを脳内再生することで、気持ちだけでもあげていこうとしていた。そうでもしないと、恐怖に飲まれてしまってあっさり事故ってしまう光景しか浮かばなかった。
初日は、年下の先輩のあとをバイクでついていき、配達順路を覚えるだけの作業だった。ただバイクを走らせるだけの作業である。簡単な単純な作業だったかもしれない。
6時過ぎに配達終わった直後の僕は、ただバイクを走らせていただけなのに、疲労困憊だった。
エンジンがなかなかかからない、途中でエンジンが切れてしまう、Uターンで転けそうになる、シフトを3に切り替えることをためらう。
配達の順路を覚える以前に、バイクの乗り方という段階でもう駄目だった。完全にいっぱいいっぱいになっていた。余裕が一個もなくなっていた。
部屋へ戻ると、床の上に倒れるようにして、しばらく休んだ。このときはまだ着替えの入った旅行バックと持参したパソコンぐらいしか部屋にはなにもなく、枕や布団や毛布すらなかった。近場にドンキや東急があることはわかっていたのだから真っ先に買いにいけばいいのだが、そういうことがなかなかできないのが僕というクオリティのようだった。
つけっぱなしにしておいたパソコンの液晶を見つめながら、僕は床に寝っ転がったまま、ぼっーとしていた。これから6時間後ぐらいから夕刊がある。6時間だなんて十分長い時間のはずなのに、ずいぶんあっという間な気がした。
こんなんで小説書けるのかな。
ぼっーとダレながら、そんなことを考えた。
ちょっと休めばすぐに書きたいという気持ちは出てくるはずだった。小説を書くベストな時間帯は寝起きの直後であることもわかっている。体と頭が疲れてきっていたせいで、気持ちが塞がっていた。
パソコンと荷物ぐらいしかない、妙に肌寒い部屋のなか、固い床の上に半身になって僕は眠りについた。
三が日が終わった直後から、一人で配達することが決まっていた。それまでにバイクに慣れて、配達順路も覚えて、小説も書いて、洗濯してシャワー浴びて、毛布も買って、弁当も買って。
生きるんてつらいなぁ。
そんな真理を感じたのは、この日が初めてだった。渡辺さんにキレられたときも、上京していろいろ断れたときも、そんな真理に到達することはなかった。ただ単に自らの力量の無さを悲しく思うだけだった。
でもこのときばかりは、そう思った。ここでやっていけるかなぁ、やれないのかなぁ、と。
体力も気力も魂も自信も余裕も、なくなっていた。
配達所の隅にいた女の子の存在に気付くこともないくらい、とにかくこのときの僕に余裕などは一切なかった。
「慣れ」という概念が、すべてをどうにかしてくれるわけだけど、そんなことに気付けるほど、聖夜当日の僕に余裕はなく、不安と疲弊を抱えながら、一人で配達することになる三が日へ向けて、怯え続けていた。
小柳粒男の作品
(このリンクよりご購入頂いたアフィリエイト収入は作家活動への応援として、小柳粒男へお送り致します)
本文はここまでです。