
NON STYLE 石田の明語
佐藤友哉 第四回
良く晴れた日の午後、星海社に訪れたのは、漫才コンビ NON STYLEの石田明。お馴染みの真っ白な衣装ではなく、私服での登場なのは今日が漫才の仕事とは少しちがった内容だから。2008年、M-1グランプリの王者に輝いた彼が今回から挑むのは、対談。同じ言葉を操る人々と「言葉」を使い、「言葉」を巡る旅の始まりです。
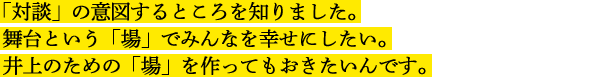
対談の最後は互いへの質問と感想を。
作家・佐藤友哉の意外な発言に、デビューから見守る担当・太田克史も思わず参戦か?
―― 今回、ある意味、それぞれの戦い方を披露していただいたような対談で、非常に楽しく伺いました。これはきっと戦い方がわからない人、あるいは戦うことすらわからない人に向けて、大切なヒントになるかと。もちろん、すべての人が戦えばいいというわけではありませんが。そして最後に、お互いに質問があればお願いします。
佐藤 単純に伺いたいことがふたつあります。ひとつめは、芸人さんが書いた小説をどう思われますか? ふたつめは、石田さんは小説を書きますか?
石田 あー……僕は仕事柄いただくことが多いので一応は読みますが、そこで刺激を受けることはほとんどありません。よく「書いてくれ」とも言われていて、断り続けて、それでも断り切れずに趣味っぽく書いてみたりもしたんですが、結局は舞台向けに落とし込んだ方がおもしろいものが作れるので、今はあくまで趣味の範囲で書いています。ただそれも、むっちゃ時間があるときにお酒を飲みながら、という程度です。
佐藤 それは世には出ないんですか?
石田 今のままではとても出せないですね。もっと50代、60代になって時間に余裕ができて、自分の言葉に重みが出てきたら……とは思いますが。今現在は小説よりも戯曲を書いて世に広めて、世の人を刺激したほうが得策かなと思うんです。
佐藤 「得策」とおっしゃいますか。それを。
―― 幸せとか、楽しいではなくて?
石田 ……今、書きたい設定がめっちゃあって、ありすぎる状態なんです。
佐藤 すばらしいじゃないですか。
石田 でも、書きたいものがものすごくあるのに、それから全然、芽が出ない状態なんです。
佐藤 それは、芽吹く一歩手前、開花前夜のように聞こえます。芽は出ないけれど根は育っていて、これさえ超えたら発芽する……みたいな。
石田 いや……それが、書きたいことがたくさんあるうえに優先順位をつけていくとする。とある設定があって、果たしてこれを漫才にするのがいいのかコントなのか戯曲に落とし込んだら良いのかと考えていくと、書籍はいちばん最後になっちゃうんです。
―― 手段がありすぎる。
石田 そうです。そのうえ舞台のほうが自分の「場」だし、こちらでみんなを幸せにしたいから、だとしたら将来的には小説で勝負したい気持ちはあったとしても、今、自分の頭の中に在るモノはそうではない手段で世に出した方が「得策」なので、この単語を使いました。
だって、そっちのほうがより多くの人を幸せにする、という願いが叶うから。
佐藤 さっきの例えじゃないですけど、いつか石田さんにとって、どこの誰にいつ届いて、どう幸せにできるのかわからないけれど、それでも瓶に手紙を詰めて海に投げ込みたいと思う日がくるかもしれない。そちらの方が「得策」と思える日がくるかもしれない。そう思いました。
石田 うんと未来にあるかもしれません……。
―― 佐藤さんは、なぜ、その質問を石田さんに?
佐藤 僕が小説家だからです。
石田 ああー……。
―― 僭越ながら、そこからひとつ伺いたいことが。同期のキングコング、西野亮廣さんが上梓された小説『グッド・コマーシャル』(幻冬舎)を石田さんの演出で舞台にされていますが、あの作品は果たして「小説」と呼んでもいいものでしょうか。失礼ながらご本人が喧伝するほどには……。
石田 あれはちがいます。そこについては舞台で上演するときにさんざん話しましたが、西野の性格上、大上段に構えているものの、実際、僕が書いたエッセイ集『万歳アンラッキー』(ワニブックス)を読んでものすごくほっとしたと。あれくらい肩の力を抜いてでいいんだと思ったと言っていて。
佐藤 ともすれば今、芸人さんが小説をお書きになるという一連の流れがプレッシャーになっているんですね。
石田 だから、俺らはしゃべって伝えたらいいねん、という話はしました。
―― 至極納得です。石田さんから質問はありますか。
石田 僕は今、設定がたくさんあるなかで、伝えたいことが山ほどあるんですね。それはメッセージというと大げさだけど、笑わせるだけでなくこのフレーズだけは絶対に言いたいということもあれば、全編を通してこういった気持ちを伝えたいということもある。そういったとき、作品に左右されたりしますか?
佐藤 テーマより前に作品がくるか? ということですか。
石田 はい。
佐藤 ないです。石田さんの言葉を借りると、「絶対に言いたいフレーズ」というものが僕にはいちばん大切で、そのフレーズを世に出したい。本にして世にばらまきたいんです。だから、何百枚書こうが、そのフレーズ以外の数千行とか、数十万の文字は実はどうでもいい。
石田 へー!
佐藤 そのフレーズを、ことさらに目立たせることはしませんけどね。気づいてくれる人にだけ届けばいいや、という想いはデビュー当時も、お金がほしいと宣言してる今も、一貫して変わりません。僕はワンフレーズを届けるためだけに小説を書いています。
石田 はー……そうかー……。僕、漫才だとそれがあるんです。「この一言のためにある」という漫才があるんです。でも、芝居だと怖じ気づいちゃうんです。
佐藤 え、むしろ芝居の方が込めやすそうです。
石田 その一言のために演者を集めて、脚本を書いて、時間と人を費やすことに怖じ気づくんです。だって漫才より長いし、一方的だけど届いてほしいから不安になっちゃうんですよね。だから小説という不特定多数の人に向けて、それができるのがすごい。
―― それは話が戻りますが、やはり佐藤さんが、目の前の人々に向けて、ではなく、瓶に詰めて投げることが平気だからではないでしょうか?
佐藤 いえ、それはもう、石田さんと僕のお客さんのちがいでしかないような気がします。作家は基本的にお客さんの顔が見えないですから。
石田 だいぶ、ずれてます(笑)。
太田 (思わず)でも、確かにあれは作家にはない!
佐藤 そうです。作家をやってるだけじゃ、未来永劫、あれは味わえない。芥川賞をとっても無理です。ノーベル文学賞くらいじゃないかな。
石田さんの舞台を観に伺ったときに感じましたが、うおおおおー、という万雷の拍手に囲まれて、もちろん、そこでスベったときの反動は計り知れないと思います。だとしても、ただただ僕にとってはうらやましく、心地良い空間が広がっていると認識するばかりでした。舞台の上で自分の創ったモノを放つ喜びはいかほどのものか? と考えたとき、僕は石田さんに、「小説家、イイですよ」と安易には言えない。むしろ、芸人カッコイイ! ロックバンドうらやましい! という思いが抑えられない。
太田 佐藤さん! そんなふうに思っていたなんて意外です!! 長い付き合いですが、今日は佐藤さんの話も発見が多くて興味深いです。
佐藤 ありがとうございます! 芸人さん相手なので、がんばってみました!!
太田 そこで、僕から石田さんに伺いたいことがあります。たとえばお客さんがまったくいない、もっと言えば誰もいないところで同じ事ができますか? あるいは壁の向こうにいるんだけど、見えない、わからない、反応がない。小説家と同じで「いる」ことはわかっているけれど、手応えはない、という状態では?
石田 あー……僕ら、今まで一回たりとも同じネタをやったことがないんです。変えているというか、変わってしまうので。風が吹いても変わりますし、電灯がチ、チ、ってなっても間が変わるし、タイミングが変わるから。
佐藤 バタフライ効果ですね。そういうのも才能なのでは。普通は、毎回同じになると思う。
石田 だから、お客さんがいないとなるとお客さんとの波長が合わないので最初は良いかもしれませんが、そのあとガタガタになるかと。
実はそれがテレビで、だからテレビはきらいなんです。絶対にその場にいる、お客さんとの波長っていうものがあるから。視聴者の人が笑っているタイミングがわからないままきっと僕は早く、あるいは遅くボケていると思うんです。でも劇場だとお客さんも意識せずに間を読んでくれるから、届けやすい。
佐藤 石田さんにとっては常に漫才が先にあり、漫才があるからこその芝居であり、一億円の使い方であり、またそのどれもが漫才に還るんだな、というのがよくわかりました。そして漫才といえば、石田さんとコンビで世界を構築する、小説家には絶対有り得ない、相方という存在がとても気になります。ある種の嫉妬もありますね。
石田 あー……。
佐藤 編集者はいますが、マネージャーでもないし、相方でもない。石田さんは誰も信用しないとおっしゃいますが、それでも常に隣に相方はいるわけで。
石田 ただ、そこに関していえば僕らは確かに漫才がいちばんで、最終的には「NON STYLE」ですが、相方が見ている夢と僕が見ている夢が決定的にちがうんです。だから、僕ら今ともに32歳でまだまだガキだけどこの先、何十年もかけてその焦点をあわせていかなければならないんです。
僕はけっこう現実的なところを見てしまうんですが、井上は志が高いというか、ちょっと遠めにピントが合っている。今まではそろってそこを目指してきたけれど、そろそろ僕だけは抑えるところは抑えにかかっているというか。無茶して走ってアキレス腱を切って、あかんくなったときに「ココ、用意してますよ。ココで飯食っていきましょう」っていう場を作るのが、今の僕の仕事だと思っているんです。たとえ、この先、井上が打たれすぎてパンチドランカーになったとしても、ここで雇いますよ、っていう場を作りたい。
佐藤 ロケットを打ち上げるのが井上さんで、万が一、ロケットが落ちても受け止める、というか着陸地点を作るのが石田さんで……すっごい関係ですね、相方って。
作家は独りなので、「夢を見ない」と自分で決めたら、見なくてもよくなるんです。逆に、「夢を見る」と決めたら見続けるしかなくなる。だから常に、やりたいことを自分で設定しなくちゃならないし、それを失敗するとブレちゃうんです。で、もし僕がブレちゃうと、編集者もこまる。「佐藤友哉はナニをしたいの? どんな小説を書かせたらいいの?」となっちゃう。独りで自在に決めることができるのは快感ですが、僕はすごく寂しがり屋なので、それを相方とできるってのはうらやましいです。ただ、僕は嫁さんが同業者なので、ひょっとしたら近いのかもしれません。
石田 そこで聞きたいのは、家族を持つって影響は大きいですか?
佐藤 むしろ、影響を受けようと思うことにしました。30歳になって家族を手に入れたときに、「変わるんだ」と意識的に思ったら、変わりました。それが自覚的ゆえに変わったのか、自然と変わったのかはまだわからないので、気持ち悪い感じです。
僕は「生まれ変わった」という感覚を信じていません。生まれ変わったことがないからです。「通過儀礼を経て、俺は今、新たな視点を獲得した!」という経験もないし。意識して変わってみよう、と思うことで変わりはしたけど……難しいですね。
―― 石田さんはなぜ、その質問を?
石田 僕は結婚願望が強くて、家族がほしいんです。ただ、それにより創作ペースが落ちてしまうのではないかと不安なんです。
佐藤 それはもう落ちますよ。落ちる落ちる落ちる!!
石田 落ちるのかー……。だと思ったけど。でも、それでも家族はほしいですね。(※2012年10月に一般女性とご結婚。おめでとうございます。)
―― 最後に今回の対談の感想をそれぞれ、お願いします。
太田 編集者の立場から申しあげると、今日はものすごく文学的な話でした。
佐藤 対談などで文学者と話すときは、自然と文学の言葉になるんですが、どういうわけか今回は、そういうとき以上に文学的な言葉を使った気がします。
石田 これまで対談、というもので良い感じでムキになったのは初めてでした。
普段、思っていることを隠して隠して生きているのが、あまりにもちゃんと聞いてくれるので一生懸命、話してしまいました。それ自体が自分的にはすごく珍しいことで、良い感じに脳みそが熱くなりました。普段、NON STYLEとしているときは、役割分担ということもあって、僕、ほとんどしゃべりませんもん(笑)。
佐藤 僕も楽しかったです。なにを以て「有名人」というのかわかりませんが、いわゆるテレビにでている有名人とお話ししたのは初めてでしたが、ものすごくおもしろかったです。
石田 この企画に対して、最初は不安な部分もありましたが、改めて「対談してほしい」の「対談」の意図するところが初めて理解できました。
―― 第一回に佐藤友哉さんをお迎えしたのは同じ年に生まれたというだけでなく、話すことと書くことではありつつも、近い匂いがあったからでした。それがとても伝わるお話が伺えたかと。ありがとうございました。

(2012年5月収録)