
NON STYLE 石田の明語
佐藤友哉 第三回
良く晴れた日の午後、星海社に訪れたのは、漫才コンビ NON STYLEの石田明。お馴染みの真っ白な衣装ではなく、私服での登場なのは今日が漫才の仕事とは少しちがった内容だから。2008年、M-1グランプリの王者に輝いた彼が今回から挑むのは、対談。同じ言葉を操る人々と「言葉」を使い、「言葉」を巡る旅の始まりです。
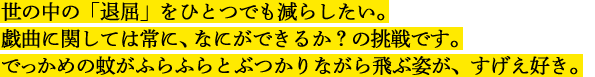
受け手をどう意識し、目がけて
どう己の作品を創造するのでしょうか。
―― 佐藤さんの、ミステリに限らず他の小説でも、そして石田さんの戯曲もですが、ともに謎解きを軸にした物語が多い印象があります。
佐藤 石田さんの舞台は、「Barアンラッキー」と、「ブラストが笑う夜」と、「ナイスなやつら」を拝見しましたが、確かに謎でひっぱるタイプが多いですね。しかも謎を提示して、「実はナントカでした!」と、オチを言って終わりでは決してなく、1本の話にいくつもの事実が並走している。そのために、実はテンポやストーリー展開に制限がかかっているんですが、伏線を回収するため一気に進めるんじゃなくて、みんなで迂回しながら旅をしているような感覚は、ジェットコースターみたいな話より、僕はとても好きです。
例えて良いのかわからないんですが、ラーメンズさんみたいな感じ。でも、ラーメンズさんの場合は、「そういうのをやりますよ」と宣言しているので、ある意味、先に構えることができるんですね。なのに石田さんは、一発芸や新喜劇的なことをやりながら、迂回の旅もやっちゃうので、びっくりしました。「Barアンラッキー」は、第1話だけしか観ていなくて、ずっともやもやしていたんです。
石田 あれは、もやもやしますよね(笑)。そういう仕掛けだったんです。さらに第1話は入り口の低さとして、いちばん新喜劇っぽく作ってあるので。
佐藤 気になって気になって、DVDを買ってしまいましたよ(笑)。
石田 ありがとうございます。そういった仕掛けというか構成はかなり意図してやってますね。果たしてこういうコトができるのか? という常に挑戦なんですよね。
佐藤 まさにそうなんですよ! 語弊がありますが、石田さんの話作りは、才能よりも努力を見るという感じなんです。新たな試みを見る快感、みたいなものがある。そういうのがね、さっきの話になりますが、「コントひとつに、こんなことまでしやがって!」という嫉妬を生むんじゃないかと。
石田 あー……、なるほど。
―― その話を受けますと、佐藤さんの小説も同じかと。ジャンル分けできない深さを内包しているというか、推理小説のフリをした、なにかちがう世界のものを見せられていることへの嫉妬というか。
佐藤 王道の推理小説のつもりで書いているんですけど、「それは推理小説じゃない」と言われ続けて、早10年(笑)。
―― 先の石田さんへの「(おもしろさが)わからないことが悔しい」、というのにも通ずるかと。そういう意味では、おふたりともスタイルを変えないというか頑固というか。
佐藤 変えないんじゃなくて、変えられないの! 変えちゃうと「笑い飯ショック」みたいに肩壊しちゃうの!!
石田 変えられないですよねえ(笑)。
―― その頑固さを愛し続ける、お客様の話をしたいと思います。創作物を届けるときに数を意識しますか? 深さを意識しますか?
佐藤 芸能の世界で活躍する石田さんとは、数の話は比べものにならないと思うんですが、そこは気になりますね。
石田 え、僕にしてみれば出版界のほうが華々しい感じがします。
佐藤 それがそうでもないんですよー(笑)。人によるけど。
石田 それはテレビも一緒ですって。
佐藤 (笑)。M-1って、「結成10年以内の漫才師が、賞金一千万円とその後ついてくる地位と名誉を目指し、努力と挫折の日々!」というストーリーがあるから、テレビを観ている分にはものすごく心躍るわけですが、もしも僕が漫才師だったら、きっと出なかったんだろうなと思います。僕は、そういう有名レースに参加することを唾棄して、舞台でしかできないような、たとえば白蛇の頭を釘で打ち付けて、かっさばいて血を飲むような(笑)、そんな芸だけやっていたい人間だったんです。
―― 過去形ですか(笑)。
佐藤 「賞金一千万円で、テレビでしょ。ふん」的な。過去形だけど!
石田 だいぶ尖ってますねえ(笑)。
佐藤 でもね、今は人を楽しませて、お金をいただくことを良しとする気持ちになっているんです。なのに、いざそうなってみたら、漫才師で言えば結成10年のリミットを超えて、M-1に出られなくなっていた! みたいな感じです。芥川賞もデビューから10年くらいが節目ですから。あれ一応、新人賞なので。
石田 ああ、そうなんですか。
佐藤 金銭と視線を集めようと思ったら、集める手段が絶たれていた。だから、そのときにね、これはもう人を幸福にするしかないなって思ったの。でも、それは全然前向きな話ではなく、手段がないからそこに辿り着いただけで、プラスの話じゃないんです。
―― でも、人を幸せにしようと思われたんですよね?
石田 それ、カッコいいな……。
佐藤 カッコよくないです。だってお金がほしいんですもん。石田さんのように「金は要らない」と交換条件を差し出すためには、ある程度、お金がないとダメなんですよ。
石田 ああ、それは確かにありますね。
佐藤 今のままじゃそれができないから、目の前の人を幸せにすることで、まずは、お金を儲けようと思ったんです。
―― かような1980年生まれの31歳がここにおりますが、石田さんはいかがでしょう。
佐藤 だいぶヒネた31歳ですよ(笑)。
石田 でも、わかります、わかります。僕は今、ある程度、お金に融通が利くように動いているので、そして「お金は要らない」と言いながら、その「お金が要らない仕事」に関連して他の仕事が発生し、お金を生むことがわかって動いているので。だから、佐藤さんの発想は実に人間的ですよね。よく、夜中に公園のトイレとかに、でっかめの蚊がふらふら飛んで、ぶつかっては方向を変えて……と、あれを見ていると「すげえ、人生そのものだなあ……」と思えて、大好きなんですよ。ものすごく不器用で、でも人間臭いというか。
佐藤 人間臭くて不器用なことは認めます。ただ僕の場合、「血も涙もない人間」の人間らしさなんですよ。ロボット的な。血も涙もあったら、もっと普通に立ち回れると思うんですよね。そこは欠落していると思っていて。
―― 一方で、石田さんはいかがですか? お金のことも含め、うまく立ち回ると言いつつも、かなりの怖がりで慎重であるとお見受けします。
石田 確かに僕はものすごい怖がりなんですが、ただし、ずるいのは皆さんが思っているほど、怖がりではないんですよ。
―― あー……なるほど。
石田 実は、怖がっているフリがうまいだけだという(笑)。
佐藤 だからアンチがわくんじゃないですか? 「あいつ、フリしてるだけじゃん!」と。
石田 なるほど、それはあるかもしれませんね。
佐藤 アンチの人って、ファン以上によく見ているから、愛憎でぐちゃぐちゃになりながら攻撃してくれるんですよ。
―― それでいうと、確かに石田さんはご自身でアピールするほどに人見知りではありません。
佐藤 うん、それは感じました。
石田 確かにそうなんですが、実は定期的に人見知りにはなるんです。
佐藤 それはどういうことですか?
石田 なぜなら、僕は貧乏の家に育ったので、生き方がセコイんです。小賢しいというか、実は誰も信じていないんです。ずっと隣にいる相方すら信じてないので、「コイツ、なんか変なヤツ」と思われているほうが得だと思ってしまうんです。
ただ、そこにひとつだけ生きる目標があって、それは世の中の退屈を減らすことなんです。ものすごく貧乏の家に育ったのでテレビもなくておもちゃもなかったから、うんと敷居の低い笑いを届けたいという気持ちがあって、道ばたで漫才をやっていたのも、その思いからで。だから電源のいらないカードゲームを開発したり、趣味でおもちゃショーにずっと通っているなかで、おもちゃ好きをアピールするために、よしもとでやっていた週替わりのウェブ番組でおもちゃのコーナーを作ったり、と、徐々に徐々に人とお金を集めていって……と、こずるいんです。
―― それをこずるいとは言わないかと。実際、ご自身が発案したカードゲーム「アンラッキー花札」が世に出て、楽しく遊んでいる人もいるのでは。
佐藤 たとえ本人がこずるいと思っていようとも、まわりが騙されたと思わなければ、ずるいということにはならないんじゃないかと。「わ、おもしろい!」と相手に思わせることができたら、それはもうずるくはないですよ。
―― そして、一生騙しおおせたら相手にはわからないかと……と言いつつ、今、ここで話されていますが(笑)。
石田 それはもう、そろそろ僕が話してもいいと思っているからです。なんだったら、相方の井上に、あのキモい、イキリをやらせているのは僕ですから。実際、ツッコミがあのキャラだと漫才の説得力が無くなるし、いやなんですが、あのほうがテレビでは浸透するわけで。もっと言うと、今は井上のキャラに隠れて見えていませんが、この先、僕がもっと悪く見えるようになる。実際、冷静になって聞くと僕のほうが言っていることはキツいですし、ひどいことをさせているので。
佐藤 というか、今こうして、「自分がこずるい」とか「自分がひどい」とかを公に言い出しているということは、ひょっとして……またナニか、腹に一物抱えてますね?
石田 (爆笑)さっすがですねー。
佐藤 こうしてやけにアピールするということは……。
石田 気付くのが早い、早い、早い! 作家、洞察力がありすぎるっ。ここ、全カットで(笑)。
―― すてきです。そういった空気を読む、ではないですが、そんなふうに「自分たちを演出していく」ことをどうハンドリングするのでしょうか。たとえば作家なら読者からの声とか編集者と相談するといったことができますが、NON STYLEとしてはナニを物差しに変えていくのでしょうか。
石田 はっきり、コレというのはないんですが強いていうなら、僕や井上の家族や親族ですかね。その辺りの反応を見ているとだいたいわかります。ああ、今、良くない状態なんだな、とか、もうシフトチェンジしないとならないな、とか。
―― それはなぜでしょう。
石田 家族ってやっぱり、良くも悪くもミーハーだから、いちばん敏感に反応するんですよね。
―― 確かに漫画家でも、まず母親に見せて、反応を見るというか、母親が笑ってくれる、あるいはわかってくれるか? をひとつの物差しにしている方がいたりします。佐藤さんの場合は編集者でしょうか。
佐藤 作家にとって最初の読者は編集者だとよく言いますが、それで言うと、これまでの僕は編集者を信じすぎていた!
石田 でた、でた(笑)。
佐藤 いや、本当に。僕は編集者を信用しすぎるきらいがあるんです。向こうが真剣で親身であればあるほど、僕も向き合ってしまうんです。
石田 ああ、なるほど。
佐藤 そうなると、2人の世界に入っちゃうんですよね。本来は読者を見なくちゃいけないのに。だからこそ、もっと編集者を信じずに人々の幸せを考えたほうがいいのではないかと思ったんです。
僕と編集者のおもしろい話、ではなく、世界がおもしろくなる話。あるいは、おもしろくなくてもいいから、幸福になる話。経済が幸福を求めている以上、それでお金も入ってくる! と。
―― デビュー11年目にして、辿り着いた実に美しい境地かと。
佐藤 結婚して大人になりました(笑)。僕はこんな感じですが、石田さんはご家族以外の指針は?
石田 ……編集者というか、作家はつけませんね。ことに先輩で芸人出身の作家さんはその人の趣味がにじみ出てくるので。
佐藤 自分の作品世界に他者の色が入ってくるのはお嫌いですか?
石田 受け入れることはできるんです。ただ、本人が持つ権力からもの申す人はいやですね。
佐藤 上から目線の?
石田 いえ、上から目線は別にいいんです。だとしても世界を広げてくれる助言ならありがたく聞くんですが、そうではなくて「おまえちょっと、こっちこいや」という助言は苦手です。歩み寄らずに俺のほうを動かすんか、と思うと、それはちょっとちがうかな、と。
佐藤 あー、それは原理的にやっちゃいけないですよね。
石田 よくなるための言葉は聞きますが、失礼ながら相手の世界を広げることができないからこそ、芸人を辞めている方が多いので。ただ、さいたまスーパーアリーナのときは、僕と井上の空気が悪くなったときに間に入ってもらうための緩衝材的な存在として、作家をひとり立てましたが。
―― ……ほんとうに周りを信じていないんですね。
佐藤 素朴に聞くな!(笑)
石田 だって、もし、その色を入れたことが裏目に出たら、僕らが損するし、叩かれるだけなんで。それは注意深くもなりますよ。
佐藤 だから星海社は編集者が前に出る会社なんです。編集者が舵を取るが、責任も取る。
太田 ああ、弊社は叩かれてますねえ(笑)。
佐藤 それが正解かどうかはわかりませんけれど。
石田 その覚悟があって、口を出すならいいんじゃないでしょうか。

自身が世に送り出すものに、どう責任を取るか? を聞いたところで、次回は作家・佐藤友哉編最終回。
対談を経て、互いへ質問をぶつけます。
(2012年5月収録)