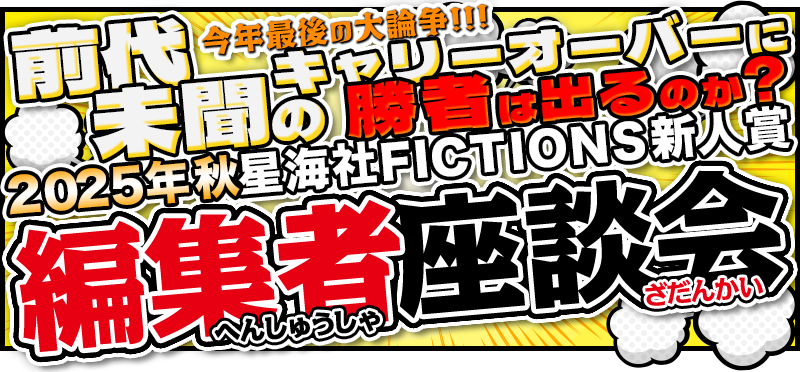
2025年秋 星海社FICTIONS新人賞 編集者座談会
2025年9月22日(月)@星海社会議室
今年最後の大論争!!! 前代未聞のキャリーオーバーに勝者は出るのか?
有力作品はなんと6作品!
太田 前田さん、心なしか顔色がいいんじゃない?
前田 今回すごくないですか? 受賞の有力作品が6作も挙がるなんて!
丸茂 うれしい悲鳴ですが、こんなに読むことになるとは思わなかった(笑)。僕はかなり悩んで自分が挙げる候補作を絞ったんですけどね。僕が読んだ作品だけでもまた投稿してほしいと思える方がけっこういました。
太田 そもそも「受賞までリーチ状態!」みたいな人がけっこういるしね。
片倉 そして今回から参加の榎本さん、自己紹介をお願いできますか。
榎本 初めまして。元自衛官の榎本です。銃を撃ったり撃たれたりする訓練をしてきました。ミリタリー描写にはうるさいかもしれません。よろしくお願いします!
丸茂 体力ありそう(すごくほめている)。
前田 それでは、今年最後の新人賞座談会を始めましょう!
太田 おう! 今回こそ受賞者を出すぞ出すぞ出すぞ……!!
ループものの新機軸?
岩間 『リフレインゲーム』は、銀行強盗事件の人質となった女性と犯人の青年が心を通わせていくお話でした。会社の平凡な毎日に不満を抱える主人公が、ある日、銀行で強盗に巻き込まれちゃいます。彼女は人質として犯人の青年と逃走する過程でタイムループに陥ってることに気づくんですね。そしてタイムループを繰り返し、青年との接触時間が長くなる中で青年と恋をするんですよ。
丸茂 そういうの、エコノミークラス症候群じゃなくてなんて言うんでしたっけ。
岩間 ストックホルム症候群! 青年はループしても必ず死んでしまいます。主人公は青年を救おうとループする度に行動を変えるんですけれど、彼の死を避けることができない。最終的に彼を救う唯一の方法として、彼女は自分の命を断つことを選び、ループは終わります。
丸茂 悲しい……。
岩間 タイムループ×ラブストーリーとして新鮮な設定だったと思います。
丸茂 タイムループ×ラブストーリー自体は鉄板ですけど、犯罪者×被害者という組み合わせは意外でいいんじゃないですか。ループの発生原因はあるんですか?
岩間 とくに具体的なものはないですね。
丸茂 「そういうもの」ってことですね。でもループものってよくできていますよね。「どうしてそんなことが起きているのか?」、「どうすれば未来を変えられるのか?」っていう、読者が物語を読む動機をお手軽にセットできる。
岩間 ただこの作品はあまりにも最初の分岐に変化がなくて、読者にここで切られちゃうよという印象でした。早い段階で変化をつけてほしかったです。
前田 星海社FICTIONSでいえば南海遊さん『永劫館超連続殺人事件 魔女はXと死ぬことにした』がループを取り入れた近年の成功作だと思いますし、星海社新書からは下倉バイオさん『「選択肢」の選択史 ニトロプラスのシナリオライターはノベルゲームをどう作ってきたか』を刊行させていただいたばかり。星海社はループものを面白がれる編集者が勢揃いしていると思いますので、ぜひまたエッジの利いた作品をお待ちしています!
ストレートな感動がほしい!
丸茂 続いて僕の担当作ですね。今回は「めちゃめちゃ悩んだけど……挙げない!(涙)」というくらいにはよかった作品が4作品もありました。まずは『炒飯密室の問題』。なんか本格ミステリにしてはトンチキなタイトルだと思うじゃないですか? 『六枚のとんかつ』みたいな抜け感があると言いますか。
岡村 たしかに、お腹が空いてきた。炒飯食べたい。
太田 あえて「かっこよくない」感じを狙ってるのがいいね。
丸茂 このタイトルで中身は青春ミステリです。しかも扱うのは日常の謎でなくて、死人が出ます。「炒飯密室」とはなにか……第1の事件では、マンションの一室から餓死した死体が見つかります。しかし、その部屋には炒飯があったんですよ。「餓死する前に炒飯食えよ!」ってなるじゃないですか。
榎本 毒炒飯ですか?
丸茂 違います! なぜこんな状況が生まれたのか、そして届く「幽霊炒飯」を名乗る人物からの犯行声明、連続する密室での事件にはやはり炒飯が残され……加速する謎にオカルト研究会所属の高校生たちが遭遇します。わくわくしませんか?
太田 いいねえー。宇山さんが喜びそう。
岡村 たしかに不思議な話なんだけど、なんで炒飯にしたんだろうね。いやまあ、作中では必然性があるんだろうけど、事件現場に残されたのが謎のメッセージや凶器とかのほうがかっこよくない?
丸茂 感覚的な話になってしまいますが、言わんとすることはすごくよくわかります。この「炒飯」という、ナンセンス感というか、浮いてる感を出すのがこの方のセンスで、大事にしていただきたいと思う一方、素直な本格ミステリらしいフックの作り方に寄せてほしいとも思う……正直なところ後者のほうが推しやすい。前者のほうが、想像できないイリュージョンを生む可能性があるけれど。炒飯の出現方法を熱心に議論する話を、おもしろいと思う人もいると思う。でもノれない人もいると思う……難しい!
太田 ある種のおふざけだよね、『煙か土か食い物』で◯◯◯が大真面目に伏線にされてるような。
丸茂 そうなんですよね……僕は何回かこの方の投稿作を読んでて、かなりこの人の作品を好意的に読めてしまうほうだと思います。編集部の他のみなさん――雑に言うと己がゼロ年代の亡霊だという自覚がない方だと、この作品のノリを最後まで読むのはきついんじゃないかな。
片倉 さすが2025年に『セカイ系入門』を編集したゼロ年代の亡霊……。
丸茂 亡霊でない方にも読めるものであったほうがもちろんいい。というか、そうでなくてはいけない。この作品は、独自の感性を読者の好みを超えて叩きつけられるほど「見事!」と叫べる点がどこかにあるかと言うと……ということで、今回は挙げませんでした。
太田 『煙か土か食い物』は文体とキャラクターも強烈だし、本格ミステリに対してメタ的なナンセンスさがあるんだけど、本質はすごくストレートな家族愛の話じゃん。あるいは『クビキリサイクル』もトリック自体はすごくシンプルで即物的だけど、いーちゃんという人間の思考や鬱屈に共感する人が多数だった。そういうポイントがほしいってことだよね。
丸茂 まさに! 今回は惜しかったんですよ……それこそトリック自体は炒飯っていう変なオブジェクトはあるけど特殊設定なし、メタなし、ベタな本格として読める範囲で組み立てていたのは本当によかった。べつに超絶技巧のトリックやロジックはなくていい、一定以上の意外性はありました。あとはキャラとドラマなのかな……と思います。
キャラクターはいいのに……
丸茂 続いて、こちらも候補作にするか悩んだ『ヴァヴィヴれ!』。ジャンルは……日常の謎ミステリっぽいなにか!
片倉 つまり、「日常の謎」と呼ぶには残念ながらミステリポイントが足りないと?
丸茂 僕そんな厳しいミステリ警察じゃないよ!
岡村 (嘘だ)
丸茂 キャッチコピーは「オルタナティブ・インダストリアル・(ノット)ディレクティブ」で、よくわからない! 舞台は高校で、ヒロインのキャラが超絶好みでしたね。「いま自分たちがいるこの世界は一度目の世界=オリジンを再演するために用意されたもの」と主張する、もう古くさい表現ですがいわゆる「電波系」ヒロインが登場します。主人公は彼女と学園生活を過ごすなかで遭遇する日常の謎をちょっとだけ解決します。
岡村 ちょっとだけなんだ。
丸茂 犯人はいちおう説明されるけど、動機を説明してくれません。だから候補には挙げられませんでした……がっかり。でもキャラクターはすごくよかった!! ちょっとゼロ年代の亡霊の感性過ぎるかもしれないけど、僕は「この世界は偽物である」って感覚に弱いんですよ。だから、このヒロインの言動には古傷を疼かされる感がありましたね。
太田 この投稿者、丸茂さんより若いのにね。
丸茂 主人公=語り手はこのヒロインにつきまとわれている女の子なので、ヒロインの浮世離れした言動に対するツッコミがちゃんと入るから冷静に読んでられますし、ふたりのかけ合いは読んでてすごく楽しい。これでちゃんと日常の謎ミステリとして成立してたら……僕はもう文句なしでした。
片倉 キャラ造形は抜群というわけですか。評価を聞く限り、この作者さんはミステリ的な謎と解決を作るのがそこまでお得意ではないんですかね。
丸茂 あまり謎解き考えようって方ではないんだろうな……でも、いま星海社として注力してるからミステリがんばって書いてほしい……! まずイメージしたのは、『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』ですね。自分のことを人魚だと言い張るヒロインがいて、彼女と過ごす日常が描かれ、陰惨なその背景が明らかになっていく。こういう路線。まあでも厳しいのかな……。ストーリーになにを持ってくるか、ミステリ以外もあると思いますよ。『わたしたちの田村くん』とか『電波女と青春男』とか、この方の日常系のテンションを活かすならその路線かな……でもいま売るならどうパッケージすればいいんでしょうね。そもそも電波系ってもう言わないし、揶揄のニュアンスが強すぎていまはセールスのためには使えないよな。絶対ミステリにしなければならないってことは当然ないので、じっくり考えてみてほしいです。
中国ものが増えてきた?
丸茂 次も候補に挙げるか少し悩んだ『月鶴楼殺人事件』。中華風ミステリですね。
太田 『薬屋のひとりごと』みたいな感じ?
丸茂 後宮ものではないです。豪商の屋敷を舞台にした連作短編で、現代日本人の尺度的にはだらしない性愛と人間関係を背景とする事件があり、『金瓶梅』みたいなイメージかな。「各話の事件が小規模すぎる!」というのもあるんですけど、気になったのは趣向です。山田風太郎の『◯◯◯◯◯』が思い浮かぶところで、それと比べて挙げることはできませんでした。読みやすさを損なわない程度に異国感のある文章はよかったです。また送ってほしいですね。
岡村 『葬令』は大清帝国を舞台にした伝奇ものです。清の最盛期の少し後くらいの話で、まだ国力はあるけど、少し衰えが見え始めてきている。20歳くらいの親王と包衣人の男性のタッグが事件を解決します。
榎本 包衣人?
岡村 皇族の召使いのような身分ですね。ちゃんと中国史で実際にあった事件が絡んでくるのがおもしろい。候補に挙げなかったのは、作品の味がよくわからなかったから。「この作品を誰に食べてほしいの?」という印象だったんです。ただ、才能はある方だと思いました。
片倉 そういえば清時代が舞台の作品ってあまり見ませんね。
岡村 パッと思いつくのは『蒼穹の昴』とか? 時代的に男性は辮髪なんだよね。
前田 辮髪にだって、ニーズはある気がします。みんな詳しいですもの。歴史にもエンタメにも目が肥えている熱い読者の方がたくさんいるのが現代日本。伝奇というジャンルは、しっかり史実を調べた上で、物珍しさもありつつ、ポピュラリティも兼ね備えないといけないから、いまは本当にたいへんです。
太田 中国舞台の投稿作品が多くなったね。『崑崙奴』の影響もあるのかな。
ギリシア哲学は小説にできるのか?
片倉 『【物語】ギリシア哲学者列伝』はタイトル通り、実在した古代ギリシアの哲学者が冒険を繰り広げる群像劇です。ソクラテスやアリストテレスなど錚々たる面々が登場しまして、主人公はディオゲネスです。
丸茂 おお、いいですね!
榎本 なるほど(誰だ?)。
片倉 ディオゲネスはずっと樽の中で生活していたエピソードで有名な変わり者の哲学者です。この作品は史実ベースにフィクションが5%くらい混じっていて、たとえばディオゲネスが半神半人という設定なんですが、序盤でディオゲネスは神の世界から追放され、史上最初の哲学者と言われるタレスに拾われます。
この世界には持ち主の思想を現実化させるアイテム「黄金鼎」があり、あるときそれがタレスのもとに転がり込みます。ところがタレスは「万物の根源は水である」という思想の持ち主なので、彼は水になってしまい、それどころかこのままでは世界がすべて水と化してしまう……というピンチが訪れます。タレスは「黄金鼎にふさわしい哲学者を見つけ、世界を安定させてほしい」という願いをディオゲネスに託し、彼は黄金鼎を持って色々な哲学者のもとを巡る、というのがあらすじです。こう言うと真面目一辺倒の話に聞こえますが、ピタゴラス教団がハデス配下の秘密組織として暗躍したりと、外連味があってかなり楽しめましたよ。
榎本 アーティファクトや陰謀チックなところは『アサシン クリード』みたいですね。
片倉 「万物の根源は火である」と語るヘラクレイトスに黄金鼎を渡したら途端に熱さに悶え、ギリシア世界そのものが干上がるシーンなんかもあり、思想を現実化させるガジェットのおかげでシリアスなのにどこか良い意味で笑いがあるんですよね。
自分はこの作品、古代ギリシャ版の『チ。』だと思いました。いろいろな哲学者が「世界はこうなっているのではないか」と世界の根源を模索する「知」の話なんです。ただ、『チ。』の「知を求める」という信念に比べて、この作品が古代ギリシア哲学を通じて提示する「世界の根源を探る」という問題意識に現代人があまり共感できないのが大きな課題です。この点さえ解決できていれば迷うことなく推薦作に上げるくらいの上作でした。
丸茂 地動説への絶対に揺るがない確信とそれを弾圧する社会との葛藤があってドラマチックになったのだから、哲学者だけで『チ。』は難しそうですね。
片倉 作者さんが古代ギリシアをしっかり調べ、うまく小説に落としこんでいることはよくわかるので、あとは「世界の根源」という古代ギリシアならではの問題意識をぜひ現代人に共感できるような物語にしてほしい! この点をクリアする改稿ができるならどうか改稿してまた送ってもらいたい、それくらいのポテンシャルを感じました。
丸茂 古代ギリシアは小説の題材としてあまり意識されてない領域なので、可能性は無限大だと思います。
文豪なのか否か
榎本 ここから先に議論するのは受賞候補作です!
持丸 僕が挙げたいのは『鬼門の化物手帖』です。舞台は文明開化期の日本……でいいのかな。主人公はオカルト雑誌の女性記者です。彼女が見世物小屋へ取材に出かけ、「影のない男」という見世物をやっている人物・太宰の協力を得て、東京に出現するいろんな怪異を解決していく伝奇ミステリでした。千里眼やこっくりさんなど、明治の心霊ブームを時代背景にした点も活きていました。
丸茂 キャラクターというか、文章がこなれててよかったですね。
持丸 女性記者が真面目すぎるのが、コミカルで可愛いらしいんですよ。葛藤とか苦しみとかがちょっと足りない気もするけど。この方は小説の基本である「語り」が上手だと思います。冒頭からキャラが動き始めるのは何物にも代え難い美質ですね。
岩間 メインキャラのふたりがいい関係性で、会話のテンポがよかったです。
片倉 自分は最初のページで芥川龍之介の名前をもじった「なんちゃって芥川」なキャラが出てきた時点で、史実への向き合い方が中途半端なのが見えてやや興ざめしてしまいました。太宰も「太宰治要素はあるのかな?」と期待しながら読みましたが特にそんなことはなく、実在の人物のイメージを都合よく摘んでいる印象が最後まで拭いきれずじまいでした。
丸茂 明治なのか大正なのか初期昭和なのか、ものすごいふわっとした時代設定ですよね。太宰も文豪ではなくて、名前だけ借りてきてキャラ付けに利用しているように見える。オリジナルの氏名にしても物語上はまったく問題がないのだけど、でも一般的な氏名にしてしまったらキャラ立ちは弱くなりますよね……。
岡村 この名前にするからには、最後にとんでもないオチとかいうのがあるのかなって思ってました。
太田 自分のことを太宰治だと思っているけど、実は三島由紀夫だった、とかね。
榎本 設定や展開をもっと過激にしていいんじゃないかと思いました。私の大正ロマンのイメージは、『パワプロクンポケット』の大正冒険奇譚編なんです。幽霊とか文豪に加え科学の自動人形とかも出てくるんですよね。そういうハチャメチャさを求めてました。
丸茂 時代設定を、明治なのか大正なのか昭和なのかしっかりする。文豪をモチーフにするんだったら、彼らそのものを書かなくてもエッセンスは組み込む。『文豪ストレイドッグス』で作品名を必殺技にしてるような感じね。あと、主人公の役割をもっと明確にしたほうがいいかなと。太宰側の役割を奪っちゃってる感じがして、太宰はやや影が薄いなと思った。
片倉 設定の作り方は今後の課題ですが、リーダビリティが高くスラスラ読める文章を書ける方なので頑張ってほしいですね。
前田 まずは「誰もが知っている話題」を取り上げて、どう料理するかだと思います。「太宰」と出してしまったのなら『人間失格』を期待しますよね。細かい整合性やリアリティラインが気になってしまう作品でしたが、そこを王道に取り組む勇気でねじ伏せる、みたいな作品が読みたい!
人狼ゲームのその先に
榎本 私が候補に挙げたのは、『memememememe』という作品です。語り手が目を覚ますと、部屋に男女 7 人が監禁されています。そして、スピーカーからこの7人の中に1人だけ潜んでいる地球外生命体を探すように指示される。1部は地球外生命体を探す7人の話、2部はこの実験の主催者視点の話、そして地球外生命体についての真相がラストで判明する、という内容です。
丸茂 榎本さんの推薦ポイントはどこですか?
榎本 地球外生命体をあぶり出すために、監禁された彼らは人間しか知らない人間の家族愛を語り合います。しかし、彼らが語った家族愛は家族の証言により認知が歪んだ家族愛だったことが判明する。その裏表ある人間模様がおもしろかったです。
片倉 あらすじはすごく面白そうで期待して読みました。しかし実際に読んでみると正直ちょっと苦しかったです。描写で惹きつけられる、読んではっとするシーンというものがほとんどなくて、後半は「ストーリーの確認作業」のようなテンションで読んでいました。
丸茂 『遊星からの物体X』とか代表的ですが、いわゆる人狼ゲーム系のソリッドシチュエーションってよくできてるなと思いました。ループものと同じようなこと言ってるな。人狼――この作品だと地球外生命体は誰なのか?っていうところで、読む動機をお手軽にセットできてしまうんですよね。それに頼り過ぎてるところはあったと思います。
持丸 最後まで読んでようやく仕掛けがわかる作品なんですが、ラストでどんでん返しが待ってます。しかし、そこに辿りつくまでがつらかったです(とくに家族愛を披露しあう部分)。全体に短編向きのアイデアだと思います。長編にまとめるなら萩尾望都『11人いる!』のように、各人が個性的かつ次々と事件が起こる展開がほしいです。
丸茂 僕はオチはガッカリ派ですね……ホラーだと珍しくない手口だと思います。人間の認知の歪みにフォーカスするのはいいんですけど、それとオチにちゃんとテーマ的な繋がりをつけないと。
岡村 小劇場で上演される演劇と相性がよさそうなネタだなと思いました。でも、もう一歩突き抜けるための独自性や驚きみたいなものがほしかったなっていうのが正直な感想です。
太田 「人間には認知の歪みがある」、だからそれはなんなのか……ってところまで書いてほしかったね。
素材は悪くないけれど……
丸茂 僕が挙げた『信仰は白雪に閉ざされて』は何度か話題にしている方の投稿作で、田舎――僕の地元が舞台なんですよ。
太田 そう、諏訪の話なのよ! だから丸茂さんに振った。
丸茂 厳密には諏訪そのものではなく、諏訪信仰をモチーフにした古くからの風習がある架空の村で、密室殺人が発生するのがあらすじです。主人公たちに超常的な設定はあるものの、事件の解決自体は現実に即した本格ミステリですね。前回の投稿作品より文章とキャラクターのノリに落ち着きがあって、追いかけやすいストーリーラインになっている。ただトリックについてはちょっと大味過ぎるかな……という感触でしたが、みなさんいかがでしょうか。
片倉 雰囲気はいいけど、謎解きが超人的推理すぎませんかね? あの御神体の正体が◯◯だと状況証拠だけで当てるのは驚きを通り越して納得がいきませんでした。でも雰囲気はよかったですね。
岡村 主人公たちの、探偵役――ワトソン役タッグの基本的な設定はうまくできていると思いました。民俗学ミステリらしい雰囲気もそこそこ楽しめる。
丸茂 僕は地元出身者のなかでも上位1%レベルに諏訪信仰に詳しいので、気になるところはあるんですけどね。
岡村 でも文章が安定してないよね。ハッとするようないい一文がたまにあるんだけど、すごく気が抜けたような説明文や、「このセリフはどっちのキャラが言ってるの?」と読んでいて迷ってしまう部分があった。
丸茂 それは否めないです……おそらく執筆期間が短いからですね。
持丸 最初の列車のコンパートメントに乗ってやって来る導入は、雰囲気たっぷりでほれぼれしましたねえ。でもそこで力尽きちゃった。殺人が起こるまでが長く、そのわりにトリックがあっけない。怖さがない点も気になりました。ヒロインの設定はもっと発展する可能性があったのに、尻すぼみになっていったのは残念!
岩間 たしかに序盤の終戦直後みたいな時代背景の描写は、すごい興味をそそられました。
榎本 静かでなんか嫌な雰囲気が漂っているのがよかったですね。
丸茂 僕の地元なんだけどね……。
榎本 読んでいて横溝正史『金田一』シリーズのような雰囲気を感じました。
丸茂 僕の地元には『犬神家の一族』のモデルになった片倉館がありますからね。うーん、ただ金田一耕助でなく孫寄りになってた感があるかな。横溝正史の描く田舎はやはり実在のモチーフがあって、たとえば『八つ墓村』はちゃんと村の成立に歴史を感じさせるんですよ。一方でこちらはリアルなローカル性に立脚しているというより、特殊設定の村、という感じ。でも、これは悪いことではない。投稿者の方は専門家ではないので雰囲気があるくらいでいいのだけど、民俗学的アプローチが薄い分、ミステリとしてのトリックや犯人特定のロジックにはもっと複雑さがほしかった。
太田 僕は冒頭の2ページぐらい読んだら、これは受賞でいいんじゃないかと思った。それくらい雰囲気がある。けれど、その後は申し訳ないけどテンションが下がる一方だったね。まずトリックについては、「最初の事件が起こったときにこの一族の人はみんな気づくのでは?」って思ってしまう。気づけないことに説得力があればいいんですけどね。あと、ヒロインを魅力的に描けていないと思う。冒頭は謎めいていてグッときたのに、途中からふつうの人物になってしまった。その結果、中盤から主人公ばかりが頑張るしかないから、「ホームズもワトソンも全部自分でやってる」という状態に陥ってる。
丸茂 そうですよね、役割分担しないと。
太田 パーツは悪くないんだけど、詰めが甘いよね。息切れからか、中盤から如実に文章のレベルが落ちてるのはダメ。キャラの設定はいいのに、役割分担を含めた描写が厳しい。トリックもロジックもこの前提で推理できるかは微妙で、しかしそれもあっけない真相。
丸茂 御神渡りをトリックに利用しようっていう発想はすばらしいと思ったんですけどね。
太田 わかる! できるならば舞台はもういっそ現実の諏訪にして、そこでひとつくらい大きな嘘をつくというやり方がよかったのかもしれない。
丸茂 それは、相当諏訪に詳しくないと難しいかな……。高田崇史さんのような造詣があって可能になる芸当じゃないですか。
太田 京極夏彦さんもすごいよね。京極さんが冒頭から繰り出してくる文献や史料は、解決編でもうまさにジグソーパズルのようにパチッとはまる感じがするじゃない。
丸茂 でも急に専門家にはなれないし、前回の投稿作の舞台だった「陰陽師の村」よりは歴史性――雰囲気があったと思います。でも現実にある諏訪から、もっと距離を取らないとボロが出てしまう。
太田 そう。この作品でまず「うっ」と思ってしまったのは、冒頭の古文だよね。これは出来が悪すぎる。冒頭からこういった細部が綻びてるから、最後まで雰囲気をちゃんと演出しきれてない。現代ものを書いてもらうのはなしなの?
丸茂 前回の「陰陽師の村」は現代ものでしたが、ダメでしたね。うーん、学園ミステリ書けば落ち着くって話でもないだろうしなぁ……この投稿者の方は発想の大きさがいいところで、それを実現するならある程度以上は現実離れした「本格ミステリのための舞台」を考えるほうがいいと思ってるんです。だから麻耶雄嵩さんの『鴉』とかがいい見本だと思ってるのだけど……まあ、また相談してきます。
万能調味料、それは……
片倉 『TSスターリン×転生ヒトラー』は、現代日本に転生し、女子高生として学内の支配に邁進していたスターリンが、同じくたまたま現代日本に転生したヒトラーと出会って喧嘩しながらも友情を深め、最後はトロツキーの生まれ変わりと判明した担任の先生とモスクワで銃撃戦を繰り広げる話です。
スターリンってこんな人物造形だったっけ? といったツッコミどころも多々ありつつ、B級映画のような勢いがあって笑いながら読めました。B級ナチス映画の名作『アフリカン・カンフー・ナチス』を小説にしたような趣を感じて個人的には大好きでした。誰もが知っている超有名人が主要キャラなのも、とっつきやすくて好感が持てます。他方でニコニコ動画的なミームを多用するので、好き嫌いがはっきり分かれるのも容易に想像できる作品です。
岩間 表面的にはラブコメとして進行していくんですけれども、前世の記憶が顔を出す場面があったりユーモアと違和感が同居してて印象的だなと思います。
持丸 『パリピ孔明』みたいなお話ですよね。正直、パロディとしても転生ものとしても楽しめませんでした。ロシア革命や共産主義の知識がふんだんに出てくるんですけど、そこで止まっている印象です。ラブコメという物語の枠に絡める工夫はあまり感じられませんでした。
岡村 ちょっとどっちつかずだなと思いました。二人ともスターリンとヒトラーの知識はあるんだけど、転生してる感があまり出せていない。
太田 うん、そうなんですよね。「スターリンのことよく知ってる女の子」の話になっちゃってる。
岡村 2人がゲームで独ソ戦をやるところは面白い。
太田 お前ら現実でやってるやんけ笑! っていうね。
岡村 「この小さな教室で第2の独ソ戦を演じているわけだ」という文があったんですけど、こういう演出をどんどんやった方が面白かったんじゃないかなとは思いました。2人の卓越した人心掌握の能力を駆使してクラス内で権力闘争を繰り広げるとか。それだけで1冊書くのって難しいかもしれないですが、本作はある大きな風呂敷を広げたものの、そこがあんまり魅力的じゃなかったですね。
前田 ここで偉大なる先例がある、ということをみなさんにお伝えしたい。おかゆまさき先生の『マルクスちゃん入門』。マルクスが、いわば「TS」して現代に蘇るんですけれど、「共産恋愛主義」というパワーワードが出てくる。そういうラブコメとして成立させる工夫が随所に見られる作品なのですね。先例を真似してくれという意味ではないですが、エンタメとしての工夫はもっともっとできると思うんですよ。本作は、小ネタを紹介したいだけ、というふうに見えるシーンが散見されて、推しにくかった。
丸茂 (マルクスちゃん検索)これすごいですね。さすがおかゆまさきさん。現代恋愛もののフォーマットに移行するんだったらこうしないとっていうお手本のような感じだね。
前田 そうなんです。けど、マルクス主義の勉強には全くならない、と思います!
太田 でも、僕は、受賞も本気で考えた! だけど、ここまでのみなさんの反応を見て、反省もした。
岡村 何でですか?
太田 ヒトラーはどこに転生したって物語になるじゃん。「ヒトラーが戦国時代に突入する」とか「新選組の長になる」とか。何やっても、ぜんぶ面白そうじゃない。我々、日本人はヒトラーをそんな風に便利にフィクションのネタに使ってきたわけなんだけど、あまりにも安易に使いすぎてきたんじゃないかな? つまり「味噌味」なんだよ。ナチス・ドイツは「味噌味」のラーメン。
丸茂 『らーめん再遊記』の芹沢さんが言ってましたね。味噌ラーメンは味噌という調味料がうますぎるために、どうやってもそこそこの完成度になってしまう。ゆえに物足りないと。
太田 そう。ヒトラーはどうやっても面白くなっちゃうんだよ。我々はここら辺に関してやっぱり今一度考えてみるべきことあるのかもしれない。もちろん、飛び抜けてうまい「味噌味」はあるよ。平野耕太先生の『ヘルシング』みたいにね。そして僕は「味噌味」のものが嫌いじゃない。でも「味噌味」だからというだけで推せるというものでもないし、推していいわけでもない……ことに、今回の座談会で気づかされました。ありがとうございました。
そのジャンルが好きな人に響くかどうか
前田 僕は『不滅の森のアヤ』という作品を挙げました。コンセプトは「ソ連・百合・SF」ですね。
丸茂 うーん、聞き覚えがあるな。
前田 ソ連といってもこの舞台は極東シベリアです。僕、シベリアが好きなんです。
太田 なんで!?
前田 長年、『地球の歩き方 ウラジオストク/ハバロフスク』とか『地球の歩き方 サハリン』とか、旅行ガイドを読み耽っているんです。サハリン版なんかには「日本に1番近いヨーロッパ」と書いてあってロマンがある。今回の作品が取り上げる地域もそうですが、ヨーロッパと中国、アジアなどの様々な異国情緒がないまぜになっているのが魅力です。みなさんも一度グーグルストリートビューで旅行してみてください!
榎本 なるほど(?)。
前田 さて、ストーリーを紹介していきます。1960年代ころの極東ソ連を舞台にしています。主人公は男装した女性のお医者さんで、不思議な女性と恋愛関係にあって同居している。この女性となぜこのような同居関係に至ったかという謎が徐々に明かされていく過程で、主人公は何人かの人々と出会う。その中でソ連を支えたSF的宇宙科学主義と、したたかに生きていくしかない闇社会の人々の価値観、そしてアジアの仏教的な世界観の衝突が描かれていきます。
丸茂 南木義隆さんの作品を思い出してしまう内容ではあったな……。
片倉 自分はこの作品、ブレジネフ時代が舞台の『同志少女よ、敵を撃て』だと思って読みました。それくらいソ連の風土や精神性が瑞々しく描かれていて好感が持てますし、主人公が男装の麗人の闇医者だったりとキャラの魅力もしっかりあります。ただし基礎値が高いだけにストーリーが地味で起伏に乏しいのが目につきました。普通の日本人には馴染みの薄いシチュエーションだからこそ、話の筋はなるべく共感しやすくわかりやすくして、派手さを意識してもらいたかったです。
持丸 作者は「ロシア文学」をやりたかったんでしょうね。なんとなくロマンチックで、なんとなく百合感。60年代後半のイルクーツクや研究施設がエキゾチックでスラスラ読めてしまうんですけど、主人公の愛や罪の意識に共感できるかというと、そのあたりはちょっと特殊で伝わりにくかったですね。
榎本 私は、シベリアの中での静かな空気の中で女性同士がラブラブしていく感じが全編にわたって続くものと思って読み進めたので、中盤以降でそのトーンがやや変わっていく感じに置いてきぼりになってしまいました。それと、読んでいて「これ誰だっけ?」みたいなところがあり、読みにくさを感じました。
前田 あえて同一氏名の人物が登場するからでしょうか。そこは頑張って読み解いてほしい!
岡村 僕は前田くんみたいにソ連とかシベリアに興味を持っていないから、あまり適切に評価できる自信がない。
岩間 作品の質は高く、スラスラ読めたんですよね。キャラクターの描写も良かったですし、構成も練られているように感じました。でも丸茂さんのおっしゃる通り、この作品を押し出せる強い一言が、自分にも思い浮かびづらかったんですよね。それなので受賞作としてこれでいいのか? という点では結構悩ましいなとも思っています。
丸茂 実力はあります。エンタメとして致命的な傷はない。しかし、このままでは多くの方に向けて推す方法が思い浮かばない。まあこれを言い出したら「『同志少女よ、敵を撃て』は売れたでしょ!」ってことを言えますが、あの水準には及んでいない。
岩間 よくできているからこそ、別の作品でデビューを目指したほうがいいのではないかなと感じました。
丸茂 別のどういうものを書けばいいと思います?
太田 そうなんだよ。どうすればいいんだろうね。
前田 大前提として、ウクライナ戦争があり、一昔前に「ソ連」とか「ロシア」が好きだった人は、今や『ゴールデンカムイ』や『満州アヘンスクワッド』を追いかけていると思います。この方もそこに敏感に反応して、モンゴルなどのテーマを入れてるんだと思う。
太田 なるほどね。
前田 だから、「ソ連もの」という特有ジャンルが成立するのかどうかには意味がなく、ある特定の地域を深く掘って描いているということを素直に評価したいです。むしろ問題は、推薦者が指摘するのも辛いところですが、「SF」として売り出すには、あまりに大味な仕掛けで、もっと練れるのではという印象があるところ。おそらくこの舞台設定が好きな人ほど、かえって納得に至らない可能性がある。だけれど、人間描写や取材をした上での空気感の描き方には実力を感じます。
大本命は長すぎる!
榎本 では最後の候補作、岡村さんお願いします。
岡村 『紙面の月』はハイファンタジーです。この世界の特徴は、いずれ来る超ド級の大災害が〈月〉という形で可視化されていることです。この世界の複数の〈月〉が落とす影に入ってしまうと、数年単位で暗闇の世界になってしまう。だからその〈月〉から逃れるために人類間で領土争いが起きています。サンテラ教国は「太陽の力」を信仰していて、魔法のような力を行使できる能力者たちを擁します。十国連邦は科学技術が発展している国で、サンテラ教国と開戦します。主人公の女の子は、この「太陽の力」を使う能力に目覚めて、サンテラ教国で出世していく。そして十国連邦との戦争に巻き込まれていき、やがてこの世界そのものの大問題〈月〉の解決に挑んでいく、というのが超ざっくりとしたお話の概要です。
太田 長かった。マジで!
岩間 31万4800文字。
丸茂 星海社FICTIONSのフォーマットだと530ページぐらいかぁ。
持丸 印象的な設定がたくさんあって、すごく読み応えがありました。第二部の戦争パートがお気に入りです。
丸茂 ハイファンタジーを読んだな、という楽しさがありました。異星の環境、それに沿った国家、民族、風習があり、戦記要素あり、そして世界の滅亡を止められるかという王道な展開がある。よくできているなと思いました。
前田 世界全体は「ダイソン球」みたいな構造になっているんですよね。
太田 今の人類のレベルは、太陽の全エネルギーのうち、ごく一部しか使えないじゃない? ダイソン球は、恒星を人工の球殻で囲んで、丸ごと利用可能なエネルギー源にしちゃおうっていう発想。もし高度な知的生命体が存在するならばダイソン球が見つかるだろう、っていわれてるよね。
前田 はい、ハイファンタジーでありながら、SF的な大きな世界観でも勝負しています。
丸茂 どう評価するか、かなり悩みました。この作品も致命的に傷はない。というか、かなりおもしろい。でも長すぎるし、どう売ればいいんだ……。
岡村 丸茂くんと太田さんの悩みはわかります。
太田 面白いよ、でも長すぎる。だから、文句はあるのよ!
丸茂 主人公のドラマをもっと強くするとか?
太田 するともっと長くなっちゃうんじゃない? この方は「ぜんぶ書いちゃう」タイプの作家なんだよ。物語世界の細部に至るまですべてにちゃんとした設定があるのは素晴らしいけど、それをぜんぶ書いちゃうというのはそこは正直うーん……と思う。主人公のドラマを強くすべきというよりも、他のキャラクターのドラマを描きすぎだからそこは何とかしてほしい。長尺の作品だからこそ、もっと余白があるべきだよ。特に文句があるのは、後半。キャラクターがひとり死ぬごとに、その人物の過去編が始まるでしょう。何回も同じパターンが繰り返されるから、流石に食傷しちゃう。
岡村 確かに同じパターンですが、それはもはや様式美とも言えるんじゃないですか。登場人物が死ぬ直前で過去編がフラッシュバックされる、という展開は『鬼滅の刃』を筆頭にいくらでも類例はありますよ。
丸茂 最近よく見かける手法ですね。でも呆気なく死ぬ『チェンソーマン』のほうで行くべきなのかも。
太田 確かにね、不思議なことにこの方の過去編はワンパターンだけど結構面白い。またかい、と、かなりイライラしながら読むんだけど、このキャラにはこんな過去があったのかーと説得されちゃう。だから才能はある。でも! はっきり言って、終わりの方の3人分くらいの過去編は、やりすぎ!
丸茂 それで物語が長くなって、商業的にも売りにくい分量になっているのがあまりにもったいない。
太田 『Zガンダム』のジェリドを思い出してみなよ。第1話から引っ張ってきて死に際は「カミーユ、お前は俺の……」の一言だけ。しかし俺たちはあのたったひと言の言葉に囚われて、もうはや40年だよ! だからこそ「こんなに魅力的なキャラクターが、こんなに次々と死んでいくんだ。『Zガンダム』かっけえ!」となるわけじゃん!
榎本 わかります。
太田 今回の作品に盛り込みすぎた過去編はきちんと削ってほしい。削っても意味を持たせるような描き方を捻り出す。そして削った部分は、スピンオフ小説にする笑。これがスマートなやり方! 炎を使うキャラクターの話とか、めちゃくちゃ面白いじゃん。そこだけで一冊にすればいいじゃない。
岡村 手からレーザーが出ますからね。男のロマンですよ。
太田 そうそう、この作品が面白かったのは、この令和の時代に、登場する能力が『ジョジョの奇妙な冒険』の第3部なのよ!! 「植物を自由自在に操る」とか、「火を吐く」とか、言われてみると第3部でしょ? それが陳腐だと言いたいんじゃなくて、王道のベタをやってるからこそめちゃくちゃ面白くなってる。
岡村 そう、ベタなんです。古き良きJRPGという感じがします。序盤の能力を発現させるところなんかは『HUNTER×HUNTER』の念能力みたいだった。「お前にこんな能力があったのかっ……!」みたいな感じ、そして、はじめはパッとしなかった主人公の能力が、使い方次第で戦略兵器的な強大な力に変貌していく感じ。この辺は本当に好きです。だから、戦記ものとしてのパートである第二部が僕は一番面白く読めた。
持丸 個人的に戦闘詳報的な文章が大好きなんです。戦争パートは、ロングショットとクロースアップの組み合わせ、それらのモンタージュ、投入される戦力、変化する戦況など、戦争シーンの描き方として完成度が高かったですよ。うまいなぁと思いました。
榎本 戦記的に読める序盤から中盤は、ミリタリー要素が強いですよね。私なりにこの主人公の能力だけで、この状況をどう打開できるかと考えたんですよ。
岩間 流石、元自衛官……!!
榎本 そうしたら、この状況でこの能力ならば、もう「毒」しかない。しかしそれでは空気や水、食料汚染で「戦後処理」が大変になる。そう思って読んでいたら、ちゃんとそれがストーリーに関わっていました。そういうミリタリー的な設定の筋の通り方がとても面白かったです。少数精鋭の主人公たちが大部隊にどう勝つかというところも納得の面白さでした。
太田 その後に主人公が久々に帰ってみたら、あれだけいた第4分隊の人たちが、もうモブしか残っていないシーンは、かっこよかった。そういう「省略の良さ」も絶対にわかっている方なんだから、もっとそれを他でも応用したらいいのに、と思ってしまったというのもあるね。
岡村 はい、だから戦記パートはとてもよく練られていてとても面白かったのですが、その先の、世界自体を救うような結末に向かっていくところは、正直少し物語が弱かったかなと思う。
太田 ネタバレになるから少し曖昧に語るけど、この世界構造でSFをするなら、例えば「外部世界」と何か交信してコンタクトするみたいな、もっと強烈な驚きがほしくなってしまったね。
岡村 伏線はちゃんとあるんですけど「最後の驚き」は過去の新人賞受賞作かつ大長編という似た傾向の南海さんの『傭兵と小説家』には勝ててないなっていう正直なところなんですよ。
太田 あれはすごい。なかなか勝てない。
前田 みなさんとかなり同意見なので、僕はあえて違う角度から。この方はネーミングセンスが抜群にいいですね。「声に出したくなるカタカナ語」なんです。
丸茂 どういうこと?
前田 固有名詞の響きがいいです。例えば『シムーン』の「テンプスパティウム」とかね、いまだに語り継がれる語感の良さじゃないですか。それに匹敵するレベルで、この方の作品の固有名詞は素晴らしい言葉の響きです。
太田 音楽家が言うと違うね!
前田 この作品のSF的世界観は、弐瓶勉先生の作品や『サカサマのパテマ』、『メイドインアビス』のような面白い構造を持っているんだけれども、それが単語レベルの説得力でも支えられている。長くても読めてしまうのは、言葉や用語だけでもう面白いからです。
丸茂 (なるほど、わからん)
岩間 世界観がしっかりしていて、物語にも引き込まれるハイファンタジーとして、抜群の魅力があったと思います。キャラも魅力的。だから正直な感想としては全体の分量だけが受賞に向けたネックだと思います。それほどのボリュームが本当に必要だったのかな? と引っかかりがあります。
持丸 第一部は冗長でした。なかなか作品に入れないもどかしさ……。ハイファンタジー成功の鍵はどんなに長くても(全5巻くらいあっても)「最初から最後まで面白く読み進められる」だと思いますので、課題は尺と語りをどうシンデレラフィットさせるかですね。
太田 100ページは最低でも削らないといけない。だけど100ページ減らすことで、100ページ分以上に面白くなると思うし、それをやり遂げられる方だと全力で期待しよう。そうすれば何も文句ないじゃん。改稿してもう一度送ってもらいましょう!!
おわりに
太田 あれ? 丸茂先生、顔色悪くない?
丸茂 今年も出なかったなーって。来年こそは5〜6人デビューしていただきたいですね。
太田 今、賞金はどれくらいになってるの?
榎本 約504万円です。多いですね!
太田 受賞者が5人でも100万円超えるんだよ!? 次回こそ受賞作を沢山出しましょう!!
前田 その年の受賞者で賞金を分けるシステムなので、2026年中に沢山の作品を送れば送るだけ賞金を受け取るチャンスがあります! 投稿お願いします!
一同 お待ちしています!!!
1行コメント
『Exterior Galaxy ONE』
よくある内容・設定でした。それ自体は問題ではないのですが、後発で世に出すのであれば、何か驚きや新しさはほしいです。(岡村)
『χορός (コロス)』
物語が長大であるほど、「読者はなにを目的にこの作品を、展開を読むのか?」という点を強く設定していただきたいです。(丸茂)
『余った水』
全体を通して描写が必要以上に過密で冗長な印象を受けました。「なぜここでこの描写を入れる必要があるのか」を吟味してストーリー展開に不要な情報を削った方が緩急がつき、メッセージが読者に響くようになります。(片倉)
『神がかり式摩訶不式』
オムニバス風に短編5作品が並んでいますが、「連作」らしさは感じられませんでした。カテゴリやテーマを決めたほうがいいのではないでしょうか。複数のテーマやジャンルを一作にまとめたいならアリス・マンローが参考になると思います。文章は一文一文もっと彫琢する余地ありです。(持丸)
『上納テレビディレクター 赤城 耕作 ~ テレビ局の女神たち』
人物像が書き割りで、また小説というより台本のような文章で味気なかったです。(丸茂)
『悲しみの雨が上がる頃には』
完全オムニバス形式で1つ1つのエピソードがまとまっており読みやすかったです。ただ、こだわり抜いた構成や、空を使った主人公の感情表現、各話の最初の部分の予告編などについて、小説作品としての効果はあまり感じられず、作品全体を通して先行作品と比べて打ち出せる新しさをあまり感じられませんでした。(岩間)
『ノベルの友くん』
土偶とAIという組み合わせは独創的だと思いました。登場人物が別の動物や物でも成り立ってしまうので、そのキャラクター設定をしっかりすると良くなると思います。終盤のバトルよりも、最初の等身大の学生のほうが引き込まれるものがありましたので、そちらで作品にチャレンジするのも良いのかもしれません。(榎本)
『終端の観測者』
宇宙ロマンのある設定で、登場人物のやりとりも含めて楽しく拝読いたしました。物語がエンディングに向けて直線的に進行しすぎているのが惜しいです。物語の起伏を意識してプロットをさらに練ってみていただきたいです。(前田)
『ソウルズ&ハードウェア』
世界観や舞台の雰囲気は良い意味での硬質さを感じます。ただ読んでいてその世界に入り込むのにかなり苦労したのと、読点の多用で読むリズムが損なわれてしまっている印象でした。(岡村)
『エピタフコード』
エピタフコードというモチーフが面白いのですが、内部犯かどうかというところに分量を割きすぎているのではという印象を持ちました。文章がわかりやすく大変読みやすいので、情報や手数をもっと増やしてみていただいても成立すると思います。(前田)
『令和を震撼させた呪われし5年A組は、昭和からやり直す!』
こういうノリの軽さや気安さを前面に押し出した文章を好きな人もいるかもしれませんが、正直なところ私には合わなかったです。(岡村)
『白花冥幻譚(しろはなめいげんたん)』
大吟醸のような、あるいは中国の白磁のような作品です。今回一つ考えられたのは、やはりファンタジーとしての売りどころに直結するような「つかみ」。今のままですと、「純度100%」であるという作品の美点と裏腹のとっつきにくさを感じます。『ガールズ&パンツァー』の「学園艦」のように、どこに「大きな嘘」を設定したファンタジーなのかをよりわかりやすくしていただけたら、と考えます。候補作に取り上げるか大変悩みましたが、実力のある方だと思い、あえて今回は1行コメントとさせていただきました。(前田)
『森の中の小さな王国』
田舎の教師生活が詳細に伝わってくる作品でした。話が長くなってしまい何がこの物語の中心なのか分からなくなってしまい、作品の魅力が下がってしまっている印象です。思いきって1つの話に焦点を当てて内容と量を整理した方が読みやすい作品になるのではないかと思います。(榎本)
『誰か僕の姉さんを止めて下さい』
全体を通して文章に大きな読みづらさやストレスはなく、一定の読みやすさが保たれていました。設定もわかりやすく楽しく拝読しました。ただ、序盤の“つかみ”がやや弱く、物語に引き込まれる力がもう一歩という印象です。読者の印象に残るため、序盤の時点で他にはない個性や新しさが求められます。今回の作品は、やや想像できる範囲に留まっており、少し印象が薄く感じられたのが惜しいところでした。(岩間)
『幸福の天秤が傾ぐとき』
土地の法則と病気、能力、犯人の動機が結び付けられたところは面白かったです。描写の細かいところもあれば、そうでないところもあり作品に集中できないところがありましたので、そこを無くすだけでももっと読みやすくなると思います。(榎本)
『遠見のレン』
設定はとても面白かったです。序盤の掴みが弱く物語に入りにくかったので、読者の関心を惹く出だしがほしかったです。(榎本)
『ハルジオンの楯』
ほかのキャラたちもっと考えようよと思ってしまって、主人公の「知略に優れている」という点をアピールできていたかと言うといまひとつな印象でした。(丸茂)
『もう一度見たい暁』
話の要素が細かくサクセスストーリーとしてやや魅力に欠けるものでした。主人公も予想の範疇に収まるキャラクターで、もっと応援したくなるような人物で見てみたいと思いました。(榎本)
『アトランティス・コード』
3人の登場人物が軸になっていきますが、キャラの魅力が薄まっているため3人が主人公ではなくてもいいような気がしました。(榎本)
『ある日、弟が勇者の剣を抜いた。』
剣を抜くことであらぬ方向へ話が進んで行く展開は面白かったです。それ以降にさらに読者を惹きつける物が無かったように感じました。(榎本)
『ジャンプ・ジャンプ・ジャンプ』
舞台設定がよく、とても楽しく拝読いたしました。読みやすいですし、会話劇も楽しいです。幽霊が本当は何者なのか、というところがちょっと読者の予測のつきやすいところだったのがミステリとしては惜しいですね。もう一捻りを期待です!(前田)
『Voices』
どこかの架空世界で、戦争で声を失った少女と心を失いかけた青年が生きる力と愛を取り戻す人間ドラマです。誠実な人物描写と「声」の主題が光ってました。一方で戦争関連の説明や中盤は物足りなかったです。メロドラマ要素のある作品は、背景は複雑じゃないほうが作品がしまると思います。中盤は二人の関係構築に集中してラストになだれ込んでもよかったですね。感情をゆさぶる手つきはなかなかのものと思いました。(持丸)
『イリアヒガーデンホテル リゾートアンドスイーツ コオリナオールインクルーシブ』
女性二人の「友情」「愛憎」「内面の旅」…いろいろに形容できますが、最後まで二人の「人物」が見えにくかったです(像を結ばないという意味です)。「心の中の男たち」が棲みついているという設定も幻想というよりは電波に感じられました。饒舌な繊細さともいうべき荒々しい文体は好き嫌いが分かれます。いずれにしても挑戦的で印象的な作品ということは間違いないのですが。(持丸)
『関係性の Answer』
文芸部の爽やかな青春小説を期待していたら、意外と薄暗い過去に立ち入る展開でミスマッチな印象でした。(丸茂)
『ウィザーズエンド』
文体のリズムが良く、スイスイ読めました。いわゆる特殊設定ミステリの作品なのですが、真相が明かされる際に読み手に驚きやカタルシスが生まれるようなつくりにはなっていなかったです。(岡村)
『訳あり医官の検屍録』
どこか唐のような国の宮廷を舞台に、奴婢の身分でありながら「検屍の才」を持つ青年がさまざまな事件に挑みます。「検屍ミステリー」×「宮廷劇」に独自性があり、登場人物の人間性も過不足なく描かれていて完成度は高いです。一方で、全編をつらぬく「動き」に欠けている点が気になりました(伏線に立ち寄りながら結末に向かってずんずん進んでいくあの感じです)。登場人物や専門用語の整理が必須に加えて、黒幕の掘り下げは強化したいところです。(持丸)
『アウランを討て』
一定の筆力を感じる、そつのない作品でした。が、ここまでの水準であるならば、歴史ファンタジーという設定にする必然性、この舞台装置を使って問いかけたいメッセージまで見たかったです。(片倉)
『女神にセクハラするなんていい度胸ですね』
全体としても読みやすく、無理なく物語に入っていける構成になっていたと思います。
ただ、異世界転移ジャンルは作品数も多く、新作として読者の印象に残るためには、もう一歩踏み込んだ個性や新鮮さが求められます。その点においては、やや印象が弱く、もったいなく感じました。(岩間)
『裁きの影』
着想や展開に惹き込まれるものがありました。一方で、まだ筆致に粗さが残る印象もあり、今後さらに磨かれていくのを期待しています。(岩間)
『おさわり禁止のあまねさんっ!』
第四話からが面白いです。もちろん読者を裏切るフェイントの意図だと思うのですが、やはり冒頭に一気にこの大ネタを提示する方が良かったと思います。そしてキャラがもう少し立ちそうですね。しかし楽しく拝読いたしました。入間人間さんの『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』をちょっと思い出しながら、不思議な部活の世界を感じました。(前田)
『叛理逸者‐ダイヴァージェンス・リベリオン‐』
推しやスマホ文化など令和的な要素が多く新鮮に感じました。未完のように感じましたので、作品の終わりを盛り上げるような作品が読みたいです。(榎本)
『寿命』
自分で生死を選び世界をもう一度やり直せるという設定は興味を惹きました。ただ展開が遅いため前半でダレてしまっていて、せっかくのテーマが消化不良気味です。冒頭10ページくらいで起承転結の「転」にあたる衝撃的な展開を入れるのを一つの目安にしてみてください。より牽引力のある小説になるはずです。(片倉)
『絵師とフィロソフィーカード』
香港の九龍城を舞台に、ポータルファンタジーとミステリが融合した活劇風の世界観が魅力です。普通の中学生の少女が「学校の七不思議」を調査する過程で異世界の戦いに立ち向かう姿が丁寧に描かれています。一方で、読者を迷わせるところも散見されます。学園パートと異界パートをもっとスムーズに橋渡しするなど緩急のコントロールが課題でしょうか(日本の代表的なファンタジー作家の高楼方子さん、岡田淳さんは日常と異界とのスウィッチがうまいですよ)。《第一部 完》という終わり方ですが、だとしても大きな区切りが必要ですね。(持丸)
『神装のアクト』
物語としての面白さは十分に感じられました。主人公の天才技術者のキャラクターも魅力的です。ただ、全体としてはまだ粗さが残っている印象です。今後のご活躍が楽しみです。(岩間)
『都市伝説ネガウちゃん』
都市伝説やオカルトをテーマにしたキャラ文芸、という目のつけどころは良いと思いました。ただしストーリー展開やキャラクター性に既視感が強く、この作品ならではの強みを感じることは残念ながら難しかったです。(片倉)
『万有は死に帰す、されど』
着想や展開に惹き込まれるものがありました。ご投稿者さんだからこそ書けたエピソードがあったのも好印象です。一方で、まだ筆致に粗さが残る印象もあり、今後さらに磨かれていくのを期待しています。(岩間)
『アストラルコネクト』
独創的な世界観でしたが、多くの読者が興味を惹かれるかというとそうではない気がしました。構想を考える時にどのような要素がいいのか研究してみると良いのかもしれません。(榎本)
『スプリット・コンプリメンタリー・アドレセンス』
人物の入れ替わりという鉄板をミステリに活かしていただき楽しく拝読いたしました。気に掛かったのは、平易な文体なのに、なんとなく読みにくいということ。一つのシーンに盛り込んでいる「やりたいこと」がちょっと多すぎる印象を持ちました。シーンごとに、やりたいことをさらに絞っていただくことで、会話の良さなどが一つずつ際立ってくると思います。(前田)
『From Now(here) フロム ノーウェア・ナウヒア』
大変クオリティのある作品を投稿いただき、ありがとうございます。ハイブローなSF設定で、面白いと思う一方、難解だと思うところもあります。ピンポイントで刺さる読者もいると思う反面、やや設定盛り盛りすぎて食べきれないぞ、というのが率直な感想です!(前田)
『Malpractice: 医師失格』
医療ものとしてのディテールには確かな説得力がありました。しかし他方で、医療の世界がわかる人にしか伝わらない細かいやりとりが多く、医療界を知らない者としてそこまで楽しめませんでした。専門知識のない一般読者も感動できるような、生命を賭けた人間ドラマの側面をもっと強調した医療ものを希望します。(片倉)
『銀河を渡るプラネター』
近未来SFとしての世界観や展開にワクワクしながら読ませていただきました。物語の流れもわかりやすく描かれていましたが、全体としては、もう一歩この作品ならではの独自性が感じられると、より印象に残る一作になると感じました。(岩間)
『妖狐の昇進譚』
物語の展開にワクワクしながら読み進めました。続きが気になるような、でもきれいに締めくくられているラストも素晴らしかったです。ただ、全体としてはやや既視感もあり、この作品ならではの工夫がもう少しあると、さらに魅力が際立つように感じました。(岩間)
『逃げたがりの料理人は、死にたい不死王と旅をする。』
冒険譚としては面白かったです。ですが、料理人でなくても良いように感じられ、キャラクターの弱さを感じてしまいました。(榎本)
『誰が愛したエカテリゼ』
どこか19世紀の北欧を思わせる片田舎を舞台に、過去の捜査記録から時効間近の未解決事件に挑みます。のこり3分の1からの解決編は、道徳的なジレンマを探求したもので、たいへん読み応えがありました。(北欧というよりも)イギリスの歴史ミステリ的なプロットと雰囲気が大好きな作品でした。人物描写、背景描写にもっと奥行きがあればと惜しまれます。奥行きというのは、たとえば紅茶を飲むシーンで砂糖を入れていたら、背景に階級や植民地が控えていることが伝わるというようなことですね。難しいんですけど。(持丸)
『天神教授の推理ゲーム』
手つきは悪くないものの、このコンセプトは『文学少女対数学少女』の精緻なロジックの応酬とどうしても比べてしまう! また送ってください(作中作ミステリからは離れたほうがいんじゃないかなと思います)。(丸茂)
『ヒカリ・ザ・フライデーナイト』
文章はしっかり読めますし、作中で起きていることもちゃんとわかります。ただ全体的にこぢんまりとした印象で、突出した新しさや驚きはあまり感じませんでした。(岡村)