
ロジック・ロック・フェスティバル
第六回
中村あき Illustration/CLAMP
新人×CLAMP 「新本格」推理小説(ミステリ)の正統後継者・中村あきのデビュー作! まだあった「新本格」推理小説(ミステリ)! 全ミステリファン注目の新人登場、星海社FICTIONS新人賞受賞作。
17 星のお告げと逆転密室(万亀千鶴の告発)
この推理合戦の発端となる疑念を立ち上げた千鶴は、やはり真実の追及に誰よりも貪欲であり、誰よりも事件に胸を痛めているのだろう。浮かべる憂いに満ちた表情はいつものおとぼけ少女のそれではない。
「よし、分かった」と会長。「それなら万亀、君に一番手をお願いしよう」
「はい、ありがとうございます。嫌なことは手早く終わらせたいので、単刀直入にいきますね」
会長の指名を受けた千鶴は立ち上がり、そう前置きした。
「この事件の犯人は――金牛遥さん、あなたです」
「な、なんだって!?」
不変とされていたはずの前提がいきなり崩され、思わぬ不意打ちに金牛事務員は声を上ずらせた。
千鶴のトンデモ推理に度胆を抜かれたのは、何も犯人だと指さされた者だけではなく。
「待ってください万亀さん。金牛さんは階段にいた女バスの子たちの証言に含まれていないんです。ここの証言を信用することは万亀さんの懸念の端緒にもなった大前提のはず。ここを疑うと容疑の輪はもはやどこまでも拡大していきますよ」
副会長の反論に千鶴は冷静に受け答えた。
「あたしは階段の先輩たちの証言を疑っているわけじゃありません。この証言が意味を持つのは死亡推定時刻を信じてこそだと気付いたんです。ここで皆さんに訊きたいのは、もしあき君と金牛さんの死亡推定時刻の予想が食い違っていたら、どちらの意見を取ったかということ」
どういうことだ?
僕は一瞬啞然としたが、次の瞬間には思い及んだ考えが口を突いて出てきていた。
「……そうか。金牛さんには確かな医学的素養があった。満場一致でそちらの意見が取られるはず。僕だってそうなれば自分の意見を訂正したし、それで納得もしたと思う」
「そうだよね、あき君。つまりあたしが主張するのは金牛さんの専門学校云々の話は咄嗟のでっち上げなんじゃないか、またはそれが本当でもそれを笠に着て適当言ったんじゃないかってこと。自分を容疑の外に出すために、噓の死亡推定時刻を実際よりずっと以後に断定したんです。金牛さんは足を怪我した先輩たちが階段に居座る前に、既に灘瀬先生を殺害し、事務室に鍵を取りに戻って現場を施錠するまでを済ませていたんです」
「……ちょ、ちょっといいかげんにしてくださいよ」金牛事務員がショックから立ち直り、ようやく反撃に出た。「僕が犯人ならそもそも研究室に鍵を掛ける必要がないでしょう? 自分を疑ってくれって言ってるようなもんじゃないですか」
「そこがキモなんですよ」しかし待ってましたとばかりに千鶴が切り返す。「自分から言ってくるなんてますます怪しいですね。簡単なたとえ話からします。仮にだけど、殺人現場にとあるAさんの名刺がこれ見よがしに落ちていたらどう思いますか?」
「んー、まあさすがにあざといかな」答えたのは線太郎だ。「それを見て『Aが犯人だ!』なんて誰も言わないと思う。むしろ誰かがAさんに罪を被せようとしたと見るのがまだ自然じゃないかな」
各々が頷いた。それが正常な思考の流れだと誰もが賛同を示す。
「そう。ではこれを今回の事件に当てはめてみます。この事件の大きな特徴は密室。さて、この部屋に施錠をしようと考えた場合、誰が一番簡単にそれができたかを考える。これは当然、鍵を管理している事務員に他ならないですね」
なるほど。言わんとしていることが分かった。いつもふざけている千鶴にしては意外な、捻くれた面白い考えだ。
「つまり現場への施錠は『事務員が犯人』というあからさまな名刺。金牛事務員はそれが逆に自分の安全を保証すると考えた。自分の不利になる証拠は自分で置くはずがないという心理を逆手に取ったんです」
一同は千鶴のアクロバティックな推理に気圧されているように見えた。彼女の見た目や普段の素行とのギャップも手伝ったんだろう。誰もが聞き手に回るしかないまま推理は終局へ。
「そしてこれが決定的。ダイイング・メッセージです。あたし、けっこう占いが好きなんだけど、それでぴんときたの。金牛って苗字を最初に聞いた時、一番最初に思い浮かんだのも金牛宮だったし」
「金牛宮?」と僕。
「黄道十二宮っていって、惑星が運行する帯状の道筋を十二個に分けたものの一つだよ。占星術なんかに使われるの。で、これは黄道十二星座にも対応してるんだけど、そっちはけっこうメジャーだよね。金牛宮はそれでいうと牡牛座に当たるものなの」
千鶴がなんだか博識に見える。
「で、アストロロジカルシンボルっていう十二宮それぞれを表すマークがあって、金牛宮のそれがこんなの」
とてとてと黒板の方に歩いて行った千鶴が背伸びしながら描いたものがこれだ。
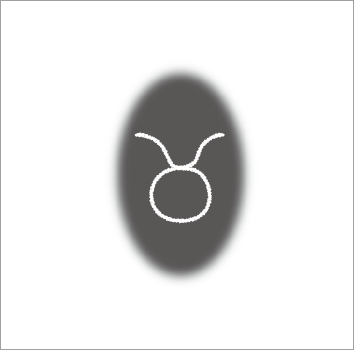
「灘瀬先生はこれを描いていたんです。最初は円の描き始めと描き終わりが上手く繫がっていないだけかと思ったけど、実はこのつのの部分だったんですね。
以上であたしの推理を終わります。素直に自分の罪を認めてください、金牛さん」
ぱちくりと大きな目をしばたたかせて千鶴は演説を終えた。
聞き方はというとそれぞれ黒板に描かれたアストロなんとかを眺めて自失している。
そんな中、こほん、と鋭い咳ばらいが沈黙を裂いた。
「千鶴、さすがに暴論よ」りり子であった。「自分の過去の学歴なんて警察が介入すればすぐ明らかになる。この場限りで姑息に偽っても意味がない。死亡推定時刻の判定も然り」
「……あ、そうだ!」金牛事務員が自我を取り戻したようだ。ポケットから財布を取り出して中を漁っている。「あった……これ、見てください」
金牛事務員がこちらに向けてかざしたのは、どこかの実験室のようなところで白衣を着た彼が仲間数人と写っている写真であった。
「専門学校時代のものです。これで納得いかなければ、ここに写ってる友達とは今も交流があるから電話して訊いてもらっても構わない。あと自分の名誉に懸けて言うけど、死亡推定時刻の判定はかなり正確だと思う。時間をこれ以上絞るのは不安だけど、特徴的な指標が出ているし、犯人が誤認を狙った細工をしている様子もない。法医解剖の結果と少しでも誤差が出たら、自分から捜査攪乱の罪でお縄についてもいいくらいです」
証拠写真を掲げながら強い調子で迫る金牛事務員に今度は千鶴がたじたじとなる番だった。さらに線太郎が追い打ちを掛ける。
「冷静に考えたら密室の件の論法も非現実的か。『自分が犯人だ』という証拠を排除するためではなく、わざわざ残すために現場に帰るというのは、ある種発想の転換ではあったけれど普通じゃない。ハイリスクローリターンだってすぐ分かるもん。ダイイング・メッセージはよく思い付くもんだと感心したけど」
「金牛さん、血だめだしね。間近であれだけ鮮血が噴き出すのを見たらどうなるか分かんない。これも演技や噓の設定なら後々すぐばれるんだから意味ないし」
僕がぼそっと呟く頃には、そこにはすっかり萎縮した千鶴の姿があった。
「あの……ごめんなさい、金牛さん。突貫推理で噓つき呼ばわりの挙げ句、殺人犯だなんて疑ってしまって……」
「い、いや、まあ、誰かしらを疑わなきゃならないわけですし、愉快な会合にならないことは最初から分かってこの場に臨んでますから。この短時間で推理を組み上げて、それを筋道立てて話せるのはそれだけでもすごいことですよ。こうやって推理を披露してくれる人がいなければ議論も進みません。僕は気分を害していませんし、万亀さんも落ち込まないでください」
「……ありがとうございます」
金牛事務員の大人な態度で少し場の雰囲気は和らいだものの、殺伐とした犯人告発は続こうとしていた。
「あの」副会長が前のめりになるように発言して、一同の目はそちらに向いた。「次は僕に推理を発表させてもらえませんか」
それはほとんど会長ただ一人の許可を得るために発せられたように思えた。
18 失われた血の絆(成宮鳴海の告発)絆
「分かった。次は成宮にお願いしよう」と会長。「私の出る幕がなく終わるなら、それが理想だ」
「全力を尽くしましょう」
会長の勅許を得、副会長は立ち上がる。微かな武者震いが収まるのを待って、副会長は口を開いた。舌の回りは非常に滑らかだった。
「万亀さんの推理も限られた時間でよく練られたものだったと思います。しかし密室を重要なファクターとしたところにまず問題があったんです。密室を作る方法など実はいくらでもあるんですよ。例えば合鍵を作っておくという方法。これならば別にいつだって誰だって行えたでしょう。特別な要件はいりませんし、不可思議なことは何もありません。
それよりもっと肝心なことは、人一人を殺害しようとするに至るほどの動機の解明です。殺意の明確な有無、それに係る刑の軽重、そうした法律的な解釈に僕は詳しくないですが、しかし現にカッターを相手に向けて振り回すという行為が行われたのです。一般的に見て、そこには被害者に対する殺意が十分に介在していたものとして認められると思います。そうなればこの場においても、強力で明確な動機のあるものに容疑が向くのが当然の帰結。この事件は一見して確固たる動機が見えにくいですが、しかし僕は様々な符合から隠された動機を発見してしまったんです。
ではやはり結論から――衿井会長、あなたが犯人だったんですね」
「……何を言うかと思ったら。成宮、正気か?」
会長が答えて静かに二人の視線が交錯した。副会長は怯む様子を見せない。
「意識はしっかりしているつもりです。会長こそ早く観念して自分の罪を認めていただけるとありがたいのですが」
「言うじゃないか。よほど自信のある推理なんだな。私はもちろん犯人などであるはずもないが、聞くだけ聞こう」
肩を落とし、目を伏せる副会長の様子は、これより会長を糾弾しなければならない胸の痛みに堪えているようだった。やがて眦を決して切り出した。
「仕方ありません。僕は会長を心から尊敬しています。それ故に会長が進むべき道を誤った時、僕は黙って見過ごすわけにはいかない。それではこれからお話ししていきますが、会長、この先あなたのつらい過去に触れることを前もってお許しください。
やや見えにくくなっていたとはいえ、この事件の動機はごくありふれたものと言ってしまってもいいかもしれません。それはつまり家族間の問題、その捩れ。灘瀬先生は会長の実の父親だったんです」
どよめく一同。これは、しかし、一気に事件の様相が覆った。
ただこの場には意味を瞬時に理解できない者の方が多かった。
「実の……?」と混乱した様子の千鶴。
そう、彼女に加えて、線太郎やりり子、金牛事務員らはもちろん、この込み入った事情を知る由もないのだ。
会長の方を見やりながら、心苦しげに副会長は述懐した。
「……会長の父親は会長がまだ幼い頃、愛人と共に失踪しました。会長の話では今はどこかで教鞭など執っているらしいですが、元の家族に会いに来ることは一切なかったそうです。中村さんは会長が倒れた時、聞きましたよね」
僕は黙って頷いた。副会長は続ける。
「自分の子も愛せない人間が他人の子を偉そうに教えている――会長の話を聞いた時、僕は正直その父親の神経を疑ったものです。しかし今思えば彼もやはり人の心を持っていたんです。自分の娘が今どうしているか気にならないはずがなかった。ただ今さら父親面して会いに行けない彼は教員として娘のすぐ傍にいようとしたんです。どこかで教員をやっているというのは灯台下暗し、実の父親はここ鷹松学園に赴任していたんです。
僕はデジカメの中の保険証の写真にぴんと来ました。簡単な算術の問題、年齢に関する符合がここから見出せました。会長の話によると、父親が出て行ったのが二十五歳で結婚した翌年、その頃会長は一歳になるかならないか、という時期だったといいます。つまり生年から逆算して、現在四十三歳の灘瀬先生はこの条件にぴたりと該当します。
会長はある時偶然、自分の父親が灘瀬先生であることを知ってしまった。それはつい今日しがただったのかもしれません。長い間の懸念が積もり積もって確信に変わったとも考えられます。ともあれ愛人にかまけ、家族を捨てた父を当然許せるはずもない。感動の再会とはならなかったでしょう。最初は確認と談判のつもりで会いに行ったかもしれない会長も、結局話の流れからかっとなってカッターを手にしてしまった。
殺人は最低の犯罪ですが、今回のケースはそこに少なからぬ情状酌量の余地があると僕は思います。今からでも遅くありません。自分の罪を正直に認めてください」
家族の隠された因縁譚を一息に語り終えた副会長に向かって、会長はただ一言、口にしただけだった。
「……ダイイング・メッセージの解説はいいのか?」
「……解釈は可能です」副会長は少し逡巡して。「会長直々のご要望であれば幾らでもお話ししましょう。衿井会長の名前は雪。名前で『ユキ』という音は珍しくありませんが、スノウの意のこの字をそのまま当てるのはやや珍しいのではないでしょうか。少なくとも僕は今まで出会ったことがありませんでした。そして自然現象であり、気象条件そのものであるため、これは天気記号というもう一つの表し方ができるんです」
そう言って副会長も低いステージに上がると、チョークを手に取り、黒板と向かい合った。描かれたのは次の記号だった。
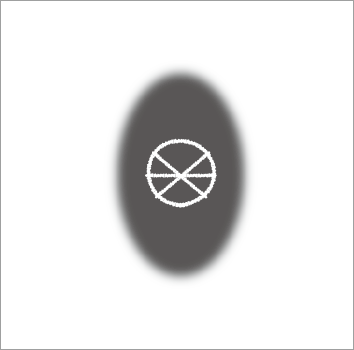
「この記号を描く途中だったんです。中の部分を描き入れる前に力尽きてしまったようですが。漢字で書くより簡略で、同音異字の『ユキ』との区別もできる。『衿井』と書けなかったのは別れた女性の名字だから抵抗があった――と見るのはさすがに邪推でしょうか」
会長はそれを聞くと、なんと堪えきれないとばかりに吹き出したのだ。
音楽室を包んでいた悲痛な雰囲気は一瞬にして氷解した。
「くふふ――いや、失礼。なるほどね、見事だよ。想像力の豊かさは賞賛に値する。脚本家にでもなったらいいんじゃないかな」
そんな会長の姿を見て、副会長は明らかに狼狽した。
「な、何を……」
「何がどうもないさ。灘瀬は私の父親ではない。それだけのことだ」
「……灘瀬先生はクリスチャンだったらしいですね。クリスチャンに離婚はご法度なんて古い観念を持ち出したりしませんよね」
副会長の最後の抵抗も会長はばっさり切り捨てて。
「私は無神論者だから詳しくは知らないが、宗派によって違うんじゃないか。教会が諫めてもどうにもならない時代の流れもあるだろう。まあそれは別として――保険証を精査したのは分かった。では、献血カードは見たか?」
「はあ?」
「写真を撮ってきてあっただろう? 実は私も自分のを持っているんだが」と財布を取り出し、中を探す会長。「これだ。献血をすると誰でももらえるんだよ……で、ほら、血液型が書いてあるんだ。デジカメから灘瀬の献血カードの画像を探してみろ」
副会長はデジカメを引っつかんだ。カーソルのボタンを格ゲーやってるかのごとくがちゃがちゃと押している。そのうちに目当ての画像を見つけたようだ。
「私はAB型、さて灘瀬は?」
会長の問いに答える副会長の声は蚊の鳴くよう、いやミトコンドリアが鳴くようと形容できるほどで。
「……O型です」
「そういうことだ。両親のどちらか片方がO型なら、AB型は生まれない。病気や突然変異による特殊な事例がないではないが、その確率とて考慮に値しないほど僅少だろう。よって私は灘瀬の娘では有り得ない」
あまりにもあっさりと論理が綻びを見せて愕然とする副会長。
「恨みつらみもないわけじゃないがもう今さらだよ。しょうもない男を一人殺すためだけに自分の人生を棒に振ったりしない。成宮は私がその程度の女だって思うのか」
「い、いや……そんなっ」
もはや少しからかうような口調の会長。唇を尖らせたその様子に、ますます面白いくらいに副会長は動揺していた。
「そもそも動機は直接的な犯行を示す証拠にはなりませんよ」このタイミングで切り出すりり子もまた容赦がない。「それとその人物に犯行が可能であったかは別問題ですから」
重ねて僕も気になった点を指摘しようとするのだから人のことは言えない。
「密室を破る手段として合鍵を挙げたのも安易と言わざるを得ません。なぜならこの事件は前提にもあるように突発的犯行と見てまず間違いないからです。合鍵等の込み入った下準備はこの場合、不可能と考えるべきです」
「すみません、会長……あの、なんて謝ったらいいか……」
「大丈夫だ、成宮、気にしていない。金牛氏も言っていただろう。悩ましいが今はこうするしかないんだ。しかし無為に疑いを向けられ、傷つく者を傍観しているのもそろそろつらくなってきたな。中村には悪いが――この推理合戦、次の私の番で終わらせてもらうよ」
会長は威風堂々と立ち上がり、それだけで木槌がなくとも場は静粛に満ちた。
まるでテミスの化身といった風格を前に誰が口を開けようか。
裁きが今、下されようとしていた。
19 大浪漫的秘密の抜け穴(衿井雪の告発)
「前二人の意見は中々興味深く聞かせてもらった。ただやはり成宮の述べた動機というものは、往々にして探偵の単なる創作になりやすい。論理的にフーダニットを追及する場合、この事件の重要なファクターは密室で間違いないんだ。ただ密室とはやはりその不可能性によって、自分を容疑の圏外に置くための手法と見た方がより自然だろう。万亀はその点、少しイレギュラーに思考してしまったが、今回の事件の犯人の狙いも自殺への見せかけか、あるいは鍵を自由に扱える者に注意を向けさせることにあったはずだ。
私が加えて着目したのは、〈前提〉で触れているようにこれが突発的犯行であること。よって密室の細工は犯行の後から要請されたものだ。となると、針や糸、磁石、日曜大工的装置によって密室工作を行ったという見方はどうだろう。行き当たりばったりでそんなことができるものだろうか。先ほど言われたように合鍵やピッキング等の準備も不可能だ。五、六年前に消失した社会科研究室の鍵をひょんなことから手に入れていたなんてことも考えにくい。
つまり論理的に考えて密室を作成する手段は最初から一つしかなかったことになる。実際にマスターキーを用いて外から施錠する以外にはな」
「……やはり僕が疑われるんでしょうか」
金牛事務員の言葉はにべもなくはねつけられた。
「あなたや菊池氏が犯人でないことは先刻証明されている。また、言うまでもないが、自殺説もとうに否定され、〈前提〉にも加えられているな。つまり、犯人が密室の作成によって狙ったミスリードはことごとく不発に終わり、結果その限定的な密室作成手法は犯人の要件を狭め、自分で自分の首を絞めることになってしまったわけだ。
まとめよう。すなわち、この事件の犯人は――『事務員でないにもかかわらず、怪しまれずに事務室に侵入し、鍵の確保・返却が可能だった人物』に限られる」
「でも、そんなこと……忍者じゃあるまいし、できるわけ……」千鶴が独りごちる。
「しかしこの一見有り得ないような要件を満たす人物がこの中に一人だけいるんだ。すなわちその人物以外に犯行は不可能。そうなれば犯人は自ずとその人物に確定となるわけだ。
そう――山手、君だよ」
思わぬ奇襲に絶句する線太郎。ようやくといった調子で二の句を捻り出した。
「……無茶苦茶言いますね。僕は透明人間にでもなれるっていうんですか」
「透明人間? いやいや、ウェルズのようなSFじゃない。現に実在した歴史の一部分、地に足の着いたノンフィクションだよ――私たちには熱心に研究していたテーマがあったじゃないか」
線太郎が顔色を変える。
「もしかして……」
「鷹松学園の地下軍事施設さ」
一同があっと息を吞んだ。
「ああ、聞いたことありますね、そうした施設が今も現存しているかもしれないという噂……」金牛事務員もご存じのようだ。
「そんな大層なものでなくてもいい。地下通路、いや秘密の抜け穴程度のものでいいんだ。君は調査と探究の末、実際に発見したんじゃないのか、そういった類いのものを。そしてそれを使って自由に、かつ極力人目に付かない形で君は事務室に出入りできたんだ。
施設の中枢部は今の事務室辺りの地下にあったと目されている。今でもその付近の床や壁やなんかには、仕掛けの一つ二つないとは言い切れない。さらに事務室から真上に直線を四階まで引っ張ってくればそこが社会科研究室だ。山手とは前に学区と司令部を繫ぐエレベーターの話もしたな。もしそれがまさに新館を縦に貫く形で実在しているとすれば、わざわざ東側階段を使わずとも、この事件に主要な部屋を行き来することだってできたわけだ。それこそ山手は誰にも見つからずに校内を跳梁跋扈できるほど、そうしたからくりを把握していたのかもしれない」
線太郎は口をあんぐり開けたまま動けない。他の同席者も一様にそんな調子で。会長は勇壮に終曲へと駆け抜ける。
「ダイイング・メッセージに関してはもういいだろう。名前との結び付きは最も直接的なんだから。なぜ先行者たちがあれほど深読みしてどつぼに嵌まってしまったのか疑問だよ。あの血の輪っかは、簡略化した環状線の路線図を示していたんだ。どこぞのCMソングでもお馴染み、最もポピュラーなまあるい鉄道路線――山手線のな。以上だ」
簡にして要を得、説得力のある推理。
御伽噺が現実に結実したような感慨。
その論理の飛躍の華麗さに、一時、雪の降る夜のような静謐が音楽室に満ちた。
しかし。
処女雪で覆われたこの論理の聖域もまた、完全なものではなく。
先陣を切ってそこに異議の足跡を残すことになったのは、容疑を掛けられた線太郎その人だった。彼はわずかな逡巡を見せながらも、簡約な知見によって会長の論理の根幹を揺るがした。
「隠し通路くらいあればよかったんですがね、会長。はっきり申し上げます。この学校の地下軍事施設は既に埋められていますよ」
「なんだと!?」
ざわめきは会長を中心に波紋のように広がった。
「僕が調査と探究の末に発見したのはそんな不寛容な現実だけでした。僕はフィールドワークや様々な方へのインタビューを織り交ぜたリサーチの中で、最終的にこの学園の設計者にまで行き当たったんです。設計図の写しから、地下を音波で見た解析図なんかも見せてもらいましたよ。めぼしいものはなーんにも遺ってませんでした。記念に携帯のカメラで幾つか撮らせてもらった資料もあるんで、今この場でも証拠として提示できます。結局、怪しげなデッドスペースやなんかも、可及的速やかに工事を行わなければならない性格上に生じた歪みだったに過ぎませんでした。
先日この結論に至った時は、はっきり言って相当ショックでしたよ。僕としては不謹慎ながら今の会長の説に少しわくわくしてしまったくらいです。まあ、でも学園がまるでからくり屋敷だなんて話になると、それはもう絵空事もいいとこです。何の根拠もありません。よって僕が犯人などという推理も残念ながら見当外れです」
会長の論理の美しさはこの細き一本の糸で、全体が繫がれていたことに由来した。ただそれ故に支えを失ったその瞬間、一斉に離散していき、あたかも地下軍事施設の幻影のように跡形もなく消え去ってしまった。
あゝ、儚きもの、汝の名は浪漫――。
「まったく……情けない有様だな。この通りだ、山手。杜撰な推理によって君の品位を貶めてしまったこと、どうか赦してもらいたい」
「顔を上げてください、会長――と、このやりとりもなんだか定番になってきましたね。こうなってくると、容疑を向けられずスルーされてる方が不安になってくるくらいですから、全然気にしないでください。それよりほら、次いきましょう」
「ありがとう。では」会長が伏せていた目を上げて。「中村、ラストだ。決めてくれるか」
視線が収斂していくのを感じる。
陽は既に大きく傾いていた。窓から斜めに差し込むその光は、何かを照らし出すというよりもむしろ音楽室に存在する一切の陰影を強調していた。
僕は気持ち、頤を上げる。
「最後に出た大仕掛けにはミステリ好きな僕にとって少々心惹かれるものもありましたが……まあ正直失望しましたね。何はともあれ無能な探偵たちの皆さん、お疲れ様でした」
僕は一つ大きく息を吐き出し、わざとらしい挑発の言葉と共に六人を睥睨した。
「犯人宣告のカタルシス、さすがに快いですね。ここまで来たらもう勿体ぶるつもりはありませんから心して聞いてください。
いいですか、灘瀬朝臣を殺したのは、この僕です」
20 犯人探偵(中村あきの告白)
言葉の意味を認識できたかな。
それではどうか思う存分、周章狼狽してもらおうか。
僕は芝居がかった調子で首を振る。
「愚鈍な探偵たちでした。まさか犯人自ら解決編を担当する羽目になるとは。ある意味、探偵と犯人の一人二役ができてお得なんですかね」
「あき……どういう……」
目をむく線太郎に向き直った僕は努めて冷徹な響きを意識した。
「自白だよ、線太郎。プレイヤーがいなくなったらゲームは続行できないからね」
そして咳払いの後、再び一同を見回した。
「ただ探偵が尽きたからといって、このまま解の提示を放棄して幕を下ろすのはご法度です。ここからは仕掛け人自身が物語を終わらせるために一つ一つ種明かしをしていかなければなりません。退屈な時間ですが、元はと言えば無能な探偵諸氏のせいなんですからね。ご清聴願いたいと思います」
場を支配するのは混乱。言葉を失った聴衆ははたしてどこまで頭が回っているだろう。しかしこの異様な雰囲気こそ僕の狙い通りなのであった。
「順を追って説明していきましょう。僕はパソコン室の使用のため、事務室に鍵を借りに行ったと言いました。その時、事務員の金牛さんは自分の頭に載っかった眼鏡を一生懸命探していましたね」
自分の名前が出たことにびくりとした金牛事務員だったが、すぐに合点がいったという風にぶんぶんと首を縦に振った。
「ああ! そうでした。やっぱり中村さん気付いてたんですね」
「気付かないわけないですよ。その時はただ面白がってそれには触れなかったんですが。しかしそれが事の発端でした。近眼の金牛さんはパソコン室の鍵と間違えてマスターキーを僕に渡していたんです」
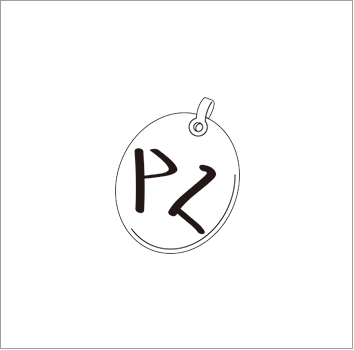
驚愕は毛細管現象のようにじわじわとオーディエンスの間を満たしていく。そしてさながら爆心地からやや離れた地点に届く爆風のように、数瞬の後、炸裂した。
「最初は僕も気付きませんでした。タグの字はミミズののたくったような字でしたから。先入観から僕はマスターキーを示す『マス』の文字を『PC』と読んでいたんです。その鍵でパソコン室が開いたらそれがパソコン室の鍵だと思い込んで普通は終わりでしょう。
しかし僕はそれがマスターキーだということに気付いてしまった。社会科研究室の鍵が紛失していることも知っていた僕は、この鍵の錯覚を利用して推理小説のような密室が構築できることに思い至ったんです。
いてもたってもいられなくなりました。自分の考案した密室を殺人と絡めて実行に移したいという衝動に駆られたんです。ミステリをよく読む僕には、以前から探偵への憧憬から謎解きへの衝迫が湧き起こることが度々ありました。しかし今回のそれはそんなものとは比べ物にならなかった。あの時の僕には小説という枠に囚われている世界を現実に生み落とすこと自体が可能だったのです。どうしようもありませんでした。気付いたら僕は灘瀬先生を殺していたのです。一つの魂を推理小説の神に捧げ、ミステリ的世界を召喚することを選んだのです。彼を殺したのは単に彼が社会科研究室にいたから以外にありません」
「それが……動機だっていうのか……?」
会長の声は震えを隠しきれておらず。それでもなお威厳を保とうとする姿はいじらしくもあった。
「有り得ないと思うかもしれません。納得しかねる方が大多数でしょう。しかし世の中には小説のトリックで殺人を犯したミステリファンや、実際に行った人殺しの経緯を自分の作品に書いて御用になった推理小説家もいます。異常ではあるかもしれませんが、そういった抗い難い感情の突き上げが全くないとも言い切れないのです。現に僕がそうだったのですから」
犯人が自ら語る心情に口を挟める者がいるはずもなく。僕は淡々と解説を続けた。
「僕が犯行に及んだのはドリンクコーナーにジュースを買いに行った帰りです。アリバイを検討してもらえば分かる通りそこにしか時間的余裕はありません。トリックを思い付いてすぐでしたし、もちろんまっとうな凶器を用意する暇もありませんでした。だからその場にあったカッターを凶器に使うしかなかったのです。灘瀬先生の隙を見てカッターで切りつけましたが、彼が咄嗟に身を翻したので急所を逃しました。傷が浅かったことも察知していたので、すぐに反撃を警戒しながら第二撃を繰り出そうとしたんです。その時でした。灘瀬先生が胸を押さえてうっと呻いたっきり倒れて動かなくなったんです。発作だ、と僕は思いました。しばらくするとみるみるうちに灘瀬先生の体は弛緩していき、恐る恐る脈を確かめたら既に死んでしまっていました。こんな僕でもその時ばかりは人の命の呆気なさを思ったものです。しかしそれは突如降ってきた素晴らしいアイデアにかき消されました。ダイイング・メッセージを遺すことを思い付いたんです」
「そっか……あれは結局、犯人が捜査の混乱のために遺した……」
「ご名答、千鶴。あれ一つ加えるだけで現場はより推理小説の様相に近づきました。様々な解釈を誘発するためにはシンプルなものがいいと思ったんです。結果は大成功でしたね。ダイイング・メッセージ解釈の際の空想力という点においてのみ、探偵方を褒めて差し上げてもいいと思います。こっちは笑いを堪えるのに本当に苦労しました。そこで僕も少し考えてみたんです。あの円をαのなり損ないだと考えれば、頭文字がAの『あき』にも結び付けられませんか? ……いや、やっぱりこれはあまり面白い解答ではないですね。さすがユーモアのある探偵たちは違います」
安っぽい挑発はなんの反応も生まなかった。
しけった火ぐちのように各人は戦意を喪失していたのだ。
「……こほん、もう少しだけ辛抱願います。皆さんはこの密室トリックに面倒な後始末があることにお気付きでしょうか。このトリックは犯行を実行した後、僕の持っている紛れもないマスターキーをパソコン室の鍵だと事務員に誤認させたまま返却する方策が必要なのです。とはいえこれは金牛さんが既に眼鏡を見つけてしまっていた場合、かなりの難題となるはずでした。ただし運命の女神は僕を見放さなかった! なんと事の成り行きでマスターキーを返す前に、『マスターキーを取りに行く』という願ってもない任務が僕と線太郎に与えられることになったのです。金牛事務員がマスターキーの貸し出しを渋ることも予測できたので、僕はこの申し出を喜んで受けました。
僕は話の流れを利用して事務室に押し入ると、すぐに鍵の収納してある金属製の箱の前に陣取りました。金牛事務員や線太郎は僕がそこでパソコン室の鍵を返し、マスターキーを借りているように見えたかもしれません。しかしあの時僕がしたのは、元々箱の中にあったパソコン室の鍵を取り出し、『借りていた鍵を返します』と言ってちらつかせてから、再び箱の中に戻しただけです。あとはそのまま事務室を飛び出し、ずっとポケットの中にあったマスターキーを今しがた取ってきたかのようにして皆さんと合流した――。
これが密室のトリックの一部始終です。要するに僕は、先ほど会長の提示した『事務員でないにもかかわらず、怪しまれずに事務室に侵入し、鍵の確保・返却が可能だった人物』の変奏に該当していたわけですね。少しややこしいですが、お分かりいただけましたか?」
淀んだ空気はあるはずのない重みを感じさせるまでになっていた。しばらく待っても口を開く者は現れない。
疑問点の追及がないことに胸を撫で下ろすと、僕は少し遊びを入れて締めくくることにする。
「話は逸れるかもしれませんが、今回のことで僕には一つ分かったことがあります。それは、ミステリにおいての主役は探偵ではない、ということですね。一般にもてはやされ、スポットライトを浴びる彼らは所詮受け身な存在なんです。真に動的でクリエイティブなミステリの主賓、それこそが犯人。パッシブな探偵など彼らの隷僕に過ぎないのだと。
……さて、戯言はここまでにしておきましょう。僕の言いたいことは以上です。反省の色がないのは見ての通り。あとは煮るなり焼くなりお好きにどうぞ。通報に関してはいつでも構いません。僕は覚悟もできてますし、無駄な抵抗も自決もしませんから」
僕が言い終えると、おそらく今日最も長い沈黙が音楽室を支配した。
誰もが面を伏せている。
しかし室内は無言ではあれど、無音ではなかった。
暮れなずむ窓の外からは耳を澄ませずともファイアーストームに生徒たちが上げる歓喜の声が聞こえていたからだ。
じきに鷹松学園を、警察の捜査とマスコミの好奇の視線が蹂躙するだろう。
それは通報と同時に始まり、誰も止めることはできない。
火柱の周囲で騒ぐ生徒らが少なくとも今この時点において笑っていられるのは、会長が通報の一時留保を決行したからだ。
提案した彼女自身は今、何を思っているのだろう。
副会長は今、何を思っているのだろう。
金牛事務員は何を思っているのだろう。
友に裏切られた線太郎は? 千鶴は? そして――。
「――一つ、聞かせてくれるかしら」
場の沈黙と僕の思索、両方に華麗な終止符を打ち付けたのは鋸りり子だった。
まさかこのタイミングで――。
僕は必死に動揺を押し隠し、体勢を立て直した。
「……どうぞ、りり子」
そう答える際、僕は努力の甲斐あって真正面から彼女の視線を受け止めることに成功した。
「会長と中村君と私で研究室を捜索した時だけど、灘瀬先生の私物には携帯電話が見つからなかった。私は彼がブルーの折り畳みの携帯電話を使用しているのを見掛けたことがあったから、あの場にそれがないことに違和感を覚えたわ。それは結局、あなたが証拠の残る可能性を危惧して処分したということでいいのかしら?」
携帯電話、か。そういえば見当たらなかったな。それなら――。
「そう、あれは犯行時に僕が持ち去った。その場で処分してもよかったけれど、一刻も早く現場を立ち去りたかったからね。どこに処分したかまで君に話す義務がある?」
「いいえ、それは結構よ。ただそこからもう一つの疑問が派生することになる。あなたが携帯を持ち去らなければならない必要性についてよ。先の説明を聞いたところ、あなたの犯行手順に先生の携帯電話は絡んでこない。そこに犯人を特定する手掛かりは残っていないはずだし、現場から早く立ち去りたかったならなおさら無視してもよかったように思うのだけれど」
しまった――鎌をかけられたか?
ただ証拠がない以上、ここは何とでも言えるところだ。慌てる必要はない。
「そこは説明では省いたとこなんだけど……息を引き取る直前、実は灘瀬先生、携帯電話に手を伸ばしたんだ。適当な番号をプッシュされて――もちろん繫がりはしなかったんだけど――発信履歴にそれが残っちゃったんだ。犯行時刻が分かっちゃ具合が悪い。履歴を消す云々するより確実ってことで結局持ち去ったというわけさ」
「……よく動く口ね。これを見てもまだ理屈をこねられるかしら」
そう言ってりり子が溜め息と共に取り出したのはなんと一台の携帯電話だった。
ブルーの折り畳み。見慣れたりり子自身のものではもちろんない。彼女の所有している携帯よりずっと古い機種だった。
嫌な予感がした。
りり子がゆっくりと本体を裏返し、そこにあるものを僕の目が捉えた時、僕は足元の床ががらがらと崩れ落ちていくような感覚に襲われた。
電池蓋の隅の方には『灘瀬』と記された名前シールが貼り付けてあったのだ。
りり子は一度僕から目を離し、取り残されそうになっていた聞き手たちに呼び掛けた。
「手掛かりを蔵匿していたことを謝罪します。私は本棚の向かいに位置する教員デスク、その下の隅の方で灘瀬先生の携帯電話を発見していました。ただもう電源もつかなくなっているようなので犯人に鎌をかける手段としてとっておいたんです」そして再び僕の方に向き直る。「それがこんな使い方をすることになるなんて……中村君が処分したと言った携帯がなぜ現場に転がっていたのかしら。こんなところで噓をつく必要はないわよね」
言葉が出てこない。渇ききった喉をひゅーひゅーと空気が行き来するばかりだった。
「これが示す真相は一つ。中村君は犯人ではない。そしてそれにもかかわらず、自分が犯人のふりをして真犯人を庇おうとしていたということ。おそらく中村君は現場に携帯がないのなら犯人が持ち去ったのだと考えたのでしょう。しかし犯人はそうしておらず私が先に回収していた。さっきも言った通り電源はつかないみたいだけど、ここからデータを引き出すことができれば決定的な証拠が残っているかもしれない。これでもまだしらばっくれるつもりかしら。正体が分かってもいない犯人の肩を持つなんて有り得ない。中村君は犯人が分かっているんでしょう?」
やられた。
完全なる敗北だった。
僕が築き上げた虚構の推理もここまで。
紛うことのない紛い物の探偵。
繕うべくもない作り物の犯人。
偽るまでもない偽物の結末。
全ては完膚なきまでに崩壊した。
『名探偵』が物語を集結させるために現出したのなら、もう他の登場人物に勝ち目はない。
「……ちょっと待って! どういうこと……? 分かんない……分かんないよ……りりちゃん! あき君っ!」
千鶴が堪えかねて声を上げた。
それは僕とりり子を除く全員の代弁であり、嘆願でもあった。
りり子は千鶴に向かって頷いて見せると、咳払いをして姿勢を正した。一呼吸おいて口を開いた時、既に彼女は中学時代の『名探偵』の風格を取り戻していた。
「つまりこういうこと。もともと茶番だとは思っていたけれど、中村君がこの戯曲――偽曲ともいえるのかしら――の狂言回しを務めていた。私たちは途中から彼の誘導にまんまと乗せられていたの。未だ虚構の檻に囚われたままの皆さんを論理の糸で救い上げられるのはおそらくこの場で私だけでしょう。一度探偵を放棄した私がこの役割を務めるのは僭越ではありますが……仕方ありません。
よろしいですか? 今から私が真犯人を告発します」
21 『名探偵』の復権(鋸りり子の告発)
僕は彼女の告白のことを思い出していた。
それが愛の告白であればどれだけよかっただろう。
しかしそれは自らの罪の告白だったのだ。
「――灘瀬先生刺しちゃった」
そんなことがあるわけないと思った。
それでもと思って社会科研究室を覗いた僕の目に飛び込んできたのは、紛れもない無残な灘瀬の死体なのだった。
突き付けられた現実。
到底信じられなかったけれど、信じざるを得なかった。
そこで僕が咄嗟にしたことは、手元にあった鍵のタグを思い出し、その部屋の扉の鍵穴に恐る恐る差し込むことだった。
かちりと嵌まり施錠がなされる。
その時、思った。
これは神様が与えてくれたチャンスだ。
考えろ。上手くやればあの人から容疑を逸らすことだって可能じゃないか。
最終的に僕が罪を被ることになっても構わない。
それにしても手抜かりなくやらなければならないが……。
さあ、彼女を救うために、考えろ、考えろ、考えろ――。
「これが……本当の解決編なんだな?」
会長がりり子に問い掛ける言葉で僕の意識は呼び戻された。
会長は状況を吞み込みつつあるようだったが、未だ僕の構築したミステリ的世界に束縛されているのも確かだった。
「ええ、これが最後ですよ。さっさと終わらせてしまおうと思います。真犯人の名から早々に明かしていきましょう。私はもったいぶったような話し方をする探偵が一番嫌いなので」
りり子はここで言葉を区切って僕の方を一瞥したが、完全無欠の探偵の表情はその瞬間だけ深い憐憫の情を内包したように見えた。
「灘瀬先生を殺した犯人、それは――葉桜仮名先輩です」
「なんだって!?」「葉桜先輩!?」
線太郎と千鶴が同時に驚嘆の声を漏らした。
「会長と副会長もご存じの人物かと思います」
りり子は言い、二人が頷いたのを確認してから続けた。
「そう、真犯人は彼女だったのです。先ほども述べましたが中村君は犯人を知る機会を得ただけなのでした。しかしその人物が彼にとって自分が罪を被ってでも守りたい大切な人であり、さらに中村君にはその時偶然、事件を隠蔽する手段も持ち合わせてしまっていたのです。おそらく鍵のトリックは実際に行った通りに説明したのだと推測します。
ただ意図的に濡れ衣を着るというのは口で言うほど簡単なことではありません。いくら自分が犯人だと大騒ぎしたって、様々な証言、現場の状況、そういったこと全てに辻褄が合っていなければならないのです。
ここでの推理ゲームはその時間稼ぎだった。
現場の検分、他の容疑者のアリバイ……すぐに警察に捜査を要求したら得られないような情報を中村君はこの推理ゲームを通じて獲得した。そしてそれらを基に自分を犯人に仕立て上げる算段を練っていったのです。
事実、この推理ゲームは会長の通報保留提案と千鶴の疑惑が発端になったにせよ、それに乗じて話を膨らまし、擬似論理で条件を囲い込んでいったのは思い返してみるとほとんど中村君でした。私たちは誤った前提条件に踊らされていたのです」
「あの……」
ここで金牛事務員が躊躇いがちに言葉を発した。「どうぞ」とりり子が促す。
「赴任して日の浅い僕にはハザクラカナさんがどんな方かいまいち判然としないんですが……まあそれはそれとして仰ることは理解できました。自白した犯人が犯人で有り得ないとなったら、それは真犯人を庇っている以外にない。なるほどですね。しかし、不可解な点がまだ多すぎます。大きな所を二つ挙げさせてもらうなら――、
一点目、ハザクラさんが真犯人であることを示す根拠はあるのか。話の流れ的にハザクラさんは中村君の……えーと、想い人のようですが、それだけで真犯人をハザクラさんと決め付けているのなら暴論じゃないでしょうか。中村君が庇い得る相手は他にいるかもしれません。犯人がハザクラさんでなければならないきちんとした証拠が示されるまでは納得できませんよ。
二点目、真犯人はなぜ階段にいた女の子たちの証言を逃れたのか。いくら中村君がこの事件における論理の道筋の大部分を構築した張本人とはいえ、死亡推定時刻と新館四階への侵入経路が東側階段しかなかったという事実は動かせないでしょう。容疑の輪の外から名前が挙がった以上、ここを説明してもらわないわけにはいきません」
りり子は金牛事務員に向かって大きく頷いた。
「二点共もっともな疑問です、金牛さん。もちろん一点目として挙げられた葉桜先輩が犯人である根拠は、これから私の思考の過程をなぞって逐次提示していきます。さわりだけ言わせてもらえば、実は私は皆さんより早い段階で皆さんの得ていないような情報を得る機会があったのです。故に私は事件の発端からずっと葉桜先輩に嫌疑を向けていました。『葉桜仮名が犯人である』という仮定を置いた上で、今までずっとその証拠を集めていたといってもいいくらいです。まるで中村君が犯人でないことが分かってから、芋蔓式に葉桜さんという真犯人に辿り着いたような印象を受けるかもしれませんが、中村君が犯人でなかったことも並列に収集してきた証拠の一つでしかないのです。私は証拠が十二分に出揃うタイミングを待って、初めて自身の考えを開陳したに過ぎないのです。
二点目の疑問も既に解を発見しています。そして同時に私の説を固める論拠にもしているのですが……追って話していくことにしましょう」
一呼吸置いたりり子の目には、遠く山際に下り始めた夜の帳と似た光が宿っていて。探偵は優雅な所作で論理を手繰り、推理を紡ぎ、そして真実を描き出していった。
「最初に葉桜先輩に疑問を覚えたのはドリンクコーナーでした。私は二時頃に一度一階に下り、自販機前で中村君と、そして葉桜先輩と鉢合わせたと先ほどもお話ししました。そこで一つ大きな違和感を覚える出来事があったのです。葉桜先輩はその時コーヒーを買って飲んでいたのですが、それはあのうだるような炎天下にもかかわらずホットだったのです」
「え……?」
それが自分の口から発せられた疑問だということを、一拍遅れて認識する。
いまいち話を捉えきれていない周囲の人々とは対照的に、僕は大きなショックを受けていた。
あのコーヒーがホットだったって?
改めて記憶の糸を繰り寄せる。確かに彼女はコーヒーの缶を捨てた直後の手を僕の頰まで伸ばした。
けれどその手は温かく、すべすべとして、さらさらとして、水気が全くなかったことをはっきりと思い出した。
僕の持っていた冷たい飲み物の缶はびしょびしょになるほど結露していたというのに。
「あの気温の中で温かい飲み物を飲むということは、彼女が寒さを感じていた証拠です。では、それはなぜか? 冷たいものを食べたのでしょうか? あの暑さです。少しくらいじゃどうってことありません。風邪気味だったのでしょうか? 彼女は半袖のシャツを着用して登校してきていました。ですからこれも考えにくいですよね。しかし夏場、皆さんも体験したことがあるはずです――冷房の効き過ぎた部屋で凍えそうになることが。
現在、この学校内で冷房が作動する部屋はパソコン室、職員室、社会科研究室のみです。パソコン室は中村君と山手君がいましたし、職員室は少し前に私が覗いた時、冷房の効き目を実感できないほどにごった返す人の熱気でいっぱいでした。単純な消去法です。ドリンクコーナーに来る直前の時間、葉桜先輩は社会科研究室にいた。私はその時点でそう推測していたのです。これは〈前提〉の犯行時刻とも一致します」
りり子は既に録音されたものを再生していくかのように続けた。
「次に中村君の推理の中では誤魔化して片付けられていたダイイング・メッセージですが、あれは確かに灘瀬先生が書き遺したものだったのです。
私は研究室捜査組でしたが、最初あの大きさにまず違和感を覚えました。円のような図形の直径は二十センチを優に超えていたでしょう。何か文字や記号を示す物なら少々大き過ぎると思いませんか。
それに灘瀬先生が手をいっぱいに伸ばして描いているのも不自然です。犯人の名前等を記したかったら、もっと自分の手近で描けばいいはずです。なのにそうしなかったのは、その地点にあるものを示したかったからに他なりません。例えば衣類のボタンを落としていった犯人を示すダイイング・メッセージを遺そうと、被害者がそのボタンをぐっとつかんでいたという事例があります。こんな風に犯人の遺した痕跡を示すものと考えたらどうでしょう。しかし灘瀬先生があれを記したということは、それは自分の手で握ったり捕えたりできないものだったということが分かります。しかもあの大きさで、です。
……私には思い当たるものがあったので、灘瀬先生と同じ視点になるようにぐっと目線を下げて、記された円の内側の床を見てみました。そうしたらうっすらとですが発見できたんです。最も古典的な痕跡の王様――足跡らしきものを。摩擦でゴム底が焼けて残ったと思われるものでした。灘瀬先生はこれが犯人を示す手掛かりになると考えた」
「ちょっと待って」線太郎の手が挙がった。「学校って大概指定の上履きがあるから、生徒はみんなそのおんなじやつ履いてるはずでしょ。鷹松学園に至っては教師や事務員も揃いの上履きを履いてるくらいだ。なんで灘瀬先生は同種のものが多数存在して、サイズくらいでしか犯人像を絞り込めなさそうなものを一生懸命遺そうと……」
しかし線太郎が懸念した意見は、その半ばで会長にかき消された。
「あっ! そうか……違うんだ、彼女の場合は!」
「さすがの観察眼ですね」りり子が頷く。「そうです、葉桜先輩は学校指定ではない、別の特徴的な上履きを履いているんですよ。足跡自体はかなり薄くて照合まで持っていけるか分からないほどですが、これは被害者が『足跡が証拠になり得る』と考えた証拠にはなりますよね。
本日、校外から来ている人には、スリッパの着用を義務付けています。鷹松学園は教員諸氏にも指定の上履きが支給されますから、この要件はかなり犯人の範囲を絞り込みます。私の論理を固く固く補強するのです」
研究室を検分している時に、ダイイング・メッセージを仔細に観察しているりり子を見た時は冷や汗ものだったけれど……やはり見抜いていたか。
ダイイング・メッセージの真意については、実は僕も気付いていた。ゴム底の跡は拭って消えるようなものじゃない。いっそメッセージ自体を拭ってしまおうとも考えたけれど、あまりにリスクが高かった。これを踏まえた上で都合よく自分だけを示唆する強力なメッセージを構築できなかったのは僕の力不足だ。
しかしここまで決定的なものでない以上、ダイイング・メッセージなんて解釈や深読みの余地があり過ぎて、普通は犯人特定の定理にまではなり得ない。これも今回は運が悪かった。
「では、次の立論ですが、ここが皆さんの最大の謎にもなっていると思います。なぜ犯人は階段口にいた女バスの先輩方の証言を逃れたのか、ということに言及していきますね」
聴衆が一際、耳をそばだてる気配があった。確かにここが最も不可解な部分だといっていい。トリックがあるのならそれはどんなものか――そしてそれがどうやって仮名先輩に繫がるのか。
この透・深月両先輩の証言は、容疑者の枠を狭める非常に大きな論拠になっていた。僕は元から犯人が仮名先輩だと知っていたから、彼女たちから当然その名前が出てくるものだと思っていた。むしろそう覚悟した上で負け戦でも何でも死に物狂いで挑むつもりでいたのだ。しかし結果として彼女らは仮名先輩の名前を出さず、僕は虚構の推理の中で仮名先輩を容疑者リストの外に確保することができた。その幸運に感謝はしたものの、僕自身それに明確な結論を導き出せていなかったのだ。
たださすがというべきか、りり子は辿り着いたのだ。
それは紛れもない『名探偵』の復権だった。
「順に検討し直したいと思います。まず犯人と階段口の先輩方との共犯関係の有無に係る命題。この事件は突発的な犯行でした。よって事前の共犯は、偽。また、事後の共犯は犯人が階段口で自分の犯行を打ち明け、衆人環視の中、彼女らと共犯の算段を練らなければなりません。これは非常にリスクが高い。階段口の先輩方の側が偶発的に犯行があったことを知ることも不可能。よって、偽とされました。中村君は先ほどこのように理論を組み立てましたが、なるほど、キモの部分であるだけにさすがにしっかりしています。シンプルで突き崩せません。よってこれは前提通りでしょう。犯人と女バスの先輩方との間に共犯関係はなかった。
しかし大事なのは『犯人と先輩方との間に共犯関係がない』ということと『先輩方は噓の証言、偽りの証言をしていない』ということは、必ずしもイコールで結べないということです」
「……どういうことだ?」
周りの雰囲気を代弁することになったのは僕だった。
りり子は一瞬こちらを見やった後、ふっと視線を軽く上方に向けた。言い換えの言葉を探すような仕草。それもほんの短い間ではあったが。
「噓の証言、偽りの証言というのは必ずしも共犯関係によって発現するわけではないのです。つまり、この事件とはまったく無関係の要因によって個人的に名前が出されなかった可能性が有り得るということです。……中々ぴんと来ないようですね。犯人には、共犯以外の目的で東側階段を通っていたのに通っていないことにされる理由があった、ということになるのですが。いるのにいないと偽られる、存在しないとみなされる状況――思い当たりませんか。
そうですね、ではもっと直接的にいきましょう――シカト、なんていう行為がそこにあったとするなら、どうでしょうか」
時が止まった気がした。
りり子の言葉の残響が脳でわんわんとこだましている。
なんだって?
自分の体をかき抱く千鶴の姿が視界の端に引っ掛かった。
線太郎の歯ぎしりが低く鳴った。
なんだって?
会長が露骨に顔をしかめ、「……ふざけてる」と苦く言い放つのが、どこか遠くの方から聞こえた。
次いで副会長が静かに目を伏せて。
支えを失ったかのように金牛事務員が椅子に沈む。
なんだって?
僕の頭の中の無数の疑問符は、続くりり子の演説で一つ一つ残酷に解き明かされていった。
「決して気分のいい話ではありませんが……探偵を自らもって任じた以上、仕方ありません。葉桜先輩が女バスの二年生の方々にシカトされなければならなかった理由、それに踏み込んでいきましょう。
葉桜先輩は現在、特定の班活に所属してはいません。しかし二年生になる直前まで、彼女は女子バスケットボール班に在籍していたのです。私はこれを前年度発行の生徒会月報で知りました。その号では大々的な女バスの特集が組まれていたのですが、その中にはまだ彼女の名前があったのです。しかし彼女は現在、女バスを辞めてしまっている。この一年の間、彼女の身に一体何があったのか――。
それに関して私は決定的なものをつかむには至りませんでした。なのでこれは断片的な情報をより合わせ、噂や憶測といったものを総合的に勘案した結果に過ぎませんが――その裏には上級生からの執拗な嫌がらせがあったのではないでしょうか。元来女バスには、華々しい実績を打ち立てていく過程で、過剰な上下関係や精神論といったものを容認する風土が出来上がってしまっていたように思います。練習が厳しいことは前々から知られていましたが、それは次第に純粋な指導やしごきといった範疇を超え、いじめ染みたものに向かったのかもしれません。
とにかく事実として、彼女は前年度の終わりにようやく退班したと聞きます」
僕は開いた口が塞がらなかった。
仮名先輩は高校でもしばらくはバスケを続けていた――。
僕がバスケ班見学で仮名先輩の姿を見かけなかったのは、つまり彼女がもう辞めた後だったからで――と、そんなことはさして重要ではない。
いじめみたいな行為が、そこに介在していた、だって?
それはどうなんだ? さすがに想像力をたくましくし過ぎなのではないか――。
――いや、待て。
思い当たることは、幾つもあるじゃないか。
仮名先輩のお母さんは、先輩が部活で体中に痣を作って帰ってきたと話した。
また、仮名先輩は、一年強で上履きがもう三足目になると漏らした。
接触プレーがあるにはあるが、極力それらを避けるようにルールが作られているバスケットボールで、体中に痣ができるなんてやっぱり尋常じゃない。それに、上履きを替えるペースだって明らかにおかしい。普通に履いてるだけなら、だめになるのが早過ぎるじゃないか。
それはつまり――そういうことだったのだ。
「――続けます」とりり子。「女バスを退班したことにより、葉桜先輩は上級生からの直接的な危害からは逃れることができたかもしれません。しかし閉鎖的で排他的なコミュニティは報復の手段を別の方向にシフトしたに過ぎなかったのではないでしょうか。例えばこんな論法が出てきたと考えるのは想像に難くありません。
『葉桜仮名は女バスと関係を絶った、であるならば、女バスも葉桜仮名と関係を絶つべきだ――あいつと関わるのはやめよう、金輪際、徹底的に無視してやろう』
そして上級生の打ち出したその方針が、葉桜先輩と苦楽を共にしてきたかつての仲間――つまり彼女と同学年の現在二年生の班員たちにも強制されたとしたら……」
そういえば――仮名先輩が親しげに呼び掛けた声が届かなかったことがあった。それは十分過ぎる声量だったにもかかわらず、相手は見向きもしないどころか廊下の角に逃げるようにして消えた。それはつまりわざと聞き流されたのだ。先輩はあの時「みっちゃん」と呼び掛けた。彼女が誰だったのかも今ならわかる。みっちゃん――それは深月先輩だったのだ。そして彼女は今回、階段にいた二人組の片割れでもある。
「私はそれが今回の謎を生んだ根源だったと推測します。階段にいた女バスの先輩方には、葉桜先輩をいない者として扱うしばりがあった、だから証言も自然とそのルールに則る形になった――と」
「……そんな馬鹿な……」金牛事務員の口から可聴域ぎりぎりの呟きが漏れた。「僕たちはある特定の生徒を存在しないものとするゲームに巻き込まれてたっていうのか……」
否定できるものなら否定したかった。しかし僕の脳裏にはりり子の推理を裏書きする記憶が鮮明に浮かび上がってきていて。
女バスの班室に貼られていた無数の写真――あのどれにも仮名先輩は写っていなかった。写っていればその時、僕は先輩が女バスに属していたことを知ったはずだ。一年間一緒に活動していたはずなのに、彼女らにとって先輩は存在しないも同然の扱いをされていたのだ。
そしてもう一つ、頭をよぎったこと。それは鋸家の蔵の中で聞いた、りり子と叔母の話。
――さしずめ私は『見えない女』かしら。
到底信じられなかったけれど、それは現実だった。そういった現象が実際に起こり得ることも、僕は知っていたのだ。
僕は無意識のうちに体を折り曲げるようにして頭を抱えていた。
身近でこんなに残酷なことが起こっていたという事実の恐ろしさに体が震えていた。
いや、この震えの原因はそれだけじゃない――。
こんなにもたくさんの示唆が転がっていたというのに――僕は何も気付けなかった。
仮名先輩のことが好きだった。大好きだった。
でも所詮、そうと喚くばかりで、彼女の何も見えちゃいなかったんだ。
その深いところに分け入っていこうとは、一切していなかったのだ。
何が探偵だ。
何が彼女を救うだ。
自分の愚かさに腹わたが煮えくり返りそうだった。
でも――もう、何もかも、手遅れだった。
祭りの後の、後の祭り――。
「――私が葉桜仮名先輩を犯人だと指摘する理由、根拠は以上です」
『名探偵』は静かに、ただただ恬淡と物語をコーダへ導いた。『劇終』という文字が目前にでかでかと現れようものなら、あるいは緞帳が荘厳に下りてこようものなら、この場は万雷の拍手で満たされただろう。しかしこれは紛れもない現実だった。悲劇の後も物語は続く。その後の物語は、きっと悲劇そのものより悲劇的だ。
「なぜ……葉桜さんは人一人を殺めるなんて極限に至ってしまったんでしょうか。灘瀬先生は件のいじめとは関係なさそうですが……その動機は……」
副会長が自失しながら尋ねた。その言葉を千鶴が受ける。
「あれかな……灘瀬先生が仮名先輩を研究室に連れ込んで、よからぬことをしようとしたのかも。灘瀬先生にはセクハラ疑惑もあったし……」
しかしりり子は静かに首を横に振って答えた。
「彼女の動機の解明までは現在要請されていないはずです。私たちが今すべきこと、それはこの私的裁判及び探偵ゲームの一刻も早い閉幕と――警察への通報です」
りり子が言い終えたその瞬間、音楽室にも閃光とやや遅れる形となって、グランドフィナーレの花火の音が響いた。
それはまるで閉じゆく鷹松祭と日常の、断末魔のようでもあった。
22 顚末
あの後すぐに会長の携帯から一一○番へと通報がなされた。文化祭のフィナーレは訪れていたし、そうでなくても真犯人は容疑者の囲い込みの外に存在したのだ。これ以上通報を遅らせる理由はなかった。
警察の捜査はその日の夜から早速開始され、当惑する生徒たちと野次馬のおかげで鷹松学園は一時騒然となった。優秀な捜査官らは数日の間に些少な痕跡の幾つかをどこからともなく嗅ぎ出した。そしてそれらは全て微弱ながらも、しかし確実に葉桜仮名が犯人であることを示していた。そこから厳しく警察に追及された仮名先輩はほどなくして自身の罪を認めている。
仮名先輩本人の証言から動機に関わる部分が明らかになった。仮名先輩は以前から、灘瀬に対して猛烈なアプローチを行っていたらしい。灘瀬はというと、真しやかに語られていたセクハラ疑惑とは全く無縁であり、それどころか仮名先輩から激しく好意を寄せられていたものの、頑なに関係を拒むほど潔癖な男であったという。しかし彼は虚を衝かれ、仮名先輩に二人の関係性について誤解を招くような写真を撮影された。最近の彼女はそれをちらつかせながらほとんど脅迫じみた勢いで交際を迫っていたんだとか。動機は彼女の愛情のもつれだと見られた。
仮名先輩がメールで僕に言っていた『好きな人』というのはつまり『灘瀬朝臣』だったわけだ。
ショックはショックだった。けれど、僕はこのことに関しては薄々感づいていたのだった。
最初に違和感を覚えたのは〈やまつみ〉暗号メール事件の次の日。わざわざ直接前日のお礼を言いに来てくれた先輩は、しかし僕が振った『TPIQ』のセールの話題になぜか少し当惑するような反応をしていた。
――彼女はその前日、本当に『TPIQ』にいたのだろうか。
そんな小さな小さな懐疑が、その後も事あるごとに僕の心に積み重なっていった。自分の恋が実らない漠然とした予感みたいなものは、そうして徐々に明確な形を持ったものに変わっていったのだ。
先輩がメールで言っていた、好きな人の名前の中に隠れる『季節』の謎も、少し考えたらすぐに解くことができた。
NADASE ASON――NADASEASON
まったく紛らわしい……。
結局、僕がしていたのはぬか喜びもいいところだったわけだ。
まあ仮名先輩はああいう人だから僕を勘違いさせてほくそ笑んでいたわけでもないだろうし、可愛い後輩として僕のことは気に入ってくれていたんだろう。
他でもない、この僕に自らの罪を告白してくれたのだから。
特別な懺悔の相手に、僕を選んでくれたのだから。
――いや、もしかして……。
もしかして、先輩は全て計算した上で、僕に――。
ま、待て待て、そんなはずないじゃないか。優しくて、可愛くて、ちょっと抜けてる先輩に限ってそんなこと――人の好意を逆手に取るようなこと――あるはずない。
事件の後、未だ先輩とは会えていないけれど。
もし会って話せたとしても、彼女の本当の気持ちなんて、おそらく絶対に知りようがないけれど。
それでも――それでも自分が罪を被ることが好きな女性のためになると思い込んだみたいに、僕はこれからもそうやって思い込んでいくしかなかった。
女バスでいじめが行われていたことも匿名生徒のリークによって表沙汰になった。まもなく仮名先輩と女バス班員の双方の証言があり、事実であることも立証されてしまった。
いじめの主犯はりり子の語った通り、今の三年生の先輩らだった。顧問が校訓の『自主自律の確立』を履き違え、それにあぐらをかいている間に、女バスでは上級生の権力が異常に強くなってしまっていたのだ。歯向かったら余計にしごかれるかもしれない、いじめのターゲットが自分に切り替わるかもしれない、そういった恐怖が班員の間に蔓延し、誰も逆らうことができず、仮名先輩がスケープゴートにされてしまったというわけだ。
そんな背景を考えると、女バス班室写真消失事件で恩先輩が写真を持ち去り、呪おうとした相手も一年生ではなく、元凶の三年生だったと考えるのが妥当かもしれない。新入生歓迎会の写真に写っているのが一年生だけとは限らないし、恩先輩の目下の関心は健全なレギュラー争いより、三年生の脅威からいかにして逃れるかにあったに違いない。
ただ仮名先輩自身はこのいじめと殺人事件の間の因果関係については、全くといっていいほど語らなかった。
とはいえマスメディアにとってこれは絶好の餌なわけで、この部分はやたらとセンセーショナルに取り上げられることとなる。ワイドショーでは連日連夜、教育専門家だのコメンテーターだのがこぞって無茶苦茶な議論を戦わせていた。いじめられた経験が少女を教師との恋愛に駆り立てたんだとか、これこそ傷害衝動の遠因になったに違いないとか、そもそも名門校という体質が教育病理の根っこなのだとか、云々。
滑稽な探偵はそこら中にいるんだな、と思う。
しかし考えてみれば、滑稽な彼らと滑稽な僕との間に一体どんな相違があるというのだろう。
そこにない事件をでっち上げたかと思えば、今度はそこにあるあからさまな事件を見落としている――。
僕がしてきたことは、こいつらのやってることとどこが違うっていうんだ?
――違うさ、何もかも。
テレビを消して、これに関しても僕はそうやって思い込むしかなかった。
僕に対してなされた処遇について話そうと思う。
しかし実を言うと、なされた処遇も何も、公権力によるなんらの罰も僕は受けていない。ただただ以前と変わらない生活を送ってしまっているのだ。明らかな犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪を犯していながらである。
――推理ゲームはなかったことにしよう。
通報直後、僕は警察にそう供述すべきだと居合わせたメンバーに提案した。それは僕以外のみんなを制裁に巻き込むわけにはいかないと思ったからだ。僕が彼らを殺人を玩弄する遊びへといざなったわけで、彼らはある種被害者の側なのである。罪を負うのは僕だけでよく、そして僕だけは断固として罪を負わなければならなかった。
しかし通報を遅らせた、推理合戦に賛成した、という時点で自分たちも同罪だと、彼らは警察の尋問に僕の不利になる証言はしなかったらしい。ただちゃっかり僕が仮名先輩に思いを寄せていたことはしっかり供述していたため、僕が正直に自分の罪を白状しても想い人の殺人に動転した哀れな少年と思われるだけで全く相手にされなかった。
現場の密室について言及しても警察関係者は首を傾げるばかりだった。社会科研究室への施錠や、その場所及びマスターキーに僕がこっそり遺してきていた指紋など、僕の犯行を裏付ける証拠はあのメンバーの内の誰かしらによって、いつの間にか隠滅されてしまっていたらしい。結局、僕も他のメンバーと同じように少しキツめに取り調べを受けた程度で同日中に釈放されることとなった。
そして、鷹松学園は、混乱を収拾するために一週間ほどの臨時休校を設けた。
23 探偵の動機
「あんな事件の後――しかも僕は罪を問われてもおかしくない立場だってのに――こうしてのうのうと娑婆で平穏な日々を過ごしているなんてね。クラスメイトの女の子の家に上がり込んだりしてるし」
「あなたにも災難だったと思うのよ。あんな失恋ないわ」
「珍しい。同情してくれるの?」
「あの犯人探偵説は同情できないほど酷かったけれど……探偵を辞めた私なら茶々を入れないと思ったのかしら」
「まあね。こうして美味しいお茶は淹れてくれるけど」
「………………」
七月五日。水曜日。
臨時休校を利用する形で僕は鋸邸へ二度目の来訪を果たしていた。
体よく言ってみたが、ようは自分から押し掛けたのだ。
蔵から脱出したあの日に案内されたのと同じ客間で、今回もお茶を供してもらっている。推理合戦はまだほんの三日前の出来事だ。しかしもう遠い昔に起きた事件のような印象がある。
気を取り直してという風に咳払いをした後、りり子は話を続けた。
「杜撰にもほどがある詭弁だったわ。異様な雰囲気に乗じて押し切ったつもりだったかもしれないけれど、あれじゃ他のメンバーが矛盾に気付くのも時間の問題だったわよ。それに携帯ね。あんなのでボロを出しちゃうなんて」
「まさか思いもしなかったよ。りり子が灘瀬の携帯だって出してきたものが、実は自分の携帯に『灘瀬』って書かれた名前シールを貼っただけのものだったなんて。あれ、いつものりり子の携帯じゃなかったし」
「灘瀬先生の携帯って確かグレーの最新型だったと思うわ。でもあなたはその特徴を知らなかった。これは他のメンバーにも言えることだけど……私がわざと灘瀬先生の携帯の特徴として、自分の持っている携帯の特徴を言っても訂正がなかったもの。見覚えがなかったのも当たり前。私はたまたま携帯を前日修理に出していて、あれは代替機だったから。あとは私が研究室の教員デスクの下で見つけた名前シールをそこに貼っただけ。灘瀬先生の持ち物のいずれかから剝がれ落ちたのね。名前シールなら筆跡が問題にならないとはいえ、もうちょっと粘ってくるかと思ったんだけれど」
「すっかり騙されたよ。ただそこで崩されるまでの論理の組み立てには自信があったんだけどな。少なくとも押せ押せでなんとかなると思った。君も結局、僕が犯人探偵説を発表するまで、そこを端緒に切り崩すまでは、傍観の姿勢を貫くしかなかったみたいだし。瑕疵に気付いたところで筋道立てて別の犯人を指摘できなきゃ、詭弁とはいえ僕の理論を覆すこともできない。逃げ切る形で僕の勝ち――って寸法だったのに。君に阻止されちゃったってわけ」
「……本題は何? お茶を飲みに来たわけじゃないんでしょう。まさか引かれ者の小唄を延々聞かされるのかしら」
「単に負け惜しみ言いにここに来たわけじゃないよ。あえて言うならそうだな……僕の敗因の核心を知るため、かな。あの事件でりり子が真相に到達することは分かってた。前提にしてたって言ってもいい。ただそこからが完全に僕の想定外だったわけで――つまり君がそれをあの場で口にしたことだ。僕の敗因は結局、その読み違いの一点にのみ帰着する。
だってあそこで真犯人を告発することは、君がもう一度探偵になることと同義だ。君には探偵を辞めた理由がある。探偵を再開する理由ができたとしたら、後者は前者を凌駕する強力なパラダイムシフトだ。自分の命が危うい、みたいな切迫した状況でもなし、こう言っては亡くなった灘瀬に失礼だけど、この事件にりり子の衝動を突き動かすほどの要因があったとは思えない。なぜ、君はあの時、再び『名探偵』と成ったのか。その動機が知りたいと思った」
りり子は黙ったまま。僕はお茶で唇を湿らせて付け加える。
「僕が納得してあの状況を受け入れていた以上、真犯人を暴き、真相を明かすことにどれだけの意義があっただろう。国家機関が僕を犯人と認めればそれが揺るぎない真実になるわけだし、そうならなかったらそれまでということ。それが君の望む世界、探偵のない世界のあるべき姿だったんじゃないかな」
数瞬、二人は黙って見つめ合った。字面ほどロマンチックなものではなかったけれど。
ほどなくしてりり子は居住まいを正して受け答える。
「……あなたがえせ探偵として介入している時点でその前提は既に存在しなかった」
「探偵の排除のために自らが探偵になったとしたら、それこそ本末転倒じゃないか」
僕は間髪を容れずに返して様子を見た。
「………………」
りり子は口を開いて何か言おうとしたが、言葉を発する前に静かにその口を閉じてしまう。
そして次の瞬間、なんと彼女は目を伏せたのだ。
ぶつかっていた視線が透かされる形になって僕は驚く。彼女から人と合わせた目を逸らすなんて。これは鋸りり子が見せる素振りではないはずだ。
どうなってる?
「……それにはまず、私が探偵を辞めた理由を話さなければならないわね」
その通りだった。そして僕が返答をする前にりり子は吐き出すように続けた。
「あのね、私の家族は――」
戸惑う僕に出し抜けに投げられた言葉。
「え?」
衝撃。
殴打されたわけでもないのに揺れる頭蓋。
「私の家族は――」震える声、唐突な告白。「私が殺したのよ」
驚愕の余韻は胸を去らなかったけれど。
僕が勧めたお茶を飲み干すと、りり子はだいぶ落ち着きを取り戻したようだった。
「……昔話を、させてもらってもいいかしら? あなたの問いに答えるためにも言及せざるを得ないから」
正座を少し崩しながら彼女は言った。声はもうほとんど平静の様子に戻っている。促したい僕は、しかしそこに若干の躊躇を覚えてもいて。
「つらいなら――無理強いはしないけど」
「いいえ、話させて」
「分かった」
一つ深く息を吸うりり子。そしてほどなく形の良い唇から、詠うように物語が紡がれ始める。推理を披露している時は、まるで冷徹なマシーンを連想させるようなりり子の語りも、この時ばかりは紛れもない生きた人間の温もりを内包していた。
「私には物心ついた時から論理を構築する能力があった。それは真相を手繰る才とも言い換えられるようなもので――子供心にそれが強大で、ある意味恐ろしいほどの力だと気付いていたわ。自惚れや思い込みであったらどれほどよかったか。もはや才能や資質なんて呼べるものではなかったかもしれない。そう、それは呪縛だった。
そんなだったから私はいつも一人で考えていたわ。この悪魔の力を使って、なんとか困っている人を助けられないかって。真実をつかむことで、本質を見抜くことで、家族や友達――そういう大切な人たちの糧になれないかって。それこそが原点、私が探偵を始めた原初の理由。
小学生くらいの頃から細々と事件を解決していた。噂は噂を呼んで探偵の輪はみるみる広がっていったわ。それにしても中学の頃は少し異様だったけれどね。なんというか私がもっと上手くやれていればよかったところもあるのかしら。――中学時代、私の後を継いだ、あなたみたいに」
「……気付いてたんだね」僕は目を見開く。
「今のはほとんど勘よ」
うぐ。またやられた。
「鎌かけられてばっかだな、僕……」
「ごめんなさい。でも、私だけ過去を告白するの、フェアじゃないでしょう? 続けるわ。探偵をしていると、喜んでもらえるばかりじゃないのよね、当たり前だけれど。真実は時に痛くて、煩わしくて、受け入れるのにとても苦慮したりするものだから。疎まれることもあった。蔑まれることもあった。だけど――私は自分が正しいことをしているってずっと信じてた。今は残酷な真相に戸惑っているだけでいつかみんな分かってくれる時が来るって。
そして――中学三年の時、転機が訪れた」
転機――その言葉に、いい予感はしなかった。
りり子は僕の思考を読み取ったみたいに軽く頭を振る。
「言うまでもないけれど、これは悪い方の転機ね。
当時、私の父と母は夫婦揃ってそれなりに名の通った学者だった。彼らには特に可愛がっている一人の若い女性研究員がいて、折に触れて自宅に食事に招くほどだったわ。そんなだから私も何度か彼女に会う機会があった。彼女は礼儀正しく、謙虚な態度とたおやかな微笑を決して崩さなかった。余計なことは一切話さなかった。それでも時折発せられる言葉の端々には常に超越と逸出とがあった。
ある日、父と母が海外の学会へ出掛けた時、留守を預かっていた私は両親の書斎の掃除中に、ふと研究員の女性が書いた論文を見つけたの。その内容は、門外漢の私ですら、今まで感じたことのない知的興奮に胸が高ぶるようなものだった。おそらくこのたった一本の論文で、広範な分野に先鋭的かつ独創的な新風を巻き起こしたであろうことは想像に難くなかったわ。しかし深く読み込んでいくうちに、私はさらに驚愕することになる。
論文はそれ自体に巧妙な仕掛けが施されていた――それは特殊なアルゴリズムによって構築された暗号文でもあったの。私は三日三晩ぶっ続けで解読に取り組んで、ようやくそれらが示す全容を把握することができたわ……幸か不幸かは別として、ね。
なぜなら、それは――学界における、両親の不行状を告発するものだったから」
「そんな……」
にわかには信じられなかった。
学究的な家庭と非凡なる女性研究員。
彼女の物した論文に忍ばされた暗号。
明らかになってしまった両親の不義。
これだけでも規格外に異様な彼女の物語は、しかしまだまだ終わらなかった。
「嫌疑は、他者の業績の略取から論文の剽窃、果てはそれらが表沙汰になるのを防ぐための学会連合への根回しにまで及んでいた。ご丁寧に根拠も検証も十分だったわ。
私は意を決して両親に国際電話を飛ばした。私が震える声で糾弾すると、彼らはあっさりと自分たちのしたことを認めた。強く反省と後悔の念に苛まれている様子だった。残りの予定を全てキャンセルして早急に帰国した後、自主的にしかるべき場所へ出頭する――私の説得に応じる形で、そこまでその場で約束した。
――私は正しいことをしたんだ。
通話の後、何度も何度も自分に言い聞かせた。両親が自ら世間に罪を打ち明けることで、彼らの中に小さいけれど確かな品格が残る。それは私が両親を想い、最後の一線の前で彼らを立ち止まらせ、守った――その証でもある。必死になってそう思い込もうとした。
でも次の日、その驕りは粉々に打ち砕かれることになる。両親の帰宅を待つ私に一本の電話が届いたの――両親の乗った飛行機が墜落した、と」
重く臓腑を打ち据える無慈悲な破局。
その無残な光景が、嫌でも脳内に再生されそうになる。
不運だった。ただ、ひたすらに――でも、不運は不運で、それだけだ。それ以上でも以下でもないはず。
「……君のせいじゃない」
僕の絞り出した言葉は、しかし彼女には届かなかったようで。
「研究員の女性は混乱のさなかに知らず姿を消していた――。
彼女の思惑も今となってはわからない。けれど、論文に織り込まれた暗号のレベル設定、そしてそれが示していた内容から推しても、彼女は不特定多数の人間に向けてこのメッセージを記したわけではないと思う。それは、他の誰でもない、私に向けられたものだった――今ではほとんどそう確信しているの。彼女なりの、それは対話だったのかもしれない。彼女とは、それ以前にまともに言葉を交わしたことすらなかったけれど、必要なかったのね。そうした無駄な応酬は一切なしに、一足飛びに私の本質に語りかけることができたから。
彼女は、私に謎を解くか否かを問い、私は解くと答えた。
彼女は、私に真実を語るか否かを問い、私は語ると答えた。
しかし、そうした探偵自身の介入があるべき運命を変えること、そして、その行動の責任が一生ついて回ることを、その時の私はまだ知らなかった。
結局――私は力に溺れて大切なものを失った。何も守れなかった。自分のちっぽけな自尊心以外は、何も。私が家族を殺したのよ。父も、母も……
「それは違う!」
僕は咄嗟に叫んだけれど、りり子は首を横に振ってそれを遮った。
「分かっているわ、私だって。でもね、こういうのは頭で分かっていてもだめなの。家族を失った私は親族に引き取られたけれど、そこでも白い目で見られた。幼い時分から賢しく知恵の回る私を、彼らは何だか気味悪がっていたの。腫れ物に触るような待遇だったけれど、私はそれを当然のことだと受け入れた。そして、私はもう探偵することを辞めたわ。当然よね、本来探偵することによって守らなければならなかったものを、探偵するという行為、真実を追求するという行為自体によって壊してしまったのだから。守るべき存在の喪失、それに直面した私はその手段を放棄することで自我のバランスを取ろうとした。それが彼らにとって償いになるのだと勝手に納得しようとしたのよ」
それこそりり子が――、
探偵を辞めた理由。
悲痛で卑屈な理由。
想い故の重い理由。
「その時はそれでよかった。恥ずべきことに私はその行為によって僅かばかりの安心を得たのだから……。しばらくは人とも深く関わりを持たないように生きてきた。そもそも探偵の頃からの癖で誰かと馴れ合うのって苦手だったんだけれど。
それでもこの鷹松学園に来て、こんな私にも守りたいと思えるほど大切な人ができた。彼――そう、彼と一緒にいられる時間は楽しかった。こんな時間がずっと続けばいいと思うくらいに。
なのにね。彼は自分を犠牲にして無茶苦茶な選択をしようとした。道を踏み外しそうになる彼のために、私は空っぽの自分の心の中を闇雲に漁った。そして思い知ったの。その底に残っていたもの、大切な人を守るために私にできること……それは、畢竟探偵することしかなかったのよ」
僕は押し黙ったまま、一言も聞き漏らすまいとりり子の言葉を受け止める。
「その時は正直打ちひしがれたような気持ちもあった。とはいえ、それって――今はそんなに悪いことじゃないかもしれないって思えるの。それが過去を乗り越えるってことなのかもしれないって。
家族を失った悲しみが風化したわけじゃない。もちろん開き直りなんかでもない。だけど探偵することで今まで確かに救えたものだってあったはず。探偵を辞めることは自分で自分が間違いだったことを認めることになる。だったら私はまだやれる。自分が正しかったって証明できる。これから私が探偵することによって、真実を追い求めることによって、自分が大切に想うものを守っていけるのなら、それがその証明になる。
今回の事件では彼自身も、彼の考える方法で、彼の大切に想う人を守ろうとしていた。それは分かってた。でもだからこそほうっておけなかった。彼がしていることは自分自身と自分の大切に想う人、両方を貶める行為だと思ったから。私が真実を提示することは、彼の思惑を打ち砕くことになってしまう。けれど、それで結果的に自分が憎まれたりしても私はもう大丈夫って思った。……素直に言うと、それはやっぱり少しは悲しいけれど、一時の安息のために虚構を構築してもそれは『本当』でない以上、絶対に後から無理が出る。歪みが生じる。だから彼と彼の大切な人とのこれからを思う意味でも、こうすることが一番良いと思った」
伏し目がちだった目を上目遣いにこちらに向けようとするりり子。
「長々と話させてもらったけど、つまりはそういうこと。再び私があの場で探偵と成った理由、それは――私が大切に想う、彼を守るため」
彼女が言い終えた瞬間、二人の間に柔らかな風が吹き抜けた。
縁側に面した襖が開け放たれていたからだろうか。
それはまるで、一つの物語を締めくくるかのようだった。
「そっか――」僕は短い沈黙と逡巡の後、答えた。「ありがとう、りり子。洗いざらい話してくれて――とても、つらかったはずなのに」
「ううん、いいの。私も話したい、吐き出したいと思っていたことだったから」
「大切に想ってる誰かのために、誰かが大切に想ってくれてるかもしれない自分が犠牲になるって考え方は――やっぱり自分本位に過ぎるのかもしれない」
自分に言い聞かせるように呟いてみた。
鋸りり子が真実を追い、探偵として語り続けてきたならば。
僕はいわば真実から逃げ、探偵を騙り続けてきた。
――エゴイズムとナルシシズムの権化。
そうだ、それが、きっと僕だ。
それでも。
りり子の裁きは、一方では赦しであってくれたから――。
「その彼もきっと」と僕。「りり子を憎んだりなんかしてないよ。真実の提示は結果的に彼に大切なことを気付かせてくれたはずだ。僕が保証する」
「そんな風に言ってもらえると……私も嬉しい。探偵冥利に尽きるわ」
りり子は長い髪を少し弄ぶ。
それは世界で一番控えめな照れ隠し。
そこへ――。
ぴーんぽーん。
「ん?」
絶妙なタイミングでインターホンが響いた。
「誰かしら……? 訪ねてくる人なんていないはず……」
りり子がそそくさと立ち上がって様子を見に行く。
戻ってきたりり子の後ろには、見覚えのある顔が二つ追加されていた。
「やっほー。あき君に先越されてるとは思わなかったよ」
「失恋で傷心中かと思ったら……あきもやるねー」
千鶴と線太郎だった。てか、なんすか線太郎さん、そのにやにや笑いは。
「別に。笑ってないし」
いやいや、明らかに笑ってるから。(笑)が語尾に透けて見えるから。
この人たち、鋸邸の場所知ってたっけ? と訝っていたら、
「近隣の方々に聞き込んで辿り着いたんだって」と、りり子が説明してくれた。
いやはや――調子狂うよな。
線太郎と千鶴は事件の後も何も変わらない。
『名探偵』のりり子に接する時も。
へっぽこ探偵で、狂言回しで――いや、そんな大層なものですらない、あることないこと継ぎ接ぎして自分だけの夢想に酔っている、破綻者の僕に接する時も。
――どんなにかそれに助けられていることか。
「食べ放題行くよ。ケーキ屋さん」
「ほぇ?」
千鶴が意気揚々と述べた言葉が突然過ぎて、口からおかしな音が出てしまった。
「新しくできたお店。食べ放題やってるんだって」
線太郎の補足に思い当たる情報があった。僕は噂で聞いたことをそのまま披露する。
「あそこの食べ放題、後半はほとんど試練だっていうじゃん。味付け、ひたすら甘いらしいし」
「あき君、甘党でしょ? 甘党って名前の新党立ち上げるくらいの。全然平気だよー」
千鶴がしれっと答えた。
僕が肩をすくめて反応に困っていると、りり子からの目配せがあった。彼女は僕のすぐ隣まで歩み寄り、こちらに向かってすっと手を差し伸べる。
「行きましょう」
――ここから、また、一歩前に。
そんな声なき声が、彼女の表情から読み取れた気がした。
そうだ。物語は続く。
僕たちがそれを紡ぐんだ。
僕はその手をしっかとつかんで立ち上がる。
「――試練、か。試練くらい受けてしかるべきなのかもな」
線太郎が小さく零した。すっと縁側の向こうに移した視線を真似してなぞると、青すぎる空は目に痛いくらいで。
「後でさ」僕は提案する。「灘瀬先生にお線香上げに行こう」
こちらを振り返る三人。
「うん!」と千鶴。
「賛成」と線太郎。
「そうね、そうしましょう」とりり子。
夏が、始まろうとしていた。