
ロジック・ロック・フェスティバル
第四回
中村あき Illustration/CLAMP
新人×CLAMP 「新本格」推理小説(ミステリ)の正統後継者・中村あきのデビュー作! まだあった「新本格」推理小説(ミステリ)! 全ミステリファン注目の新人登場、星海社FICTIONS新人賞受賞作。
9 そして、時は来たれり
七月一日。遂に訪れた文化祭当日である。
低血圧の僕が六時近くにぱっちりと目を覚ましたのは、その頃には既に周りで活発に動き回っている人々の気配が感じられたからだ。
床に硬いマットレスを敷いただけの場所で寝ていたので、体のあちこちが痛い。なんとか軋む体を起こして昨夜の宴の片付けに加わった。体育館はもちろん本日多くの団体によって使われるので、立つ鳥跡を濁さずというわけだ。
七時から各係長が集結しての入念な打ち合わせが始まった。それが終わるとそれぞれの係に散って、時間ぎりぎりまで細かいところの最終確認だ。
開門は午前九時。しかしクラスの出し物や班の出し物の準備のために朝早くから集まっている生徒たちも多く、開門一時間前ともなるとその熱気はもはや爆発寸前にまで高まっていた。
ぶらりと一通り校内を見回った僕たち実行補佐だったけれど、手数は足りており、どこもあとはお客さんを待つばかりといった雰囲気なので手伝えるようなこともなく、結局早めに最初の持ち場である中庭の本部に向かうことにした。
そして八時五十八分。
正面玄関の大時計が二分進んでいるため、開門の許可が下りた。
待ちかねたお客さんたちがどやどやと入場し、興奮は正門からあっという間に校内の隅々にまで伝播していった。
僕たち四人は本部から中庭に流れ込む人の波を眺めていた。初っ端から本部待機とは退屈だけれど、ここには三十分から一時間のローテーションで全ての実行委員が一度は立つことになる。それなら早めに済ませておいた方がいいだろうという判断で、僕たちは自らこの時間の担当を所望したのだった。
会長と副会長も基本的にはここにいる。あとは中庭の特設ステージで使われるマイク等の機材班もこのテントにあった。つまりステージの目と鼻の先。
特にやるべき仕事もなかったので、パイプ椅子に座りながら特ステ(特設ステージの略だ)で行われる催しを眺めて過ごした。特ステ係にも何度かお邪魔して、催しの意見を出したり、小道具作りを手伝ったり、女装コンテストの衣装のマネキンにさせられたりしたっけ。
たった今一つ目の催し、ラムネ早飲み大会の決勝が終わり、次はお笑いバトルの予選が始まろうとしていた。
「――で、どうだったんだよ、あき」
ラムネ早飲み大会の優勝者が景品にラムネをしこたまもらって退場するのを拍手で送りながら、線太郎がにやにやを抑えきれないといった顔で話を切り出した。
「え、何が?」分かってたけど、僕は一度とぼけてみる。
「何がじゃないよ。仮名先輩、誘ったんだろ」
「……うん」
「どうだった?」
「一日目は基本暇だって。だからこの後一緒に回ることになってる」
「おお!」
「……今から心臓が飛び出そうなんですけど」
「これは脈アリだって。あき、分かってる? 文化祭一緒に回ろうってほぼ告白だからね」
「ですよねー……でも先輩案外とぼけてるからなあ。どう思ってるんだろ」
「ほうほう。それではどっかでびしっと言わなきゃですな」
「もう彼女いる人はいいよな、気楽でさ。どうせ来るんでしょ、今日も」
頭の後ろで手を組み合わせ、パイプ椅子の背にもたれ掛かった僕に、線太郎は気恥ずかしげに指摘した。
「……言おう言おうと思ってたけど、あれ、彼女じゃないから」
「ええ! 線太郎、あの子のこと、幼馴染みって言ってたじゃんっ」
「だから幼馴染みなんだよ。彼女じゃないだろ」
「おんなじようなもんじゃない」
「いや、そのりくつはおかしい」
「なんだっけ……いりの?」
「入野果樹」
「私立姫越女子のお嬢様でしょ。一度お目見えしたいものです」
訪れているお客さんの中にも色とりどりの制服が交じっているのが、ここから見ていてもよく分かった。
「まあ、お互い校内ぐるぐる回ってりゃそのうち会うんじゃない」
「なるほど、そだね」
「女子の方々は誰かと回るんだろうか」
そう言って線太郎がりり子と千鶴のいる方に目を向けたので、僕も釣られてそちらを見やる。
ステージ上では手に汗握るお笑いバトルが繰り広げられていた。千鶴はくだらないダジャレに爆笑し、りり子も時折目をぱちぱちさせてはいたものの概ねじっと戦局を眺め、降壇する演者たちには律儀に拍手を送っている。
千鶴が男子と並んで歩いている姿を想像してみたが、一向に画が浮かばない。今度はりり子が知らない男と二人きりで歩く様子を思い描こうとしたが、なんとなく気分が乗らないのでこれも途中でやめてしまった。
しばらくすると次の担当となる二年生の実行委員の皆さんがやってきた。交代の時間である。お疲れ様です、と会釈。
「二人はこれからそれぞれデートなんでしょ? いいなー」
会長と副会長にも挨拶をし、本部テントから出たところで千鶴が陽差しに手をかざしながら言った。なんと。お笑いバトルに夢中かと思ったら聞こえてたのか。
「じゃありりちゃん、一緒に回ろうよ。あたしお化け屋敷行きたいんだけど、一人じゃちょっと怖くて」
りり子はこくん、と頷いた。
僕らは三方向に分かれた。すなわち千鶴とりり子は旧館二階のお化け屋敷へ、線太郎は果樹ちゃんを迎えに正門へ、僕は仮名先輩との待ち合わせ場所である一階の自販機前へ。
自販機のあるドリンクコーナーは中庭からすぐだった。待ち合わせの時刻は十時。今は十五分前くらいだったけど、このままもう向かってしまって、何か飲み物でも飲んで待っていようと思った。
自販機前に到着。周囲にさっと目を配ってみるけれど、まだ待ち人の姿はないよう――と、ふと見やった新館へ延びる通路の突き当りに、小さく揺れる人影があった。匂い立つような佇まいは、遠くからでも一瞬で見分けがついて。
――間違いない、仮名先輩だ!
まるで心が通じ合っているかのようにばっちりのタイミング。意味もなく嬉しくなってしまう。いやいや、それにしても早めに来ておいてよかった。女の子を待たせるなんてもっての外だからな。
しかし仮名先輩は曲がった通路の向こう側にいる誰かと言葉を交わしているらしく、まだこちらには気付いていないようだった。相手の方まではここからでは視認できない。
一体誰と話し込んでるんだろう――そう考えた時、その相手の方がぬっと曲がり角の陰から姿を現した。というより、ずいと進み出て仮名先輩に近づいたのだ。
それは――社会科教諭の灘瀬だった。
前に出てきた灘瀬から距離を取ろうと、後ろに身を引こうとする仮名先輩。しかしあろうことか灘瀬は、そのまま仮名先輩の右腕をぐいとつかんだのだ。
「仮名先輩!」
僕は知らず叫んでいた。
明らかに驚いた様子の灘瀬は僕の存在を認めると、ぱっとつかんでいた手を離した。僕と先輩に一瞥をくれてから、そそくさとその場を立ち去る。
「あ、あきちゃん」
「大丈夫ですか?」
僕が走り寄って言うと、先輩はまるで何事もなかったような調子で答えた。
「え? うん、平気だよー」
しかし僕は今起こった出来事が頭の中でまだぐるぐると回っている。唾を飲み込んでから尋ねた。
「灘瀬ってやつ、なんか生徒にセクハラしてるとか聞きます。今まで根も葉もない噂だって思ってましたが……あいつ、先輩に何かしようとしたんじゃないですか?」
「あ、そーゆうこと? 違う違う」先輩は右手に握っていた携帯をひらひらと振った。「私が大きな声で電話しながら歩いてたら、みっともないからやめなさいって注意されただけ」
「……ほんとですか」
あれ、勘違いだったのか。
「なんかいっぱいお客さん来てるから神経質になってるみたい。まあ、あの先生普段から何かと細かいんだけど。ってか、あきちゃん、もしかして怒ってる?」
「怒ってるっていうか……なんか灘瀬に言い寄られてるように見えて気分悪かったんです。だって僕は仮名先輩のことが……」
「仮名先輩のことが?」
「え、あ、あの……仮名先輩のことが……心配、そう、心配なんですよっ。先輩、ちゃんとしてるように見えて案外抜けてるっていうか、でもそういうところも素敵っていうかで、あの……」
「そっかあ。あきちゃん、私のこと心配してくれてるんだあ。なんか嬉しい」
くすぐったそうに笑う先輩が眩し過ぎて、僕は後に続く言葉が出てこなくなってしまった。
仮名先輩は呆けている僕にさらに追い打ちを掛ける。
なんと彼女は僕の手を取って、ぎゅっと握ったのだ。
「じゃあ、時間だし行こっか。適当にぶらぶらしよっ」
灘瀬のことなんかあっという間に頭の隅に追いやられてしまった。
ああ。僕、今、世界で一番幸せかも。
10 フェスティバル・フリーク
仮名先輩は大のお祭り好きらしかった。目に入るものには片っ端から感興をそそられるようで、僕は引きずられるようにしてあちこちの出し物や展示の間を飛び回ることになった。
二年のクラスの自主製作映画、三年のクラスのボールプール、化学班の実験ショー、囲碁班の公開対局、漫画研究班の機関誌配布、オカルト班のウィジャ盤占いetc.……。
いつの間にか正午も回り、いい感じに足が棒になってきた頃、先輩は一際大きな歓声を上げた。
「ここ、メイド喫茶だって!」
目をキラキラさせながら長蛇の列を指さしている。
「ああ、はっちゃけてこういうのやっちゃうところ、どの学校にも一クラスはありますよね」
「楽しそう。入ってみよ」
当然ながら僕に拒否権はない。できることは先輩の後に従って、しずしずと教室から伸びる列の最後尾に付くことだけだ。こうやって振り回されるのも楽しいから全然いいんだけどね。
「……それにしてもだいぶ並んでますね。かなり盛況みたいです」
「きっとメイドさんが超絶美少女揃いなんだよ」
「そんなふざけたラノベみたいなこと――」
そこまで言った時、背後から甘ったるい声が聞こえてきた。
「お帰りなさいませ、王守仁さまっ。順番に並んでお待ちくださぁい」
嫌な予感がした。
『ご主人様』と掛けたにしてもこのダジャレは無理矢理過ぎる。こんな雑なボケを臆面もなくかませる人物を僕は一人しか知らない。僕は振り返って一喝した。
「千鶴! こんなとこで何やってんだよ」
「あ、バレちゃった。せっかくサービスでとっておきの萌え声出したのに。なにってメイドに決まってるでしょ。あき君の目は節穴か」
くるくるとその場で回って、スカートを翻して見せる千鶴。
「いや、そういうことじゃなく……それに王守仁て。そりゃ中国、明代の高名な儒学者であり、思想家であるところのお方だろ」
ちなみに諱である守仁より陽明という号の方で一般的には知られている。
「じゃあ、お帰りなさいませ、ご愁傷様?」
「気の毒に思われちゃったよ!」
そんなやり取りに仮名先輩が強引に割り込んだ。
「え! なにこの子っ。あきちゃんの知り合い? 可愛い! ちっこくて可愛い!」
全力で千鶴を抱きしめて頰ずりまでし始める仮名先輩。
何事かと、列に並ぶお客さんが一斉にこちらを凝視しだした。騒いじゃってごめんなさい……ってあれ? カメラ構えてる人とかいるんだけど。
「すみません、お静かに願えますか。他のご主人様のご迷惑になりますので……」
そう言って教室から姿を現したもう一人のメイドに、僕はまたまた度胆を抜かれた。
あれはなんだ? 僕の目が正しければ鋸りり子のように見えるけれど。しかし彼女がメイド服を着て、こんなところにいるはずないではないか。
「あー! あの子も素敵! めちゃくちゃ綺麗! モデルかお人形さんみたいっ」
興奮が収まらない先輩。
「あれはりりちゃんだよー。可愛いでしょ」
解説する千鶴。って、やっぱあれ、りり子だったのか。
おそらく僕の姿を確認したからだろう、目を伏せてすっと室内へ引っ込むりり子。それを列を無視して追っていこうとする先輩と千鶴。いや、ちょっとちょっと。先輩も先輩だけど、千鶴はお店側の人間じゃないのか。一緒になってはしゃいでどうする。
おかげで列は乱れ、メイド喫茶に並ぶお客さんたちは混乱し、辺りの無関係な人たちをも巻き込んで、一時廊下は騒然としてしまった。収拾がつかないのでとりあえず後のことはりり子に任せることにして、僕は先輩だけなんとか引きずって退散したのだった。
後から聞いた話によると、どうやら千鶴とりり子はメイド喫茶をやる一年のクラスの助っ人に駆り出されたらしい。注文していたメイド服が当日になってようやく届いたらしいのだが、そのあまりの露出度の高さにメイド役の女の子たちが土壇場で着用を拒否しだしたのだ。にっちもさっちもいかないところにふらふらしていた千鶴とりり子が通り掛かり、そういうことならと引き受けたらしい。やれやれ、肝が据わってるというか、怖いもの知らずというか……。しかし思い返してみるとそれぞれ似合っていなくもなかった気がする。一枚くらいは写真を撮っておいてもよかったかもしれない。
メイド喫茶に入れなかった仮名先輩はしばらく項垂れていたが、
「いろいろ回ってそろそろ腹の虫も鳴き疲れました。そろそろお昼ご飯でもどうですか?」と僕が提案するとたちまち元気を取り戻してくれた。
先輩の強い要望で焼きそばの屋台へ。時間をずらしたというのにだいぶ待たされ、無事二人分の焼きそばを購入した時には、時計は午後二時を指そうかというところだった。
方々に設置されているベンチの一つを選んで座り、焼きそばを頰張る。空腹が満たされると、ようやく人心地つけた気分になった。
しかし食後の冷たい缶コーヒーを啜る仮名先輩はまだまだ文化祭を楽しみ足りないようで。
「次はどこ行こうか……あ、あれ! あれなんてどう?」
そう言って先輩が指さした看板は、天文班プレゼンツのプラネタリウムだった。
「いいですね。行きましょう行きましょう」
「わーい」
焼きそばのごみと空き缶を抱えて立ち上がる仮名先輩。
歩きだそうとした時、先輩の上履きがきゅっと鳴ったのを聞いて、僕は先輩の上履きが学校指定のものと違うことに気付いた。今まで知らずにいたのが不思議なほどそれは中々個性的な代物だった。一応学年カラーの緑が入っているとはいえ、こんなもの校内で堂々と履いてるのは彼女くらいなもんじゃないかな。
「……? どうしたの?」
「あ、いえ、洒落た上履きだなーと思って」
「三足目だからね。ちょっと趣向を変えてみたの」
「は、はあ」
三足目? 履きつぶしちゃったんだろうか。趣向は変えんでも、って気はするけど。まあ些細なことだと思い、僕はお茶を飲み干すついでにお茶を濁した。ただ願わくば、生活指導なんかで咎められませんように。
「さ、プラネタリウム、こっちみたいですよ」
僕が気を取り直し、看板に記された矢印を確認して、先輩を促した時だった。
「中村さん!」
背後から誰かに呼び止められて。
見るとそれは全力疾走の直後と思しき副会長であった。息も絶え絶えな上、ひどく取り乱している。冷静で穏やかな普段の風格が欠片も見られない。
「はあ、はあ……やっと見つけました」
「副会長、そんなに急いでどうしたんですか」
呼吸を整えながら副会長は衝撃の事実を告げた。
「たった今……本部にいた会長が……倒れました」
「えっ!?」
思いもかけない知らせに僕は凍りついた。
デートは一時中断のようだ。
11 健康と対策
仮名先輩と別れ、押っ取り刀で僕と副会長は保健室へ急行した。
保健室に着くと、ノックも煩わしいとばかりに二人してドアを引っつかんで転がり込む。マナーは悪いが気にしている暇がなかった。消毒液の臭いがつんと鼻を突いて。
室内に保健医の姿はなかった。疑問に思った僕と同様に、副会長も辺りをきょろきょろと見回している。
「僕が倒れた会長をここに運んできました。彼女が譫言で『実行補佐を呼んでくれ』と呟いたので、保健医の先生に診断を任せ、その間に僕は飛び出してきたんです……」
副会長が言いながら見当を付けて、室内の一画にあるカーテンをそっと開けてみると、まさにそこのベッドに会長は横になっていた。
こちらに気付いたように閉じられていた目がゆっくりと開かれる。
「ああ……成宮か。すまなかったな、君が私をここまで運んでくれたっていうじゃないか。それに……中村?」
「「起き上がらなくてもいいですから会長! そのまま寝ててください!」」
もぞもぞと体を動かし、上半身を持ち上げようとする彼女を、必死になって二人で押し止める。
「中村さんがいるのは、譫言で会長が実行補佐を呼んだからですよ」
副会長の言葉を聞いた会長は、横になりながらも声だけは快活に言った。
「なるほどな……これはとんだ醜態をさらしてしまった。しかしもう大丈夫だ。過労と睡眠不足、あとは軽度の栄養失調らしい。保健医の先生も少し休めばすぐによくなると仰っていた。忙しい先生はすぐに別の急患のため、現場に直行したみたいだが……。とにかくこれ以上、何も心配いらないよ」
それを聞いて副会長の表情が変わった。途端、平素きくことのない強い語調で会長に迫った。
「『何も心配いらない』――ですって? そんなこと、この期に及んでよく言えますね! 会長はいつもそうだ。周りを案じるあまり、自分のことは後回しにしてしまって……だからあれほど食事には気を遣ってくださいと言ったじゃないですか! 一人暮らしの食生活はとかく乱れがちだからと――」
「会長……一人暮らし、だったんですか」
僕は虚を衝いて出てきた新事実に驚きを隠せなかった。
「……あ、も、申し訳ありません」副会長は我に返ったようだ。「つい、あの、軽率な口をきいてしまって……」
「……いいんだ成宮、気にしないでくれ。別にひた隠しにしている事実でもない。そうなんだ、中村。私はずっと一人暮らしなんだよ」
僕の脳裏には、ふと鋸りり子の顔が浮かんだ。会長は続ける。
「私がまだ一歳にも満たない赤ん坊だった頃、父親が愛人と駆け落ちして家庭を捨てたんだ。お互い二十五で結婚したその翌年のうちにだったといったかな。まあ、それから一度も会ったことがないから、私はその父親の顔もほとんど覚えていないんだが。今でもどこかでのうのうと教師なんかやってるそうだ。だから『衿井』も母方の名字なんだよ。その後、元々体が強くない母はショックで精神を病んで病院に入れられた。私は親戚に預けられたけれど、馬が合わなかったこともあってすぐにそこを飛び出して独立した。つまらない話だろう。しかしこんな話はドラマや映画に求めるまでもなく、掃いて捨てるほどその辺に転がっているものなんだ」
副会長は唇を嚙み締めていた。僕も二の句が継げない。
「……ああ、こんな話をするために呼んだんじゃなかったのに。だめだな、体が弱ると心も弱るというのは本当らしい。文化祭のこれからのことも考えなければならないのに、少し頭を冷やさなければ……」
副会長が会長の言葉を遮る。
「いえ、それは僕の方ですよ。実行補佐を呼ぶのだってそうでした。携帯を使えばわざわざあちこち走り回る必要もなかったんです……はあ、一度落ち着かなければなりませんね。しかし会長、冷静になって手段を講じるのはあなたの仕事ではなく、僕たちの仕事です。会長不在という状況下でのシミュレーションも行っていますから、それこそ会長のお株を奪うようですが、何も心配いりません。これからすぐに実行補佐を招集し軽く打ち合わせた後、各係長を動員して緊急対策本部を立ち上げます」
僕も気持ちを切り替えて、副会長の後を引き取った。
「今、会長になさらねばならない仕事があるとすれば、それは療養への専念です。僕たちもこのくらいのトラブルで文化祭をだめにしたりなんかしませんよ。約束します」
会長は交互に僕らの顔を見比べた。
粛然のいっとき。
やがて一つ息をつくと、彼女は強く短く言葉を発した。
「分かった。頼んだぞ」
各係長と実行補佐が集められた生徒会室。
成宮副会長が緊張した面持ちでざわめく聴衆の前に躍り出た。言葉を選びながら伝えられたのは以下の四つの事項。
会長が過労で倒れたこと。
ただ病状は軽度のものであるため心配はいらないこと。
臨時的に副会長が指揮系統の頂点に立つこと。
無用な混乱を避けるため会長が倒れたことはみだりに公言しないこと。以上。
それらを踏まえて何らかの不具合がある係はそれを報告し、その対策について検討することも行われた。会長が倒れたことによって大きく狂う計画などはなかったものの、やはり会長は全生徒の精神的支柱ともいえる存在であった。一時的とはいえ、その不在が与える影響は決して小さくない。なんとなく生徒会室を落ち込んだムードが包み、誰の顔にも不安げな影が落ちているのがはっきりと見て取れた。
「会長、どうだった……?」
各係長がそれぞれの持ち場に戻り、副会長は教員たちに事の報告をしに行ったので、たまに出入りする生徒会役員を除けば生徒会室に残るのは僕ら実行補佐の四人だけになった。
それを見計らうようにして、千鶴が心配そうに僕に尋ねる。保健室を出た後ですぐに集められた実行補佐の面々も、僕以外は実際に会長の様子を目にしたわけではない。そうなるといくら病状が軽いと言われたって、それに「はいそうですか」とあっさり納得し、心底安心する気持ちになど到底なれないのだろう。
「いつもの覇気はやっぱり感じられなかった。でも今も別に気分は悪くないみたいだったよ」
「ううん……そっか。早く良くなるといいな」
当たり前だが、千鶴もりり子もメイド服はとうに脱ぎ捨て、鷹松学園の制服に着替えている。
「パーフェクトに見える会長もやっぱり人の子なんだね」
そんな何気ない線太郎の述懐に僕は共感を覚えた。
なんだか会長のパワーを間近で感じていると、この人には普通の人間の常識を当て嵌めたくないという無茶苦茶な心情にさえなるのだ。カリスマと呼ばれるような人物を眺めるとき、その人のカリスマ的でない部分には意図せずとも目を瞑ってしまうように。
きっと彼女は孤高であり、孤独だったのだ。その孤独の深さに手を差し伸べようと努力していたのは、おそらく副会長ぐらいなものだったのだろう。
しかし会長は意識と無意識の境を彷徨いながら実行補佐を呼んでくれた。それほどまでに頼りにされている僕らは彼女のために何ができるだろう。彼女が全てを捧げた文化祭にどうやって貢献できるだろう。
「今日のところはまだいいけれど、明日までダウンってなるとどうかしら。後夜祭、ファイアーストーム、グランドフィナーレ――」
りり子が明日の後半にあるイベントを列挙した。これらは一般公開のお客さんを一旦帰したのち、鷹松学園生のみで行うものだ。文化祭の最後を飾るとあって、毎年ど派手に盛り上がるという。終わりよければ全てよし、という諺もある。さすがにそこまでいくと極論か。とはいえ、僕は意見する。
「とりあえず先手を打って措置を講じとく必要はあると思う。会長が元気になればそれが一番いいけど、もしものときのプランBみたいな」
「後になって事の真相が知れてもさ、会長が倒れてから鷹松祭がつまんなかった――なんて、絶対言わせない!」
千鶴がそう意気込んだ時、他の三人も瞳に静かな闘志を燃やしながら、しっかりと頷いた。
午後五時。一般公開終了の時刻となった。
こうして突然やってきた不測の一波乱も、迅速な対応によって一般レベルにまで波及することはなかった。何事もなくつつがなくとは言い難いものの、鷹松祭の一日目は押しなべて成功裏に終わったといっていいだろう。
その後、簡単な片付けと明日に向けての準備が行われたが、それも完全下校の六時半まで。僕たちもその頃には揃って帰宅の途に就くこととなった。
普通ならこの後、中夜祭と称されて行われる実行委員のどんちゃんも、今夜のところは中止となった。会長が倒れなかったところで、ここしばらくの疲れが溜まっている生徒は少なくなかったのである。
明日、一般公開二日目も午前九時からスタートだ。
各々が寝床の中で今日という日に起きた出来事を反芻し、感じたことを思い返しながら、文化祭一日目の夜は過ぎて行った――。
12 アイの告白
七月二日。鷹松祭二日目。
本日の太陽は昨夜の気象予報士の言葉通り、今年一番の猛暑を体現していた。
しかし鷹松学園への客足は衰えなかった。むしろ来客数は一日目を超えるスピードで伸び続け、校内には異様ともいえる熱気が渦巻いていた。保健係が放送で熱中症への注意をしきりに呼び掛けている。
会長は午後から登校の予定だという。一応、大事を取って病院で診てもらってくるそうだ。そういうこともあり、基本的に今朝から会長不在の間、実行補佐は交代で本部に立っていた。
僕の担当の時間は十一時から。五分前くらいには本部にやって来てりり子と交代した。
すぐにはすべきこともなかったので、ステージ上の浴衣コンテストをしばらくなんの気なしに望見していると、隣に座っていた副会長が携帯を手に立ち上がった。
「会長が来たみたいです」
「あれ、早いですね。まだ十一時半ってとこですよ」
「きっと我慢できなかったのでしょうね。あからさまにまだ具合が悪そうなら追い返しますよ。校門まで迎えに行ってきます」
「お願いします」
そうして副会長と連れだってやってきた会長は、しかし昨日とは打って変わった威風堂々とした佇まいを取り戻していた。完全復活をすら感じさせる面持ち。不在時の遅れを取り戻そうと息巻いているのが伝わってくるようだ。
隣の副会長はまだ不安げな様子だったが、僕もあまりに早い復調にいささか憂慮の気持ちを覚える。この人なら多少の体調不良を平気で押し隠してしまいそうだから。
「おはようございます、会長。お体の調子はどうですか?」
「おはよう、中村。ああ、すっかり元気だ。完治だな」
「……昨日の今日でそんなわけないじゃないですか。まったく」
横にいた副会長が僕にそっと耳打ちする。
会長はそれには気付かずに続けた。
「しかし迷惑をかけてしまったな。これから随所に詫びを入れて回るつもりだが、実行補佐は輪をかけて大変だったろう。この後は一度休むといい。ドタバタさせてしまった上にこの猛暑だ。昼食はまだだろう? その時間のうちに食べてきたらどうだ」
副会長も首を縦に振っている。そういうことならとお言葉に甘えることにした。
そして会長は律儀にも本当に係長たちを中心に陳謝して回り、それから帰ってきたと同時に僕は自由時間を与えられた。
ただ今の時刻は十二時を十分ほど回ったところ。線太郎でも誘ってぶらぶらと辺りを物色しようとした矢先、ポケットの中の携帯が着信を知らせた。
それは、後夜祭のタイムテーブルに欠陥が見つかった、という後夜祭係長からの連絡だった。後夜祭の目玉企画であるファッションショーの準備が遅れているらしく、それに係総出で付きっ切りのため、実行補佐に調整を任せたいということらしい。
「朝のリハの後検討したんだけど、やっぱりもう少し全体に余裕が欲しいかも。学校が閉まる時間は動かせないから、押したら押しただけ後ろのイベントに皺寄せがいっちゃうからね。体育館への誘導は委員に徹底してもらうにしても、開始時間を動かせるようなら少しでも早めてもらう感じで。あと途中休憩のうちに動く係の数、増やせるだけ増やしていいから。その間に少しでも前後の企画の準備ができるようにお願い」
後夜祭は今日の一般公開の後、三十分ほどの簡易な片付けを挟んですぐに行われる。修正できるのは今しかない。どうせどの食べ物の露店も混んでるだろうから、さっさとこっちを片付けてしまうことにした。
「分かりました。やってみます」
そう言って通話を終える。タイムテーブルの調整にはパソコンの使用が必要だった。
実行補佐に休息の時はないのだと思い知らされながら、僕は正面玄関を入ってすぐ右手にある事務室へパソコン室の鍵を借りに行くことにした。
事務室は文化祭だからといって、取り立てて特別な仕事もないようだった。
正面玄関からのお客さんを捌くのは、臨時に長机を置いて設けられた受付の役目なのである。こっちはかなり大変そうで、来賓の方々にスリッパでの入場を義務付けている関係もあり、係がほとんど躍起になってスリッパを配っている。そうすることで土足と上靴が徹底されるし、学園の床に変な靴跡がつくこともないからだろう。
確かうちの学園は珍しく、教師や事務員にも指定の上履きがあり(基本支給で、当然生徒とデザインは違うが)、揃いも揃ってみんなそれを履いていた。そんなにこの学校は床に傷がつくことを恐れているのだろうか。ふと仮名先輩の上履きを思い出し、その身が余計に案じられた。
僕は受付に注いでいた視線を戻し、事務室の窓口に呼び掛けた。
「あの、すいません」
「は、はい」
僕といくばくも歳が変わらないような男の事務員が返事をして、窓口にやってきた。『金牛』という名札を付けている。室内には彼一人のようだ。眼鏡を頭に上げているのはお洒落のつもりなのだろうか。
「あの、パソコン室の鍵を借りたいんですけど」
「は、はい。しょ、少々お待ちいた……いただけますか」そのテンパり具合から察するにまだ新人さんのようだ。「そ、それではこちらにサインの方、お願いします」
言われた通り差し出された名簿に記名をすると、事務員はそれを確認した後、部屋の奥へと引き返していく。僕はその背中をぼんやり目で追っていた。
「えーと……これ、かな?」
新人事務員は何だかぶつぶつ呟きながら壁に取り付けられた金属製の箱を物色していたが、やがて首を傾げながら一つの鍵を持ってきた。
そこはかとなく不安な感じがしたので、その場で手に取って確認してみると、鍵にはタグが付いている。そこにはひどく乱雑な文字が記してあった。
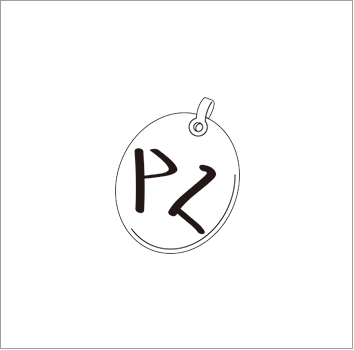
『PC』と読めないこともないから、おそらくこれがパソコン室の鍵で合ってるんだろう。鍵穴に合わなければ返しに来ればいい。
「ありがとうございます」僕は立ち去ろうとしたが、せっかくなので幾つか気になっていたことを尋ねてみた。「お名前、『かねうし』って読むんですか?」
「え? は、はい、そうですけど」
「金牛さん、目悪いんですか?」
「そうなんですよ。ど近眼なんです、僕」
「あの……眼鏡は掛けないんですか?」
「それが……さっきから見当たらなくて」
「……そうですか」
頭の眼鏡には気付いていないらしい。面白いので黙っていることにした。
一路、新館四階のパソコン室へ。
懸念とは裏腹に鍵は鍵穴にかちりと嵌まった。室内に入ると早速エアコンをつける。特権というやつだ。このくらいは許されてもいいだろう。
パソコンを起動し、さて作業に取り掛かろうかという時、入り口の扉が開いた。
「おっす、来たよ」
右手にビニール袋を提げた線太郎であった。僕が助っ人としてメールで呼んでいたのだ。首に掛けたタオルで汗を拭き拭き入ってくると、速やかに冷風の吹き出し口を探し出してそこに陣取った。
「ふー、生き返るなあ。外は地獄のような暑さだから」
「どこにいたの?」
「職員室。今あそこ、迷子の預り所みたいになってるんだよ。その子たちの子守りしたり、迎えに来た親の対応とかやってた」
「でもあそこも冷房かけられるでしょ」
「運転はさせてたけど、人でごった返してたから意味なかったよ。あそこは今日いっぱいあの調子だろうね」
「今、冷房かけられる教室はここと、職員室と、あとはこの階の社会科研究室くらいなもんだっけ」
基本、新館には冷暖房の設備がどの教室にもあったが、昨年からクーラーの調子が悪く、現在業者が入って点検、修理している状態であった。よって今、何の不具合もなく作動するエアコンは先に挙げた三つの教室のものくらいであり、それ以外は管理室で元の電源から切られているため、教室にある操作盤で何をしようと動かないのである。本格的な夏が来る前にどうにかしてほしいものだ。まあ、主に旧館で授業を受ける一年生にとってはあまり関係のない話ではあったが。
「ここで腹ごしらえも済ませちゃおうぜ」
線太郎がいたずらっぽく提案した。
「パソコン室は飲食禁止だよ」
「どうせ誰も来ないって。三階から四階に上がってくる二つの階段は、どっちも封鎖されてるようなもんだから。東側の階段には関係者以外立ち入り禁止のロープが張ってあるし、西側はそもそも修復工事中だから誰であろうと通行不可」
パソコン室は新館四階の西の端にあったので、工事中の階段の様子は僕も見ていた。なんでも雨漏りしたとかで、天井の修復をやっている。踊り場も含め、青いビニールシートが三階から四階へ上がる階段の全面に敷かれていて、厳重に誰も立ち入れないようになっていた。改めて思うとこの学校、新館の癖にガタが来過ぎである。しかし東側の階段のロープはそれに比べ、強固な壁になっているとは言い難い。
「関係者以外立ち入り禁止って関係者は立ち入り可ってことでしょ。実行委員だったらパソコン室に用がある人もいるかも」
「今、実行委員はほとんど総動員されてそれぞれの持ち場で仕事してるよ。今さらパソコン室で計画の練り直しするのなんて僕らくらいなもんさ。だから後片付けだけちゃんとやれば大丈夫だって」
「うーん……確かに」
「分かったら食べよう」言うが早いか、線太郎は持っていたビニール袋の中身を広げ始める。「おにぎりとかパンとか適当に『やまきや』で買ってきた。今の時間、模擬店すごい並んでるから」
「この暑さで行列に加わるのはキツいね。助かったよ」
食事の後は男二人、時折雑談は挟むものの至って真面目に作業を進めた。文化祭の喧噪も遠いこんなところで、お祭り騒ぎの真っ最中に何をやってるんだろうという気もしないではなかったけれど、お祭りは昨日嫌というほど楽しんだし(ついぞ邂逅することのなかった線太郎&果樹ちゃんコンビもそのようだった)、何よりこの冷房天国から出る気力が時間経過とともにみるみる減退していくのだった。
しかし、しばらくすると部屋が乾燥してきたこともあり、喉が渇いてしまった。
時計は午後二時になろうという時刻を指していた。昨日のこの時間はようやく昼ご飯にありつけてほっとしてたっけな。そろそろ休憩のし時か。
差し当たり喉の渇きと外の暑さを秤にかけていたが、心を決めて僕は線太郎に持ち掛けた。
「なんか飲み物買ってくるよ。何がいい?」
「お、さんきゅ。じゃあ夏みかんゼリーで」
鷹松学園生、夏の定番である。
「了解」
お金を受け取って外に出た途端、凄まじい熱気が襲い掛かってきた。パソコン室とのギャップで余計に体感温度が上がっているのだ。くらくらしそうになりながら、気をしっかり持ち直す。当然東側の階段から下りなければならない。工事中の西側階段を横目に向きを変え、社会科研究室の前を通り過ぎていく。
階段を下り始めると間もなく関係者立ち入り禁止のロープがお出迎え。四階から三階にかけての踊り場のすぐ下に張られている。それを跨ごうとした僕の目の端に、三階の階段口に座って話し込む二人組の女の子の姿が映った。
雰囲気から察するにどうやら先輩のようだが、なんと二人仲良く足を怪我してしまっている。ギプスの白さがやけに痛々しい。脇に二人分の松葉杖も立て掛けてあった。あれじゃ文化祭、歩き回れなくてつまんないだろうなあとか考えていたら、はっと気付いた。
それはなんと女バスの二年生の先輩、透先輩と深月先輩だったのだ。絶句していると、向こうに先手を取られた。
「おう! 誰かと思えばいつかの探偵じゃねーか」
負傷していても相変わらず声の大きい透先輩。
「あら、こんにちは。改めてだけど、あの時はありがとね」
深月先輩、律儀にお礼なんていいですから!
「そ、それより! どうしたんですか、その怪我!」
「ああ。練習中、がっつーんと接触しちゃってよ」透先輩はギプスの上から足をさすりながら、たはは、と白い歯を零した。「状況的に避けきれなかったんだ。でも三年の先輩からは『集中してないからだ!』なんてぼろくそ言われたな。文化祭はつまんねーしで散々さ」
「そうだったんですか……」笑い話にしようとしてくれているみたいだけど、班活は今大事な時期のはずだ……心配である。「雑務に追われてまったく存じ上げず……そうと知っていればお見舞いに伺ったのに」
「いいのよ、そんなの」深月先輩が手を振って。「こうなったら、あなたにあたしたちの分まで文化祭楽しんでもらうから。あ、実行補佐の仕事は疎かにしちゃだめだけど」
「はい、わかりました」と僕。「先輩たちの一日も早いご回復をお祈りしてます」
小腰をこごめてから別れを告げた。
やっとの思いで自販機前に到着した時、暑さで霞がかったような頭がぱっとクリアになった。なんとそこには自販機の取り出し口に手を差し入れる仮名先輩がいたのだ。
「仮名先輩っ」
声を掛けると先輩は缶コーヒーを取り出しながら応えた。
「お、あきちゃん。やっほー」
そして驚いたことに、その後ろにはりり子も同席していたのだ。先輩がその経緯を説明してくれる。
「そうそう、今々そこでばったり会ったの。昨日はメイド服着てたからぱっと気付けなかったんだよね。挨拶も落ち着いてできなかったし。懐かしの小原ヶ丘中メンバーだね……あ、そうだ」声のトーンを落としたかと思うと気遣うように言い添えた。「会長さん大丈夫だった? もう今日からお仕事してるみたいだったけど」
いかんせん仮名先輩は昨日、僕と文化祭を回っていたのだ。副会長の突然の招集も横で聞いていた。一般生徒で会長が倒れたことを知っている数少ないうちの一人だ。あれからメールで概要だけは知らせたが、やはり心配だったのだろう。
「やっぱり疲れが溜まってたみたいです。激務でしたから」
「そっかあ。じゃあ、あきちゃんとか周りの人たちも大変でしょ? 今もお仕事?」
「今は一応、自由時間ってことになってます。仮名先輩も今日は係の仕事あるんですよね?」
「特ステ係でほんの気持ちね。あきちゃんたちに比べたら全然だよ」
両手で包み込むようにして缶コーヒーを飲む仮名先輩。りり子もさっさと自分のジュースを買っていた。
僕もここにきた用件を思い出し、自販機に近づいてコインを入れた。まずは線太郎に頼まれた夏みかんゼリーのボタンをプッシュ。それを取り出してから、僕は炭酸の気分だったのでコーラのボタンをプッシュ。お金はぴったし。お釣りゼロ。
ふむ、しかし一気に二本買ってしまってから気付いた。僕はここで先輩とお話ししながら飲むつもりだったのだが、そうすると放置される線太郎の飲み物が温まってしまうじゃないか。
仕方ない、ごめん線太郎! と一瞬思ったけれど、仮名先輩は既にコーヒーを飲み終えそうな様子だった。僕は潔く諦めることにする。ほどなくして先輩によって干された缶は、半袖シャツから伸びる白く細い腕によってごみ箱に投げられた。
「じゃ、私は先に行くね。二人ともお仕事頑張って」
にっこり微笑んでから回れ右する先輩。しかしすぐに何か思い出したような仕草の後、
「あ。ねえ、あきちゃん」とこちらに振り返った。
「はい?」
仮名先輩は缶を放った直後の右手をそのままこちらに伸ばし、歩み寄ってくる。
両手が二本の缶で埋まっている僕の頰にそっと触れる先輩の掌。
それは温かく、すべすべとして、さらさらとして――。
「せ、先輩?」
それだけでは終わらなかった。
なぜか先輩の顔がどんどん近づいてくるのだ。
みるみるうちに視界が埋められていく。
先輩の髪の匂いが、先輩の息遣いが、すぐ間近に感じられる。
顔が燃えそうなくらいに火照っていた。
ジュースの缶が結露して水滴を纏うのに負けないくらい、汗が僕の背中を伝っている。
体は硬直して動かない。
頭はのぼせてしまって何も考えられない。
熱い。近い。熱い。唇と唇が触れる――。
――と思った瞬間、先輩の唇は僕の唇のすぐ脇を通過していった。
先輩の顔と僕の顔がすれ違うようになる。
先輩の唇が今度は僕の耳元へ。
そして――。
「――××××××××××」
「え?」
唐突な、あまりに唐突な、青天の霹靂のようなそれは。
先輩の『告白』の言葉だった。
「あ、ちょ、先輩!」
しかし呆気にとられていた僕が、それに対して返す言葉を待たず、先輩は風のように消えてしまっていた。
13 それは清き学び舎を妖しく濡らして
しばし僕は茫然としていた。
だってそうするしかない。
いきなりあんなことを言われたのでは、むしろそうならない方がおかしい。
先輩が僕を選んだ?
なぜ?
どうして?
いくらなんでも不意打ち過ぎる!
しかも先輩が去ってしまっている以上、今からその理由や真意を問うことも、僕が『告白』に対して何かしらの返答をすることも許されないのだ。
僕は考えることを放棄した。きっと悪い冗談やなんかなのだ。そう結論付ける。先輩は僕をからかって遊んでいるに違いない。
ただ、問題はもう一つあった。今しがたの一連の流れを目撃していた人物が、すぐ近くにいることを僕は視線を感じて悟ったのだ。
慌ててりり子の方を見やる。しかし少し離れた所にしゃがんでいた彼女は、何事もなかったかのように平然とジュースを啜っていた。
まあ何も見てなかったわけはないにしても、『告白』の言葉があそこまで届いたなんてことはさすがにないだろう。
僕は一連の出来事で上昇した心拍数を落ち着け、気を持ち直してからりり子に話し掛けた。
「りり子のとこにも実行補佐は自由時間だって会長からメール来たと思うけど、なんか見て回ったりしてるの?」
「……のんびり、してるわ」
「そっか。ならよかった」
それなら無理にパソコン室に引っ張っていって、男衆の仕事に巻き込むのはやめておこう。大人数でやって効率が上がる類いのものでもないし。きっと千鶴もどこかでのんびり鷹松祭を楽しんでるはず。それならそれが何よりだ。
「じゃあ、僕も行くね」
頷くりり子。
僕はゼリーの缶を持った右手を振ると、うだるような暑さの中を再び階上へと歩き始める。
どうしても気に掛かっていたことを一つだけ確認してから、パソコン室へ戻った。
室内は相変わらずのエアコン・フルパワー。
殺人的な炎天下から帰還した身にとっては嬉しいけど、ちょっと寒過ぎるくらいだ。
「遅いぞー」
線太郎の気のない出迎えにこれ見よがしに肩を落とす。ったく、ちっとは労ってくれてもいいものを。
しばしのお茶会の後、またしばらくパズルを組むような微調整が続けられた。
やれるだけの修正を施し、ようやく形としてまとまったという頃合いに、タイミングよく後夜祭係長から連絡が入った。プリントアウトしてチェックしてもらいに行こうと思っていたが、ちょうど生徒会室でパソコンを立ち上げているところらしく、それならということでそこにデータを送信させてもらった。
無事受領のメッセージが届き、内容に関してオーケーが出たことにほっとして時計を見ると、時刻は既に三時半になろうとしていた。
一般公開の終了が迫って来ていた。後ろに控えたイベントのため、今日の一般公開終了は昨日より一時間早い午後四時である。思ったよりぎりぎりになってしまったな。
二人でごみをまとめ、ぱっと見飲食物だと分からないようにカモフラージュしながらごみ箱の奥の方に押し込み(心の中で「ごめんなさい」と呟いた)、パソコン室の空調の電源を落として外に出た。
僕が鍵を掛けている最中、目の上に庇のように手をかざした線太郎が、廊下の向こうへ目を凝らしながら背中をつついてきた。
「あれ、副会長だよね?」
「え? あ、ほんとだ」
社会科研究室の前にいるのは確かに副会長だ。鍵をポケットにしまいつつ近づいてみると、少し乱暴とも思える勢いで研究室の扉をノックしている。呼び掛けたら逆に驚かれてしまった。
「あれ、中村さんに山手さん、てっきり自由に鷹松祭を回られているのかと思ってました……パソコン室で何か作業なされてたんですか?」
「ええ、まあ頼まれてしまって」と僕が答えた。「でも、もう終わって鍵を返しに行こうとしてたところです」
「それはそれは、ご苦労様でした。……いや、しかし本当に仕事に掛かりっきりになってしまったんじゃないですか? 鷹松祭、楽しめました?」
「いえいえ、実際一日目は僕もあきもしっかり遊びましたよ」とこれは線太郎。「それに今日だって随所で生徒もお客さんもみんなが鷹松祭を楽しんでいる様子を見られました。実行補佐冥利に尽きるといいますか、それを見られただけでもけっこう満足なんですよ」
傍から聞いたら優等生な回答に過ぎるんじゃないかと思うかもしれないが、しかし線太郎のこれは本心だ。なぜなら僕もそう感じているから。実行補佐はきっとこの気持ちを全員が共有しているはず。
「……頭が下がる思いです。一年生でそこまで達観なされているとは」
「ところで副会長は何を?」
そう僕が促すと、副会長は研究室のドアを示した。
「ええ。ちょっと灘瀬先生に備品の片付け場所について尋ねたくて来たんですが、応答がないんです。他の先生に居場所を訊いてきたのでここにいるはずなんですけど……しつこく呼び掛けても返事がない上に」副会長はガチャガチャとドアを揺らした。「鍵が掛かっているんです」
「ちょっと失礼します」僕は前に出て、ドアに手を掛けた。確かに鍵の掛かった感触。「灘瀬先生」
ノックして呼び掛けてもみたが結果は同じだった。
「妙ですね」
線太郎が横で感想を漏らした。
副会長が腕を組む。
「灘瀬先生といえば……確か心臓に持病をお持ちじゃありませんでしたっけ? 万が一、発作や何かが起きていたらと考えると……」
「一大事じゃないですか!」僕は予想外の事実に驚いたが、すぐに一つ閃く。「元々事務室へ行く予定でしたし、僕たちが社会科研究室の鍵を持ってきますよ」
そう申し出た時、社会科研究室から廊下を挟んで向かいにある部屋の扉が開いた。そこはちょうど正面玄関の真上に当たる部分で、二階は吹き抜け、三階は学生ホールの一部、そして四階は望遠鏡室に繫がる小部屋になっていた。鷹松学園の新館には屋根に張り出す形で立派な天体望遠鏡が備わっているのだ。基本は天文班員以外立ち入り禁止のはずだが……。
「あ、線太郎君、あき君。それに副会長じゃないですか」
しかしそこから出てきたのは、天文班でもなんでもない千鶴であった。さらに後ろから続いて出てきたのはりり子で。
「そんなとこで何してたの? 天文班に入ったなんて聞いてないけど」
線太郎が疑問を代弁してくれた。千鶴はしれっと答える。
「ああね、実はここから屋上に出られるようになってるんだよ。天体望遠鏡を囲むようにスペースがあってね、中庭を見下ろせるの。あたしとりりちゃん、特ステを上から撮影する任務を仰せつかったから、天文班の友達経由で許可取って、上からずっと撮ってたんだよ」
背後のりり子がビデオカメラを持ち上げた。なるほど、では実行補佐の女性陣も結局どっかから仕事を請け負っていたのだ。のんびりしてる、なんてりり子は言っていたけれど。
「……頭が下がります」
感心している副会長の代わりに、今度はこちら側が現在直面している状況を手短に説明した。
「大変じゃん!」
千鶴はそう叫び、りり子もその目を神経質に社会科研究室の扉に向ける。
「じゃあ僕ら」と僕は線太郎に目配せして。「鍵を取りに行きますね」
「お願いします」
答えた副会長を背に、僕と線太郎は事務室へ向かって走りだした。
四階と一階だが、空間的には社研と事務室はほぼ一直線上にある。社研の真下がちょうど事務室。しかし当たり前だけど、すとん、と落ちていくわけにもいかない。使用する階段はもちろん東側。
階段を下りる時、女バスの二年生二人組はまだ三階の階段口で話し込んでいた。軽く会釈だけしてやり過ごす。
事務室の窓口にいたのは見覚えのある顔だった。金牛事務員だ。しかしさっき彼は眼鏡を掛けていなかったから、見覚えはこちらの一方的なものだろう。眼鏡の在り処には気付けたらしく、今はちゃんと掛けていた。
「すみません、社会科研究室の鍵を貸してください」
到着するや否や線太郎が要求を突き付けた。
「え、シャ、シャカイカ……?」
勢いに押されたのか、なぜか片言の金牛事務員。
「社会科研究室です」と僕が繰り返す。「鍵を借りに来たんです」
「あ、社会科研究室の鍵ですね、しょ、少々お待ちください」
そう言って鍵のしまってある金属製の箱に近づきかけた事務員だったが、その足はすぐにぴたりと止まってしまった。怪訝そうに線太郎が尋ねる。
「……どうしたんですか?」
「あの……確かその教室の鍵はないですよ」
「は? どういう……」
「確か五、六年前に紛失してそのままになってると聞きました。特に困らないからと」
ぽりぽりと顎をかきながら答える金牛事務員。これでは緊張感に差があり過ぎている。事情の説明は不可欠か。僕は彼にごく簡略に事の次第を伝えることにした。ただし周りを気にして声量は抑える。
「でも緊急なんです。内から鍵が掛かった部屋にいるはずの教員から応答がありません。中にいると思われるその教員は心臓に持病があります」
金牛事務員の顔色が変わる。僕は畳み掛けた。
「そうだ。マスターキーを貸してください」
「えーと……でも、マスターキーは菊池さんの許可がないと……」
誰だ、菊池さん!
事務員の長だろうか。そういえば腰の曲がったおじいちゃんが、下校時刻に校内の施錠をしているのを見たことがあるような。
「じゃあ早く連絡を取ってください」
そう言う線太郎は明らかに苛立っている。
「あの、き、菊池さん携帯持ってないんです……」
「命に関わるかもしれないんですって!」
僕もさすがに声を荒らげた。線太郎が僕の肩をつかむ。
「もういいよ、あき。社研の扉を破ろう」
「え、研究室のドアを壊すんですか!? だめですよ!」
これではドアが開かない上に埒も明かない。
僕は窓口を横切って事務室のドアノブに手を掛けた。鍵は掛かっていない。そのまま事務室に押し入った。
「ちょっとなに勝手に入ってきてるんですか!」
無視して僕は鍵を保管してある金属製の箱の扉を開けた。事務員の方を向きもせず、引っ掛かっている鍵を一つ一つ検めながら僕は言う。
「マスターキーを借りるか、ドアを蹴破るか。二つに一つなんです」
ぐぐぐ……というような変な音が金牛事務員の口から漏れている。
「……分かりました、どうぞ。確か右上の方にあります」
ようやく折れてくれた。僕はすぐに目当てのものを見つける。
「ありがとうございます。それではついでなのでさっき借りたパソコン室の鍵は返しておきますね」事務員の方にかざしてから箱にしまう。そうしてから立ち上がり、マスターキーの収まったポケットをぽんと叩く。「こっちも使ったらすぐに返しにきますので」
「ああ、先ほどパソコン室の鍵をお借りになった方でしたか……分かりました。名簿にもそこに追加でこちらが記入しておきます」
僕は頷いて応え、事務室を飛び出した。
しかしそこで再び金牛事務員が一際高い声を上げる。
「ああ、そうだ! マスターキーの使用には事務員の立ち会いがいるんでした! でもここで僕が行ったら事務室がもぬけの殻に……」
「しょうがないよ、行こう、あき」
線太郎が言って、走り出す。
もう構っていられなかった。僕らは一顧だにせずスピードを上げて。
「菊池さんが帰ってきたら、僕か菊池さんがすぐ行きますからね! おーい、聞いてますかあ!」
がなる声を背に廊下を抜け、四階まで駆け上る。階段に座る透先輩が、深月先輩と顔を見合わせた後、「忙しそうだな」と笑いかけてくれたが、もう気の利いた応答ができるほど余裕はなかった。不審がられない程度に笑顔だけ作って通り過ぎた。
四階に辿り着くと、そこにはなんと会長までもが参席していた。
「鍵、持ってきてくれたか! 早く、嫌な予感がする」
既に事態も把握しているようだ。
「はい、これ、マスターキーです」
走り寄って僕がポケットから鍵を取り出すと、会長が引っつかむようにしてさっさと鍵穴へ差し込んだ。
かちり、と確かに鍵の外れる音。
社会科研究室の扉が開くと、中から冷気が溢れ出した。エアコンがかけっ放しらしい。何か異様な雰囲気と共に、確かな臭気がその中に感じ取れた。
「うっ……なに、この臭い」
千鶴が鼻を押さえる。
「――灘瀬先生、いらっしゃいますか?」
呼び掛けながら室内に足を踏み入れる会長。僕がその後に続いた。
研究室の入り口付近は左手にすぐ壁、そして右手に本棚といった配置である。そのため本棚が途切れたところで、ようやく部屋の全容が見渡せた。
目に飛び込んでくるのは痛いほど鮮やかで、残酷な色彩。
一面の赤色。
血の海。
赤の海。
そこに沈む、ぐにゃりとした男の体。
深紅に溺れる、こと切れた灘瀬がそこにいた。